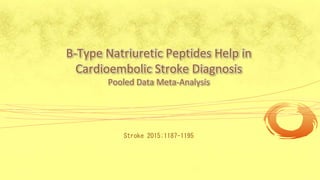2016.9.9 心原性脳塞栓症に対するbnpの有用性
- 1. B-Type Natriuretic Peptides Help in Cardioembolic Stroke Diagnosis Pooled Data Meta-Analysis Stroke 2015;1187-1195
- 2. はじめに 脳性ナトリウム利尿ペプチド(brain natriuretic peptide:BNP)は、主に心室が張った状態で心 筋細胞から分泌されるホルモンである。半減期が約20分であることより、刻一刻と変化する 心臓の状態を鋭敏に捉えることができる。 日常診療において心疾患のスクリーニングや心不全の治療効果を判定するバイオマーカーと して用いられている。 近年、脳血管障害、特に脳梗塞急性期にBNPが高値を示すと報告されている。 BNP値が140pg/ml以上であると感度80.5%、特異度80.5%で心原性脳塞栓症を他の病型分類 と識別できるという報告もある。 当院でも救急外来で脳梗塞が疑われる患者さんが搬送された際などはBNPを測定することが 多い。 ほぼroutineのように測定するBNPの意義について勉強したく今回の論文を選出。
- 3. Back Ground 虚血性脳卒中は最も重要な脳神経障害の一つである。 再発予防のための最適な二次治療を行うには、虚血性脳卒中の正確な原因分類が不可欠であ る。 心原性脳塞栓症の患者には抗凝固薬を投与するが、大血管アテロームによる脳卒中やラクナ のような小血管疾患の患者には抗血小板薬が選択される。 心原性脳塞栓症は一般的に重症化及び再発しやすく虚血性脳卒中の約1/5を占める。
- 4. Back Ground 正確な病型分類が重要ではあるものの、約35%の患者ではあらゆる評価を行っても原因を特 定できない。この患者群における発症後1年後の再発率は約30%であり、不適切な二次予防 がその一因となっている。 AFは心原性脳塞栓症の診断において検出が不可欠な頻度の高い心調律障害であるが、発作性 のことがあり、その場合標準的な心臓モニタリングで検出することは難しい。 近年、「近位動脈狭窄または高リスクの心原性塞栓源がない非ラクナ梗塞」として定義され る原因不明の塞栓性脳卒中という新しい臨床概念が提唱されている。発作性AFおよびその他 の調律障害による左心房由来の血栓性塞栓が、原因不明の塞栓性脳卒中の重要な寄与因子で あると考えられている。
- 8. Inclusion Criteria and Search Strategy 検索対象とした研究はすべて、虚血性脳卒中または一過性脳虚血性発作の確定患者の様々な サブタイプにおいてBNPまたはNT-proBNP血中濃度を測定した原著論文であった。 2013年11月12日までのPubMedデータベースを検索し、独立したレビューアー4名が論文を選 択した。 選択した研究および公表済みレビューの参考文献を手作業でスクリーニングし、その他の関 連研究を特定した。
- 9. Data Collection 選択した全研究の責任著者にEメールで連絡をとり、IPD解析のためにデータの共有を依頼し た。 脳卒中のサブタイプが判明している患者のみを対象として原因予測モデルを導き出した。こ の時点で原因不明の脳卒中患者は除外した。 次に、当初原因不明であった脳卒中患者のサブセットに対し、この導き出した予測モデルを 適用した。その結果として予測モデルに従った心原性脳塞栓症の確率を得た。モデルで予測 した原因と、完全な臨床スクリーニング後に特定され該当論文に報告された原因とを比較し た。
- 11. Results 最終的に23の論文が選択された。 18の異なるコホートを検討してお り、16コホートは原因が確定した 患者のデータ、2コホートは原因不 明の患者のデータ。 合計すると、脳卒中の原因が確定 した患者2834例の個別データが蓄 積された。 BNP値、NT-proBNP値は別々に検討 した。
- 16. Discussion 脳卒中のバイオマーカーは、脳卒中の診断、高リスク患者のスクリーニング、転帰の予測、 脳卒中原因の特定など、様々な場面で役立つ可能性がある。 今回の研究結果はBNP/NT-proBNPと心原性塞栓に起因する脳卒中との関連性を強く裏付ける ものである。 心原性脳塞栓症患者では、心原性脳塞栓症を原因としない患者に比べ、 BNP/NT-proBNP値 が高く、この差は発症後72時間まで有意であった。 抗凝固療法の最適な開始時点に関する明確なエビデンスは示されていないが、 バイオマー カーの検査により心原性脳塞栓症患者を早期に特定すれば、治療開始の意思決定プロセスの 迅速化に役立つ可能性がある。
- 18. 本研究では、 BNPとNT-proBNPの両者により、年齢、性別、入院時のNIHSSスコアに関係な く心原性脳塞栓症を予測できることが明らかになった。 これにより、初期の補助的検査では検出できなかった心疾患の特定のために、長期モニタリ ングが必要な患者を選択しやすくなる可能性がある。 循環血中BNP/NT-proBNP濃度を補完的に用いた基本的な臨床予測モデルは、AFの検出が困難 な症例における心原性脳塞栓症の診断に適している可能性がある。また、両ペプチドが心原 性脳塞栓症とそれ以外の脳卒中とをよりよく鑑別する上で役立つことが示されている。
- 19. 原因不明の脳卒中を発症した患者では、その後2年間の再発率は14~20%と報告されている が、これは主に不適切な二次予防に起因する。これらの患者は3か月後の機能的転帰も不良 であり、3年間の追跡調査における累積死亡率が高い。 バイオマーカーを併用した評価により、原因不明患者の41%が心原性脳塞栓症の可能性が高 い症例に再分類されることが報告されている。 BNP/NT-proBNPは心原性脳塞栓症に関して高い感度・特異度を示しており、診断に関して高 いエビデンスレベルを有すると考えられる。
- 20. Limitation 検討した研究の評価項目は共通しているが、各論文における発症機序の特定および原因の精 密検査は、多数の国の様々な施設において9年間にわたって行われている。したがって、原 因のサブタイプ分類の信頼性は不明確であり、バイアス源になる可能性がある。 BNP/NT-proBNP値を標準化したため、心原性脳塞栓症を鑑別するカットオフポイントを濃度 単位で示すことができなかった。 予測モデルは多数の被験者に基づいて作成したが、これらのモデルの検証に用いた原因不明 の脳卒中患者のサブセットは少なかった。 個人差による変動を回避できなかったため、 BNPとNT-proBNPを直接比較することはできな かった。
- 21. Conclusion 本研究により、虚血性脳卒中患者の心原性脳塞栓症の特定においてナトリウム利尿ペプチド の役割が裏付けられた。 侵襲的な経食道的心エコー検査やAF発作検出までの数週間から数カ月間に及ぶ経過観察に 比べ、日常臨床診療におけるナトリウム利尿ペプチド検査のほうが、抗凝固療法を開始する きっかけとして優れている可能性がある。 これと同時に、ナトリウム利尿ペプチド検査の利用により、根底にある心原性塞栓の可能性 を効率的に除外でき、経食道的心エコー検査や徹底した心拍モニタリングの必要性がなくな る可能性がある。 ~終了~