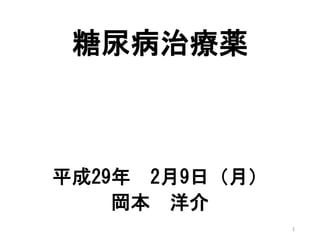
糖尿病治療薬スライド
- 2. 糖尿病 Diabetes Miletus (DM) …インスリンの作用不足による高血糖 (血糖値が180 mg/dLを超えると尿中に糖が排泄される)
- 3. 糖尿病合併症 …初期は無症状だが,健康寿命を著しく短くする • 糖尿病腎症 …透析理由の第1位 • 糖尿病網膜症 …失明原因の第2位 • 糖尿病神経症 • 動脈硬化性病変(脳梗塞,心筋梗塞) • 足壊疽 →足切断
- 4. 1型糖尿病 2型糖尿病 頻度 5% 95% 好発年齢 小児-青年 中年期 体形 やせ形 肥満 原因 自己免疫,遺伝 遺伝性,生活習慣 家族歴 少ない 高頻度 インスリン 分泌障害 高度 中等度 インスリン 抵抗性 なし あり 進行度 進行性 回復する可能性が ある 症状 急激 初期は無症状 昏睡 糖尿病性ケトアシ ドーシス 高浸透圧糖尿病症 候群 1型糖尿病と2型糖尿病
- 6. 2型糖尿病 ・血糖値:≥ 空腹時126 mg/dL ≥ 随時 200mg/dL ・HbA1c : 6.5% 以上 6 『医科生理学展望』 およそ2か月間続く高血糖を反映する
- 7. 膵臓ランゲルハンス島 7 Ross & Pawlina Histology, a text and atlas. 6th ed. Wolters Kumwer Health BioDigital • 90%が外分泌線 • 2%がランゲルハンス島 • ランゲルハンス島は膵尾部に多い
- 8. GLUT2 Cell 2012 148, 1160-1171DOI: (10.1016/j.cell.2012.02.010) 膵β細胞のGLUT2 Km 発現部位 SGLT1 0.1 - 1 小腸,腎尿細管 SGLT2 1.6 腎尿細管 GLUT1 1 - 2 胎盤,脳,赤血球,腎, 腸,胎盤 GLUT2 12 -20 膵β細胞,肝臓,小腸 GLUT3 <1 脳,胎盤,腎 GLUT4 5 骨格筋,心筋,脂肪組織 8
- 9. 9 1 mM 5 mM GLUT1 GLUT4 GLUT2 グルコース濃度 (mM) グルコース取り込み
- 10. 10 Cell 2012 ,148, 1160-1171DOI: (10.1016/j.cell.2012.02.010) 膵β細胞のATP感受性K+チャネル GLUT2 Cell 2017 ,168, 101 -110
- 12. 12 Cell 2017, 168, 101 -110
- 13. 13 代表的なスルホニル尿素薬 Cell 2012 148, 1160-1171DOI: (10.1016/j.cell.2012.02.010) トルブタミド グルベンクラミド 重大な副作用は低血糖
- 15. インクレチン関連薬 (インクレチン促進薬) http://www.msd.co.jp/healthcare • インクレチン 摂食に伴い小腸から分泌されるホルモンで,インス リン分泌を促進するもの.GLP-1とGIPとがある. 15 GLP-1 GIP Physiol Rev 2007, 87, 1409 -1439
- 16. 16半減期が長く,インスリンの分泌量の指標になる プログルカゴンとプレプロインスリン Physiol Rev 2007, 87, 1409 -1439 Ross & Pawlina Histology, a text and atlas. 6th ed. Wolters Kumwer Health
- 17. 17 代表的なインクレチン関連薬 GLP-1受容体作動薬 • リラグルチド • エキセナチド • リキシセナチド DPP-4阻害薬 『最新臨床糖尿病学』 DPP-4 … 様々な細胞に発現しているセリ ンペプチダーゼ.インクレチンを分 解する働きがある.
- 18. 18 インスリン分泌促進以外の戦略 • ビグアノイド系(メトホルミン) … AMPK活性化 • チアリゾン系(ピオグルタゾン) … PPARγ活性化 • α‐グルコシダーゼ阻害薬 … 糖吸収の抑制 • SGLUT2阻害薬 … 糖排泄の促進 インスリン抵抗性の糖尿病治療するため,あるいは 危険な副作用である低血糖を回避するため,インス リン分泌促進以外の戦略が必要
- 20. 乳酸アシドーシスの原因 『最新臨床糖尿病学』 AMPK ADP AMP Physiol Rev 2009, 89, 1025 -1078 AMP-activated protein kinase (AMPK)の働き 75歳以上には推奨されない
- 21. • 肝臓で糖新生を抑制する • 肝臓でのインスリン抵抗性が改善する • 骨格筋で糖の取り込みが促進される(GLUT4) • 乳酸アシドーシスの危険 ビグアノイド系(AMPK活性化)のまとめ
- 23. PPARγの働き
- 26. SGLT2 血糖値が180 mg/dLを超 えない限り,濾過された グルコースは尿細管でほ とんど再吸収される. • SGLT2で90% • SGLT1で10% 再吸収される.
- 28. SGLT2阻害薬の効果と副作用
- 29. 代表的なSGLT2阻害薬
- 30. 30 糖尿病治療薬のまとめ 名称 作用 代表薬 インスリン分泌促進 スルホニル尿素薬 KATP遮断 グリベンクラミド 速効型インスリン分泌促 進薬(グリニド薬) テナグリニド インクレチン関連薬 GLP-1, GIP分泌 促進 PPD-4阻害薬,リラグルチド インスリン分泌以外の作用 ビグアノイド系 AMPK活性化 メトホルミン チアリゾン系 PPARγ活性化 ピオグルタゾン α‐グルコシダーゼ阻害薬 糖吸収抑制 ボグリボース SGLT2阻害薬 糖排泄促進 イプラグリフロジン
Editor's Notes
- よろしくお願いします. 糖尿病治療薬についての講義をします.
- まず,糖尿病がどんな病気か,ということなんですけど.糖尿病っていうのは,一言でいうと,血糖が高くなる病気のことです.人の体の中で,血糖を下げる方法って一つしかなくて,インスリン,というホルモンを分泌する,ということなんです.インスリンが分泌されると,インスリンが体中を巡って,グルコースを細胞の中に取り込みなさい,と指示をだして,血中の糖が,各臓器に取り込まれていくんです.ですので,糖尿病って,インスリンの作用不足,ともいえるわけです.病名としては,尿が甘い,という意味らしいんです.Diabetes Miletusって.病院ではDM,DMて略してよびますけど.ただ,尿中に糖が出るのはかなり糖尿病が進行してからです.患者数は全国で300万人.めちゃおおいです.高血圧は1000万人なので,そこまでじゃないですけど.ほかの疾患と比べても,糖尿病は,めちゃ多いです.Common diseaseに該当します.
- 初期症状は無症状です.無症状なのに何で直さなきゃいけないかなんですが,糖尿病は高血圧と同じように,ほっとくと,重篤な合併症を引き起こすんです.病態としては細い血管が障害を受けると考えるんだと考えられています.糸球体が障害されると腎不全ですよね.本来排泄しないといけないものが排泄されないと,すごく具合が悪くなるので,透析しないといけないですね.網膜の血管がやられると網膜症.失明の原因の2位.ちなみに一位は?緑内障ですね.3位が網膜色素変性症.この網膜色素変性症をiPS細胞を移植することで直そうと,日本は今頑張ってますよね.糖尿病と関係ないですけど.それから神経症.これは手足のしびれ,とかです.この上の三つが糖尿病3大合併症というやつで,かならず覚えないといけないやつですよね.実際臨床の現場では,脳梗塞とか心筋梗塞,あと壊疽で足切っちゃってる人,Amputationを略してアンプタ,アンプタっていいますけど,も多い.と,いうように,きわめて特徴的なことは,どの科にいっても知ってないといけない疾患なんですよ,糖尿病って.適した薬を処方して血糖をコントロールするのは糖尿病内科がするのかもしれませんが,どんな薬が処方されているかぐらいは,何かの医師でも知らないといけないかもしれませんね.
- 一応,教科書的には糖尿病は1型と2型に分かれます.ただ,ほとんどは2型糖尿病です.ですので,2型糖尿病の説明を中心講義を進めていきます.ポイントとしては2型糖尿病のほうが遺伝性の素因が強いということです.1型糖尿病のほうが若年で発症するので,遺伝子疾患のような気がしがちなんですけど,実際には家族歴と相関があるのは2型糖尿病のほうなんです.インスリン作用不足の病態としては,1型はインスリンの分泌障害であるのに対して,2型はインスリン抵抗性もある.つまり,インスリンが出ているんだけれども,血糖が高くなってしまう,というやつですね.ですので,1型の治療は薬を使うというよりは,インスリンを投与することになるので,ま,それもあって,薬理の授業としては,2型糖尿病を中心に話をしていきます.
- 大事なことですけど,といいつつプリントには載ってないんですけど,糖尿病が遺伝性だといいましたが,だからといって,糖尿病遺伝子,みたいなある特定の遺伝子が変異を起こして,糖尿病になる,という単純なことではないんです.糖尿病の発症に関連のある遺伝子っていうのはこんなにあって,まだまだ毎年新しい遺伝子が見つかっていってるんですよ.典型的な多因子遺伝ですね.この場合,変異と言わずに多型というんですが,変異の場合は,ある特定の変異がある特定の遺伝子に生じていると,ハンチントン病になったり血友病になったり,嚢胞性繊維症になったりするんですが,多型の場合は組み合わせなんですよね.この多型とこの多型とこの多型をもっていて初めて糖尿病が発症する,みたいな.でもどういう組み合わせで発症するのかは実はわかってません.ここに挙げてあるのが糖尿病発祥と関係のある多型だということです.ちなみにこの遺伝子が最初に報告された多型で,今日の講義に出てきます.PPARγです.これも出てきます.ATP感受性Kチャネル.Kチャネルはもう一つあって,これはうちの石井先生が長年研究しているKチャネルですね.なんで,糖尿病と関係が強いのかはわかっていません.遺伝学上では変異と多型の違いは発生頻度の違いです.0.5%が境ですね.ですので,1000人中5人より稀に発生するゲノム上の配列を変異と呼んで,それよりよく現れる.そんなにすくなくないものを多型と呼ぶんですね.変異っていうのは一つあるだけで重篤な疾患になって淘汰されやすいので,頻度がすくなくて,多型っていうのは一つあったとしてもそれだけでは何ともないことが多いので,人口の中に残りやすいんですよね.ですが,それ故に,疾患の頻度も高くなる,Common diseaseの原因になる,ということです.糖尿病が遺伝性だというのはこういうことです.これはただ,まだ,仮設の域でCommon variant-common disease仮設とよまれていて,厳密に実証されているわけではないんですよね.
- 糖尿病の診断ですけど,無症状でも血糖値が高かったら糖尿病ですよね.食後に血糖値が速やかに戻らないのが糖尿病です.ですので,血糖値の診断基準を覚えなきゃいけないんですが,とりあえず,僕の講義ではこっち覚えますか.HbA1cが6.5%以上.覚えやすいので.HbA1cっていうのはこういう風に糖がくっついちゃったヘモグロビン.こういうヘモグロビンが全ヘモグロビンの6.5%以上になると糖尿病.本当は血糖値の基準とヘモグロビンと両方を満たさないといけないのですが,ヘモグロビンの方が検査値としての信頼性が高いので,こっちを覚えてもらいます.で,赤血球の寿命って知ってる.赤血球って核が抜けちゃってるじゃない.この状態で何日持つか知ってます? 120日ね.で,この半分の60日の高血糖を反映するといわれています.
- それで,さっきも説明したように,高血糖の原因はインスリンの作用不足なんだけれども,そのインスリンはどっから出てくるんですか?膵臓ですね.膵臓の外分泌線は十二指腸に開いて,アミラーゼとか,リパーゼを分泌するわけですよね.だからこうやって十二指腸にくっついている.こっちが膵頭部ね.90%が外分泌線.内分泌腺であるランゲルハンス島は膵臓内に散在しているのですが,どちらかというと膵尾部に多い.全部で2%.HE染色だとこういう感じに明るい部分がランゲルハンス島なんだって.このずで矢印はα細胞,グルカゴンを分泌する細胞を指していて,それ以外はβ細胞,だから,ランゲルハンス島は膵臓の2%しかないんだけど,そのほとんどはβ細胞といえるわけですよ.Β細胞がインスリンを分泌するっていうのはいいですよね.グルカゴンはα細胞,インスリンはβ細胞から分泌されるっていうのはもうやってると思うので.
- Β細胞がどうやって血糖値を感知して,インスリンを分泌するかですけど,まず,GLUT2というグルコーストランスポーターが,膵臓のβ細胞でグルコースセンサーをしています.グルコースセンサーってどういうことか説明しますね.グルコーストランスポーターにはナトリウムと共役輸送するSGLTと受動輸送するGLUTの大きく分けて2種類あって,発現している組織とKm値っていうのがそれぞれ違うんですね.SGLT1,SGLT2,GLUT1とあって,GLUT2ですよね.でβ細胞に発現しています.Km値が他と比べてやたら大きいのがわかりますよね.
- Km値っていうのはトランスポーターが各濃度でどれくらいグルコースに結合するかを測ったものなんですけど,それはそのままグルコースを取り込む速度の指標になります.マックスをここにしたときに,取り込み速度がマックスの半分の時のグルコース濃度がKm値です.GLUT1のKm値は薬mMですのでこんな感じですね.今日,講義の後半で登場してくるGLUT4はこんな感じで,Km値は5mM.正常の人の血糖値ってだいたいこれくらいなんです.1から5mMくらい.ところが,GLUT2はKm値が15とか20とかあるのでこんな感じですよね.まったく血中のグルコース濃度と比例して,グルコースを取り込むんですよ.だからセンサーなんです.
- GLUT2が血糖値に応じて取り込んだグルコースが,どうやってインスリン分泌につながるかなんですが,脱分極が起きるんですよ.心筋細胞も神経細胞も機能を発揮するために膜電位を利用していることはよく勉強していると思いますけど,β細胞も同じですね.ATPが増えるとATP感受性Kチャネルというのが閉じて,脱分極するんです.そうすると電位依存性CaチャネルからCaが流入して,Ca依存性にインスリンを含んだ小胞が細胞膜に融合してインスリンを分泌するんですね.このATP感受性Kチャネルのタンパク名をKir6.2といって,遺伝子名は先ほど言ったKCNJ11です.機能するためにはスルフォニル尿素受容体SUR1というサブユニットが必要です.スルフォニル尿素受容体,というくらいですのでSUR1にはスルフォニル尿素という物質が結合します.で,このスルフォニル尿素というのが,今日最初に紹介する薬剤です.スルフォニル尿素剤はSUR1結合して強制的にATP感受性Kチャネルを閉じてしまうんですね.そうすることで無理やり脱分極を促して,血糖値と関係なく無理やりβ細胞にインスリンを分泌させるわけです.右の図は最近わかったATP感受性Kチャネルの3次元構造ですね.ピンクとブルーのカラフルな部分がサブユニットSURで,黄色と緑がチャネルの部分Kir6.2ですね.最近ではこんなところまでわかってきたんです.
- ただですね,もともと,ATP感受性Kチャネルの存在を最初に発見したのも,このKir6.2を最初にクローニングしたのも日本人なんですよ.いまでもバリバリ研究しています.ATPで閉じてしまうKチャネル,KATPと略させてもらいますでど,KATPを見つけたのは野間先生って言います.発見当時は愛知県の生理学研究所で研究していました.クローニングしたのは稲垣先生ですね.クローニングっていうのはこのKチャネルのアミノ酸配列と遺伝子を同定することです.稲垣先生は糖尿病内科医で,今では京都大学附属病院の院長されてますけど,僕に生理学の講義をしてくださった恩師ですし,ちょっと脱線して,稲垣先生の研究の話をしますね.試験には絶対出ません.ですが,ここでしか聞けない話だと思います.稲垣先生はもともと内科医ですので,大学院に入ってから研究を始めるわけですよね.1990年代だと思います.イオンチャネルのクローニングが隆盛だった時代です.野間先生はKATPの存在をもう10年ほど前に発見していることになります.稲垣先生は糖尿病内科医で,スルフォニル尿素剤がKATPを遮断して,インスリンが分泌されることをよく知っていたので,KATPのクローニングを始めたんだそうです.内科医からいきなり熾烈な研究の国際競争の中に身を投じることになるんです.最初,どうやったかというと,ほかのNaチャネルやCaチャネルのクローニングと同様にチャネルに結合する化学物質,この場合スルフォニル尿素剤,グリベンクラミドを放射性同位体でラベルして,膵臓の中からラベルされたグリベンクラミドに結合するタンパクを生成してクローニングしようとしたんですね.しかし,これは先にやられてしまったんですよ.つまり,競争に敗れたわけです.そころが,グリベンクラミドで釣ってきたそのたんぱくは,K電流を流さなかったんですよ.つまり,スルフォニル尿素剤に結合するスルフォニル尿素受容体は,サブユニットにすぎない,ということがその時分かったわけですね.そこで,稲垣先生は,KATPは,野間先生の実験から,内向き整流性だということが分かっていたので,とうじ配列が分かっていた内向き整流性のKチャネル,Kir3.1をテンプレートとして使って,DNAライブラリーからKATPを見つけようとしたんですね.でみつかった.のですが,確かに内向き整流のKチャネルでATP感受性でもあったのですが,なんと,β細胞にそのチャネルは発現してなかったんですよ.またしても失敗したんです.稲垣先生はそのチャネルにKir6.1と名前を付けています.あきらめかけた稲垣先生ですが,最後にクローニングしたばかりのKir6.1をテンプレートに同じことをして,見事,Kir6.2のクローニングに成功します.その後,SUR2もクローニングしたので,KATP関係はSUR1以外すべて稲垣先生がクローニングしたことになります.すげー大変だったんだと思います.でも,稲垣先生は医学生に対して,僕も昔医学生だったので,医学生に対して,研究はするべきだ,と一生懸命説明してました.まず,病気の理解が深まるし,精神修行になるし,何より,医療の進歩に大きく貢献する可能性がある.からだそうです.僕の言葉じゃないので.京都大学附属病院の院長のことばなので.一応,メッセージとして残しておきます.
- 野間先生や,稲垣先生の研究がもととなって,つい今月,KATPの3次元構造が発表されました.以前,抗凝固薬のところでも話しましたが,三次元構造が分かると,今はそれをもとに薬をデザインすることができるようになってきています.実は平滑筋ではKir6.1がKATPを構成していますし,心臓でも平滑筋でもSUR2がKATPのサブユニットになっています.スルフォニル尿素剤は比較的β細胞のKATPを強く遮断するみたいなんですが,ほかのKATPも遮断してしまうので,完全に膵臓選択的な薬というわけではないんですよね.ですが,三次元構造が今年解明されたことに引き続いて,スルフォニル尿素剤に代わる,より選択的な治療薬が続々と登場するだろうと,僕は予想しています.時代が変わろうとしているんですよね.おそらく薬理学も変わっていかないといけないだろうし,医者も時代についていくことが求められるんだろうと思いますよね.研究はするべきただ,という稲垣先生の言葉をもう一度言っておこうかな.
- 何度も言いましたが,スルフォニル尿素剤,スルフォニル尿素薬っていうのはKATPを遮断してβ細胞の脱分極を促す薬です.みんなスルフォニル尿素という同じ骨格をここにもっていて,代表的な薬としては,とりあえず,試験まではこれとこれを覚えておきますか.副作用が重要ですね.低血糖.例えば心筋細胞は主に脂肪酸をエネルギー源にしてますけど,脳はほとんどグルコースだけがエネルギーなので,低血糖は,まずいんですよ.この血糖を下げすぎちゃうという副作用が,一番怖いんですよね.
- 代わりになる薬として,同じようにKATPを遮断する薬なんだけど,SU構造がなくて,SU剤とは違う場所に結合する薬があります.短時間作用型で重篤な低血糖を起こしにくい,グリニド系という薬剤があります.もちろん短時間作用なので力価はSU剤には劣ります.
- それから,間接的にインスリンの分泌を促す,インクレチン関連薬というのがあります.インクレチンというのは,摂食に伴い小腸から分泌されるホルモンで,インスリン分泌を促進するもの.GLP-1とGIPとがある.実際にはインクレチンの量を増やす薬のことだよね.GPL-1とGIPだとGPL-1の方が働きが強いので,主にGPL-1の作用を強めます.GPL-1はglucagon-like-peptide-1の略,GIPはglucose-dependent insulinotropic polypeptideの略.インクレチンはインスリンの分泌だけでなくて,グルカゴンの分泌にも影響をあたえるのですが,GPL-1はグルカゴンの分泌を抑えて,GIPはグルカゴンの分泌を増やすといわれています.GIPの働きは比較的弱いので,総じて,グルカゴンの分泌は抑制されることになり,血糖値が上がらなくなるんだね.
- GLP1はGlucagon-like-peptideだって説明しましたが,もともとグルカゴンと同じペプチドから,違う切り取られ方で生成されたものなんです.もともと遺伝子から翻訳された直後はプログルカゴンと呼ばれるながいペプチドで,それが各臓器で固有にプロセッシングをうけて,それぞれ別の生理活性物質になるんですよね.膵臓ではグルカゴンが生成されて,腸ではGPL-1が生成されます.ホルモンはこういうプロセッシングを経てから分泌されるものがほとんどで,インスリンもそうです.インスリンはプレインスリンがプロインスリンになって,Cペプチドを放出してインスリンになるんだけど,このCペプチドが半減期がインスリンより3-4倍長いのでインスリンの分泌量を測るのに適しているわけです.インスリンは一瞬で分解されてしまうので,実際には直接計測できないんですよ.一型糖尿病ではこのCペプチドが著しく低いので,客観的な指標としてⅡ型と1型の鑑別ができるんです.
- つづいて,比較的最近登場した糖尿病治療薬で,SGLT2阻害薬というのがあります.SGLT2は腎臓の尿細管に発現しているグルコーストランスポーターで,腎臓におけるグルコース再吸収の主たる役割を担っています.基本的に尿細管では一度濾過されたグルコースは全て再吸収されますが,SGLT2で90%が再吸収されます.ですので,SGLT2の働きを阻害できれば,グルコースが再吸収されず,排泄される量が多くなるので,結果的に血中のグルコース濃度が下がるわけです.
- どうして,すべてのグルコースを再吸収できるか,なんですが,SGLTはグルコースをナトリウムとの共役輸送で再吸収するからです.実際にはグルコースの濃度勾配に逆らった輸送なんですが,ナトリウムが尿細管で再吸収されるときに,利尿薬の講義のところでやったと思いますが,ナトリウムは受動的な輸送で再吸収されるんですけど,それと一緒に濃度勾配に逆らって再吸収されていくんです.で,この再吸収を阻害すると
- インスリンは各臓器,骨格筋とか,肝臓にグルコースを取り込ませて血糖値を下げますが,SGLT阻害剤は体内のグルコースを排泄して,体内のグルコースの総量を下げてしまうので,どうなるかというと,もちろん血糖値を下げるのですが,体重が落ちる,という効果が期待できます.夢のやせ薬として,よの
- リンゴの根の皮,フロシジン
