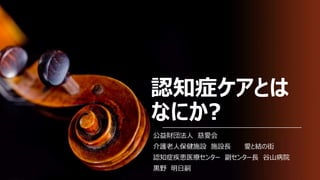
認知症ケアとはなにか?
- 1. 認知症ケアとは なにか? 公益財団法人慈愛会 介護老人保健施設施設長愛と結の街 認知症疾患医療センター副センター長谷山病院 黒野明日嗣
- 2. 認知症とはどういう病気? • 医学的に • 関係性でいうと • 脳に器質的な異常があること • 記憶や言語などの複数の認知機能が障害 • 後天的に障害される • 慢性に持続する • 社会生活活動水準が低下する 目黒謙一2004
- 4. 人と人の関係の成り立ち • コミュニケーションによって支えられる • 社会生活を営む人間の間で行われる知覚・感情・思考の伝達 • 動物個体間での、身振りや音声・匂い等による情報の伝達 • 動物との大きな違いは「言葉」を使えること • 言葉を使うことによって、より深く分かり合え、共感することができるから、 強い安定した関係を築くことができる
- 5. コミュニケーション • 言語性と非言語性 • 非言語性の情報伝達 • 顔の表情、顔色、視線、身振り、手振 り、体の姿勢、相手との距離、位置関 係など
- 6. 認知症は • コミュニケーションが下手になる病気 • 人間関係に影響が及ぶ病気である • 人間関係を円滑にする能力を失う病気
- 7. アルツハイマー病の言語性コミュニケーション • 言語の音韻情報(言葉の音情報)や統語能力(文字の 配列)はある程度保たれているが、意味情報の処理が困難 で、状況判断も悪く、言語を上手く活用できない • 具体的には喚語困難(呼称障害、語想起の障害)から始 まり,進行すると理解に障害が及ぶが,それに比較して復唱 は比較的保たれる(松田実東北大学准教授) • 言葉が出てこずに「あれ」「それ」が多くなる • 言葉を思い出そうとしているうちに何を話していたのかわからな くなる
- 8. アルツハイマー病の非言語性コミュニケーション • 案外保たれている • 認知症が進行しても、表情・視線・ジェスチヤーといった社会 的シグナルの認知能力や、握手・挨拶といった社会的慣習 遂行能力は比較的残存しやすい • 国立長寿医療センター脳機能診断研究室中村昭範先生
- 11. 認知症の方が置かれている状況 • 目が覚めたら、あなたは東南アジアのある国のホテルの一室に いました。外からは聞き慣れない言葉が聞こえてきます。 • さて、この時あなたは何を感じていますか?
- 12. アルツハイマー病の場合 • 覚える能力を失っている • つまり • 海馬を使わない即時記憶(10-30秒) • 遠隔記憶(古い記憶・思い出) • だけで生きている • 常に新しい環境
- 13. 海馬を使う記憶 海馬 短い時間保存(近時記憶) 一時的に保存(即時記憶) 記憶の形 長い時間保存(遠隔記憶) HDS-R 桜猫電車 はい HDS-R さっき覚えた のは何?
- 14. アルツハイマー病では • 記憶ができないので、言語性コミュニケーションだけでは安心さ せることができない • 正確に言うと30秒間は即時記憶のお陰で安心できるが、そ れ以上の時間は覚えることができないので、再び不安になって しまう • 話し続けるしかない!?
- 15. でも実際は • 入所してから1ヶ月も経つと、安心できるようになる • 不安から発生する帰宅願望もなくなる • なぜか?
- 17. 扁桃体が重要な役割を担う • 扁桃体は喜怒哀楽を司る • 扁桃体には感覚野(視覚、聴覚、体性感覚、嗅覚、味 覚)からの情報入力と、前頭葉からの情報入力がある • これらの感覚情報から記憶を作る • それが
- 18. 情動記憶 • 感情の負荷によって記憶する • 扁桃体は感情に関係がある • 記憶の回路とつながっており、感情を元に記憶 する • 阪神淡路大震災を体験したアルツハイマー病の 患者に震災のことを尋ねたところ、怖い思いをし たということをよく覚えていた
- 19. 楽しいことも覚えている • 5秒後にはすっかり忘れてしまうAさん • 孫の結婚式に出席して上機嫌 • 帰ってきてひとしきり結婚式の話をする • なんと3日間話せた! • よっぽど楽しく幸せな時間を過ごしたのだろう
- 20. 情動記憶を強化する • 扁桃体への入力系 • 感覚野(視覚、聴覚、体性 感覚、嗅覚、味覚)からの情 報入力と、前頭葉からの情報 入力がある
- 21. ユマニチュード? • 勧めているわけではないが、理にかなっていると思われる • 別にユマニチュードと言わなくても、我々はそういうケアを目指し てきた • それらをうまく体系化したのがユマニチュードなのではないか? • こういう理屈を理解して自信を持ってケアしていきましょう
- 23. コミュニケーションとは? • 例えば • 初対面の方と出会った時 • 助けて欲しいと思った時 • 思い通りにならない時 • 安心したい時
- 25. 初対面の人とあった時 • あなたはどういう声で話しますか? • 優しく • 穏やかに • ゆっくりと • 内容を考えながら • 言葉を選びながら • 相手の表情を確認しながら
- 28. 安心したいとき
- 29. お気づきの通り • 認知症の方が • 初めて入所した時(初対面の方と出会った時) • 困った時(助けて欲しいと思った時) • 混乱した時(思い通りにならない時) • 安心したい時
- 30. 認知症があってもなくても • 人と人の関係という点では同じこと • コミュニケーションが大事 • さらに言葉によらないコミュニケーションは大事 • 認知症の方はある意味「素直」 • いやなものはいや
- 31. 私が私でいられる
- 32. 抜け殻仮説と関係論 • 抜け殻仮説 • 脳細胞の変性により、健常な状態から、認知症になり、やがて人格が失 われて、空っぽになる • パーソンの捉え方 • これが自己であると自覚する意識の核が存在するという実体論 • 関係論 • 人格として周囲の人から扱われるから人格なのだという関係論 • パーソン・センタード・ケア 箕岡真子東京大学大学院客員研究員
- 33. 昔は 抜け殻仮説だった
- 34. イギリス・ヨークシャー・アッシュルティ病院の老 人病棟で起きた奇蹟 • アッシュルティ病院の老人病棟で一人の老婦人が亡くなりました。 • 彼女の持ち物を調べていた看護師が、彼女の遺品の中から彼 女が書いたと思われる詩を見つけました。 • 彼女は重い認知症でした。
- 35. 『目を開けて、もっと私を見て』 何が見えるの、看護婦さん、 あなたには何が見えるの? あなたが私を見るとき、こう思っているのでしょう。 気むずかしいおばあさん、 利口じゃないし、日常生活もおぼつかなく、 目をうつろにさまよわせて、食べ物をぽろぽろこぼし、 返事もしない。
- 36. あなたが大声で「お願いだからやってみて」 と言っても、 あなたのしていることに気付かないようで、 いつもいつも、靴下や靴をなくしてばかりいる。 おもしろいのか、おもしろくないのか、 あなたの言いなりになっている。 長い一日を埋めるために、 お風呂を使ったり、食事をしたり。
- 37. これがあなたが考えていること、 あなたが見ていることではありませんか? でも目を開けてごらんなさい、 看護婦さん、あなたは私を見てはいないのですよ。 私が誰なのか教えてあげましょう。 ここにじっと座っているこの私が、 あなたの命ずるままに起き上がるこの私が、 あなたの意思で食べているこの私が誰なのか。
- 38. 私は十歳の子供でした。 父がいて、母がいて兄弟、姉妹がいて、みなお互いに愛し合っていまし た。 十六歳の少女は足に羽をつけて、 もうすぐ恋人に会えることを夢見ていました。 二十歳でもう花嫁。私の心は躍っていました。 守ると約束した誓いを胸に刻んで。 二十五歳で私は子供を産みました。 その子は私に安全で幸福な家庭を求めたの。
- 39. 三十歳、子供はみるみる大きくなる。 永遠に続くはずのきずなで母子は互いに結ばれて。 四十歳、息子たちは成長し、行ってしまった。 でも夫はそばにいて、私が悲しまないように見守ってくれました。 五十歳、もう一度赤ん坊が膝の上で遊びました。 私の愛する夫と私は再び子供に会ったのです。
- 40. 暗い日々が訪れました。 夫が死んだのです。 先のことを考え----不安で震えました。 息子たちはみな、自分の子供を育てている最中でしたから。 それで私は、過ごしてきた年月と愛のことを考えました。
- 41. 今、私はおばあさんになりました。 自然の女神は残酷です 老人をまるでばかのように見せるのは、自然の女神の悪い冗談。 体はぼろぼろ、 優美さも気力も失せ、 かつて心があったところには、今では石ころがあるだけ。
- 42. でもこの古ぼけた肉体の残骸には、 まだ少女が住んでいて、 何度も何度も、私の使い古しの心をふくらます。 私は喜びを思い出し、苦しみを思い出す。 そして人生をもう一度、愛して生き直す。 年月はあまりに短すぎ、あまりに早く過ぎてしまったと私は思うの。 そして何者も永遠ではないという厳しい現実を受け入れるのです。
- 43. だから目を開けてよ、看護婦さん----目を開けてください。 気むずかしいおばあさんではなくて、 「私」をもっとよく見て。 出典「変装-私は3年間老人だった」パット・ムーア
- 44. この方は • 周りの人がそういう人であると扱うから、そういう人としてしか生 きられなくなってしまった • この方には他に選択肢がなかった • 選択肢がないのは大変辛く、悲しいこと • それが表現できたのは奇跡といえる
- 45. 尊厳を守る • よく言われますが、みなさんはどうやって尊厳を守っていますか? • 尊厳とは • とうとくおごそかなこと。気高く犯しがたいこと。また、そのさま。 • 大辞泉
- 46. 尊厳を守る • 関係論 • 人格として周囲の人から扱われるから人格なのだという関係論 • 皆さんのおかげ様 • 認知症の方が、認知症の患者になるか、普通の人と同じであ るか、それは、あなたがその方のことをどう思うかで決まる • 尊厳を守るとはそういうことなのではないか?
- 48. 尊厳・関係を損なうもの • BPSD:認知症の行動・心理症状 • Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia • 脳神経の障害部位で直接起こる症状(中核症状)以外 の症状の総称である • 行動症状 • 暴力、暴言、徘徊、拒絶、不潔行為、異食など • 心理症状 • 抑うつ、不安、幻覚、妄想、睡眠障害など
- 49. 周辺症状とBPSD • ほぼ同じ意味で使われていましたが、それはアルツハイマー病 での話 • 他の認知症では中核症状なのか、周辺症状なのか、分ける のが難しい例が出てきた • 日常の診療やケアではBPSDと言ったほうが理解しやすい • 今回はBPSDとして話します
- 50. BPSDの分類 • 第1群:頻度が高い、厄介 • 幻覚、妄想、抑うつ、不眠、不安、攻撃、徘徊、不穏 • 第2群:頻度は中程度、やや厄介 • 誤認、焦燥、不適切な行動や脱抑制、放浪 • 第3群:頻度は少ない、管理可能 • 泣き、暴言、意欲低下、繰り返し質問、つきまとい • 国際老年精神医学会議IPA,2000
- 51. BPSDは外から引き起こされる • 楽天的なひと、神経質な人、怒りっぽいひと、粘り強いひと、く よくよするひと、飽きっぽいひとetc
- 52. BPSDは自然に発生するのではない • 出るべくしてでている • どういうことで出てくるのか • そこには「からくり」があった!
- 53. BPSDの“からくり”
- 54. BPSDの“からくり” • エスポアール出雲クリニック高橋幸男 • 精神科治療学29(8)1011-1016,2014 • 認知症の方々の言葉から、その方の不安や辛さを推定した • 8ステップを経てBPSDが悪化していく
- 55. “からくり“1 • 認知症の人の多くは病状の進行に不安を感じているが、軽 度の段階でも言葉がタイミングよく話せなくなり口数が減る • 話せても内容がちぐはぐになりやすい
- 56. “からくり”2 抜け殻仮説 • 自然な会話ができにくくなった認知症の人は“わからなくなった 人”と思われて周囲からのさりげなく温かい声 掛けが激減する
- 57. “からくり”3 • 中核症状による生活上の失敗のために公私とも種々の役割 を奪われて居場所を追われやすい
- 58. “からくり”4 • 周囲の人と会話が減る中で、次第に友人や知人それに家人 など身近な人とのつながりを失っていく • やがて地域でも家庭でも孤立し、不安の中で、孤独で寂しく、 寄る辺のない状態になる
- 59. “からくり”5 • 家人に中核症状による不自由や失敗を病だと認めてもらえず、 “しっかりして”と励ましや願望の“指摘”をされる • 認知症の人はそれらの指摘を早期から「叱られる」と受け止める
- 60. “からくり”6 • 本人の苛立ちより家人の苛立ちのほうが強く、多くの家人は次 第に眉間にしわを寄せた厳しい表情で“指摘”するようになる
- 61. “からくり”7 • 寄る辺のない状態で、日常的に厳しい表情で叱られるという ストレスを受け続け、尊厳を失い、限界が来た時に種々の BPSDにつながっていく
- 62. “からくり”8 • BPSDが生じると、身近な人の“指摘”(叱責)が強まり、 BPSDをさらに悪化させ、身近な人も苦しめるという悪循環に 陥る • 身近な人も介護に疲れ果ててうつ状態になりやすい
- 63. どうでしょうか? • 我々にも当てはまりませんか? • 夫へ、部下へ、上司へ
- 64. この“からくり”を知ることで • 優しく話しかけることの重要性 • 温かい会話の重要性 • 表情の重要性 • 役割、居場所の重要性
- 65. 私たちのケアが 目指す方向
- 66. いい関係でいられること • 人と人の関係を壊す病気だから、その治療の方向は関係をい いものにすること • 医学的には治療目標が立てられないので、ケアの目指す方 向の共有はとても大事 • 人は社会的動物なので、いい関係でいられることは、幸せな 最期を迎えるうえでも大事なこと
- 67. なぜいい関係が必要なのか? • いい最期を迎えるために必要 • 皆さんの患者、ご利用者はおいくつですか? • 平均余命は何年でしょうか? • 意識したことがありますか?
- 68. 年齢 避けて通れない問題 • いつかくる人生の終わり 表1 主な年齢の平均余命 男女 平成24年平成23年前年との差平成24年平成23年前年との差 0歳79.94 79.44 0.50 86.41 85.90 0.51 5 75.19 74.71 0.48 81.67 81.19 0.48 10 70.23 69.77 0.46 76.70 76.24 0.46 15 65.26 64.81 0.45 71.72 71.28 0.44 20 60.36 59.93 0.43 66.78 66.35 0.43 25 55.52 55.10 0.42 61.85 61.45 0.40 30 50.69 50.28 0.41 56.94 56.56 0.38 35 45.85 45.47 0.38 52.04 51.69 0.35 40 41.05 40.69 0.36 47.17 46.84 0.33 45 36.32 35.98 0.34 42.35 42.05 0.30 50 31.70 31.39 0.31 37.59 37.32 0.27 55 27.23 26.95 0.28 32.92 32.68 0.24 60 22.93 22.70 0.23 28.33 28.12 0.21 65 18.89 18.69 0.20 23.82 23.66 0.16 70 15.11 14.93 0.18 19.45 19.31 0.14 75 11.57 11.43 0.14 15.27 15.16 0.11 80 8.48 8.39 0.09 11.43 11.36 0.07 85 6.00 5.96 0.04 8.10 8.07 0.03 90 4.16 4.14 0.02 5.47 5.46 0.01 • 人間の死亡率は100%。かならず死は訪れる • 認知症の方の場合 • 食事を摂らなくなる • 嚥下能力があっても、本人が食べる意思がないし、むしろ拒絶すらする • そのような状況で選べる選択肢とは
- 69. 医療の進歩と死 • 動物は餌を自分で取れなくなったら死ぬ • 人間は助け合うため、自分で食事が取れなくなったら死ぬことはなくなった • 動物は病気になったら死ぬ • 人間は医療という道具を発展させ、病気で死ぬ確率が低くなった • やがて人間は医療という道具を使って死を回避しようと考えた • その結果、自分で食べられなくても栄養を取れるようになった • 動物とは違う最期の迎え方になった
- 70. 5つの選択肢 • 食事をとらない • 提案できるのは 自?然
- 71. 悩み方に気をつけないといけない • 自然を選んだ時がその人の寿命 • あとはすべて延命 • 長く延命するか、短いかの違い • まずは、延命するのか、自然に任せるのか
- 72. 本当に悩むべきは時間の価値 • 残された時間の長さの価値 自然 点滴 IVH 鼻腔 胃瘻
- 73. 本当に悩むべきは時間の価値 • どの選択肢を選んでも最期亡くなることには変わりない • 時間の長さが違うのみ • ご本人にはどういう意味があるのか悩む • 例えばPEGを選択した場合 • 現在の食べられない状況は変わらない(=食事の楽しみがない) • ベッド上で過ごす時間がこれからも続く • その伸びた時間がご本人にとってどういう価値を持つのか 子供にとって の意味、価値 ではない
- 74. 延命は悪くない • 悪いのは、幸せのない延命 • 特別養護老人ホームでの状況 • ご本人は本当に希望されていたのだろうか? • 本人が決めたのだろうか?
- 75. どれだけ、悩めたか? • 本人が決めていない場合、周りの人が決めないといけない • 簡単には決められない問題 • 昨日決めたことが、今日は覆るのは当たり前 • 心は大きく揺れていい • その時必要なのは、一緒に悩んでくれる人の存在 • 一生懸命悩んで、決めてほしい
- 76. 皆さんが家族と向き合う • 家族がどの選択肢を選ぶのか、一緒に悩みに付き合う • 家族の疑問に答える • 自分の価値観を押し付けない • あくまで家族が、本人の気持ちになって悩んでもらえるように支援する • 決定がぐらつくのはあたりまえ • それにいかに付き合えるか • 最後決めたら、それが正解 • 全力で正解を支援する
- 77. みなさんと認知症
- 78. 皆さんがケアする対象 • 認知症の方とその家族 • いい関係が目的なので当然、両者へのケアは必要 • 関係論で認知症の方の存在を支える • いい最期を迎えるために
- 79. スタッフによく言っていること • 挑戦してください • あなたが何を考え、どうやったか • それが全てです • 地域は関係ない!
- 80. まとめ • 認知症の持つ人と人の関係を崩すという症状を食い止めることの重 要性 • それは、認知症の方のためだけではなく、私達の日常でも必要なこと • お互いを認め合う関係が関係をよくする • そのためには日頃のコミュニケーションは重要 • さり気なく温かい声掛け! • 認知症の方の尊厳が守られる、すなわち、我々の尊厳も守られる • いい最期を迎えられる
Editor's Notes
- 共感とは、相手が痛いと言った時に、過去の経験から同じような痛みを感じることができるようなもの
- なにもしないのではなく、そのまま看取る(大往生)
