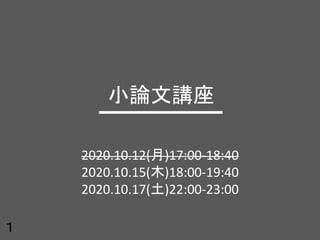
共創学部2
- 2. 今日のTOPIC テーマ「九州大学共創学部2020年 設問1 問2」 (試験時間:全体で180分 300点満点) ①前回の復習 ②問題点と原因の整理 ③添削 ④問2の解答例 2
- 3. ①前回の復習 3
- 7. ②問題点と原因の整理 9
- 8. 【資料1~5、11の読み取り】 資料1 世界遺産の定義 →世界遺産とは、過去から現在に引き継がれ、世界中の人々が保護すべきものである。 1972年の第17回UNESUKO総会によって採択され、2019年現在193カ国が加盟しており、 1120件の世界遺産が登録されている。 資料2 世界遺産の登録基準 → ・真実性や完全性の条件を満たす ・締約国の国内法によって、適切な保護管理体制がとられていることが必要 資料3 世界遺産の分布図 →ヨーロッパ、海の近くの登録が多い 資料にはないが諮問機関の人間がヨーロッパの人が多い 資料4 世界遺産の累計登録数の変化 資料5 世界遺産の登録へ向けた手続き 資料11 登録が解除された世界遺産 →文化の価値が変化している文化遺産は登録数が増加し、諮問機関の審査が甘くなってい る。一方もともと登録数が少ない自然遺産は人的要因によって自然遺産を解除されやすくも なっている。 10 どう問題? どう問題?
- 9. 【資料6~10の読み取り】 資料6 近年の世界遺産委員会の審査状況 →諮問機関の権力が反映されていなかったが、2013年当たりから 改善されている。 資料7 世界遺産登録後の集客推移 資料8 知床の年度別観光客数 資料9 首里城公園の年度別入園者数 →登録直後は観光客が減り、その後緩やかに上がるが、地域による。 資料10 観光客の推移に関するデータ →白神山地は順調に上がっている 上がる場所と上がらない場所が ある。 11 なぜ減ったのか?
- 11. 4
- 17. ③添削 7
- 21. ④問2の解答例 19