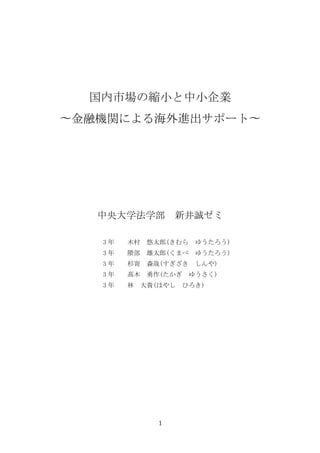
国内市場の縮小と中小企業
- 1. 1 国内市場の縮小と中小企業 〜金融機関による海外進出サポート〜 中央大学法学部 新井誠ゼミ 3 年 木村 悠太郎(きむら ゆうたろう) 3 年 隈部 雄太郎(くまべ ゆうたろう) 3 年 杉嵜 森哉(すぎざき しんや) 3 年 髙木 勇作(たかぎ ゆうさく) 3 年 林 大貴(はやし ひろき)
- 2. 2 要旨 現在、日本では、他国では例を見ないほど急速に少子高齢化が進んでいる。この影響か ら人口減少が進んでいることに加え、生産年齢人口が人口に占める割合も、今後減少して いくことが予想される。人口の全体数の減少に加え、高い購買力を持つ生産年齢人口の減 少は、国内市場の縮小につながる。これは、国内市場を主なターゲットにしている企業に とって大きな問題である。そこで、企業の長期的な成長のためには、海外市場に進出する 必要だろう。特に、日本経済全体の活性化を目指すならば、大企業のみならず、中小企業 の海外進出も不可欠である。 しかし、中小企業が海外進出する際には、資金調達の困難性と海外市場についての情報 不足が大きな障壁となっている。そこで、我々は、金融機関による信託を用いたクラウド・ ファンディングと、企業に対して海外市場の情報などを提供する専門機関の支援を複合的 に用いることで、中小企業の海外進出の障壁を取り除くことを提案する。 従来では、金融機関から資金を調達することが困難であった企業の新たな資金獲得源と して注目されるクラウド・ファンディングであるが、出資者にとってのデメリットも大き い。具体的には、資金を受け取る企業側の信頼性やクラウド・ファンディングを運営する 事業者の倒産のリスクが挙げられる。しかし、我々の提案する金融機関による信託を用い たクラウド・ファンディングでは、金融機関がポータルサイトを運営し、出資者と信託契 約を結ぶことで、上記のリスクを改善する。 また、金融機関と情報提供の専門機関との連携によって、中小企業の情報不足の改善が なされ、海外事業の成功率も上昇すると考えられる。事業の成功率が上昇すれば、そこへ 投資する出資者のリスクも改善されるだろう。 我々の提案する制度では、以上のような利点に加え、金融機関にも、新たな顧客獲得の 可能性や収入源の獲得などのメリットが見込まれる。 以上が我々の提案する制度による効果であるが、実用化への課題も残る。具体的には、 出資者の安全と中小企業の事業の広範な公開によるリスクとの調整から、金融機関が運営 するポータルサイトに、企業の情報の範囲をどのような基準で設定するかについては、今 後検討する必要がある。
- 3. 3 【目次】 はじめに 第1章 日本の中小企業の現状 1−1 国内市場の縮小 1− 2 海外進出の状況 1− 3 海外進出において解決すべき課題 1−3−1 資金調達面の課題 1−3−2 情報不足による課題 第2章 クラウド・ファンディングによる資金調達 2−1 クラウド・ファンディングの仕組み 2−2 利用者への影響 2−2−1 中小企業にとってのメリット・デメリット 2−2−2 出資者にとってのメリット・デメリット 2−3 クラウド・ファンディングに関する法改正 2−3−1 改正内容 2−3−2 出資者のデメリットにおける課題 2−4 課題に対する解決策 第3章 制度提案 3−1 概要 3−1−1 金融機関による信託を用いたクラウド・ファンディング 3−1−2 金融機関と専門機関の連携 3−2 課題の解決 3−2−1 資金調達に対して 3−2−2 情報不足に対して 3−3 新たなメリット 3−3−1 中小企業 3−3−2 出資者 3−3−3 金融機関 3−4 今後の課題・展望 おわりに
- 4. 4 はじめに 現在、日本企業でグローバルな事業展開を行う企業が多く存在する。海外に進出する国 内企業は年々増加いており、今後も増加していく見込みである。この背景には、日本社会 が抱えている「少子高齢化に伴う人口減少」という大きな問題がある。人口が減少するこ とは、企業活動の面から考えると、労働者及び消費者が減少するということを意味する。 特に、消費者が減少することは日本の国内市場の縮小に直結する。国内市場が縮小すると、 国内需要が減少し、企業間での競争が厳化する。したがって、国内企業が今後さらなる発 展を考えるならば、国内市場の縮小を見越して海外の需要獲得も視野に入れる必要がある。 そして、人口減少が改善されない以上、国内企業にとって海外進出は行わなければならな い事業になりつつある。 しかし、すべての国内企業が海外進出を行えるわけではない。特に、資金力や海外事業 における情報が不足している中小企業は、海外進出の意思を持っていたとしても、容易に 海外進出を行うことはできない。 そこで我々は、中小企業が抱える資金調達と情報不足の課題を解決し、中小企業の海外 進出を促進させることができる新しい制度として、金融機関による信託を用いたクラウ ド・ファンディングと企業に対して海外進出の情報提供を行う専門機関による支援を複合 的に用いる新制度を提案する。 第 1 章 日本の中小企業の現状 日本に存在する企業のほとんどは中小企業であり1、各国へ積極的に商品を輸出する大企 業と比較すると、資金力や人員だけでなく活動そのものの規模が小さい。そのため、国内 を中心に活動する企業がその多くを占めている。しかし、現在進行している日本における 人口の減少は、国内市場の縮小をもたらし、国内でのみ活動する中小企業にとっては大き な影響が発生することが想定される。したがって、長期的に見れば、日本国内のみで活動 を行うのみならず、積極的に海外進出をすることが多くの企業にとって望ましいと考えら れる。 1−1 国内市場の縮小 1中小企業白書概要によると、中小企業とは、業種によって定義が異なる(具体的には、サービス 業であれば、資本金 5000 万円以下で、従業員 100 人以下の企業が中小企業に該当する)ものの、 日本の企業(約 421 万社)のうち、約 99.7%が中小企業である。 (中小企業庁 『中小企業白書概要』 2016 年版 2 頁.)
- 5. 5 現在、少子高齢化に加え、合計特殊出生率が徐々に低下していることや、戦後に起きた ベビーブームによって一時的に出産数が増加したことで、人口比の偏りが生じている。こ れに対しては、有効な対策は進んでおらず、この状況が続くと、図 1 のような人口推移と なることが予測される。これを見ると、65 歳以降の増加に対し、労働に従事する 15 歳か ら 64 歳までの人口および 14 歳以下の人口が急速に減少している。2010 年と 2060 年を 比較すると、全人口に占める 65 歳以上の割合(高齢化率)が増加しており、今後も少子高齢 化が続くことが予想される。 図 1 人口推移予測 (総務省ホームページを基に筆者作成2 ) 人口の大幅な減少が起こるということは、商品の購入やサービスを受ける消費者とな る人口が少なくなるということである。したがって、国内における多くの業界の市場規模 は自然と縮小されることになり、各企業の商品やサービスが以前ほどの売り上げが期待で きなくなることが予測される。また、多くの老年人口を少ない現役世代で養わなければな らないため、現役世代の負担が増え、消費支出に使用可能な金額もより少ないものとなる と考えられる。 以上のようなことから、日本の市場は今後、縮小することが想定される。 1−2 海外進出の状況 2 2010 年までは国勢調査、2013 年は人口推計 12 月 1 日確定値、2015 年以降は国立社会保障・ 人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成 24 年 1 月推計)」の出生中位・死亡中位仮定によ る推計結果より作成 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 65歳以上 2925 3612 3685 3868 3768 3464 15~64歳 8103 7341 6773 5787 5001 3464 14歳以下 1680 1457 1204 1073 939 791 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 (人)
- 6. 6 このような国内市場の将来的な見通しが厳しい状況において、大企業は海外に積極的な 進出をすることで、その影響を緩和している。しかし、大企業ほどの資金力や規模を持た ない中小企業にとって海外進出は困難となる場合が多い。上述のように、国内市場が縮小 し、海外進出をする必要性が認識されているにもかかわらず、海外進出は十分といえるほ ど進んでいない。さらに近年では、日本円は円安傾向を見せており、国外へ輸出を行う企 業はともかく、国内での取引を行う企業は将来的に経営に苦戦することが想定される。こ うした状況を鑑みると、日本の企業の大半を占める中小企業は、経営のために将来を見据 え、積極的に海外進出をしていくべきだと考えられる。 このような状況において、政府も中小企業の支援を充実させていく方針であり、2010 年より中小企業発展のための多額の予算を計上している。その予算は単純に金銭的な支援 を目的とするだけでなく、海外進出の開始から進出後までの情報提供や宣伝、さらには複 数の企業間での連携強化を目的としても使われている。3このような取り組みは一定の効 果を挙げており、海外進出を行う中小企業の数は増加傾向にある。(図 2) 図 2 海外進出した中小企業の統計(中小企業庁調査室掲載のデータ4 より筆者作成) しかし、依然として海外進出は大企業が中心であり、日本にある企業の大半を占めてい るはずの中小企業はその勢いに追いつけてはいないというのが実情である。したがって、 日本の国内市場の縮小が予測される現在においては、中小企業は十分な進出を果たしてい るとはいい切れず、さらなる海外進出への取り組みが必要であると考えられる。 1−3 海外進出における課題 3経済産業委員会調査室 柿沼重志 東田慎平 「中小企業の海外展開の原状と今後の課題 TPP を通した「新輸出大国」の実現に向けて」 立法と調査 2016.3 NO375、27-37 頁. 4中小企業庁 前掲 11 頁. 0 1500 3000 4500 6000 7500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 (社)
- 7. 7 中小企業の海外進出が十分に進んでいない理由は、主に①資金調達、②国際業務におけ る情報不足の 2 点に課題を抱えていることが挙げられる。中小企業の海外進出を促進する ためには、これらの課題を解決することが不可欠であると考えられる。 1−3−1 資金調達の課題 一般的に企業が資金調達を行う方法としては、大きく分けると、企業が事業活動を通 じて調達する内部資金と、外部から調達する外部資金に分けられる。中小企業は、内部 資金だけでは資金が不十分なため、外部資金が必要となる。その外部資金は、直接金融、 間接金融、その他に分類できるのだが、資金調達側が出資者から資金を調達する直接金 融5 は、資金調達側によって資金調達できるかどうか難しくなることもあり、加えて専門 的な知識とコストや人材も要する。中小企業にはそのような余力がない場合が多く、直 接金融を利用できる大半が大企業に限られるのが現状である。このように、現在の日本 の中小企業は、直接金融を利用しにくいため、資金の調達側と供給側との間に金融機関 等の仲介業者を通して、間接的に資金を融通する仕組みである間接金融、特に銀行借り 入れに多く依存している6 。しかし、金融機関等から融資をうけるためには、金融機関等 の審査に通る必要があるため、中小企業が融資をうけるためには、障壁が多い。 1−3−2 情報不足による課題 中小企業が海外進出の課題には、情報不足も挙げられる。中小企業庁が行った、海外 展開に関心があるが、実行していない中小企業の「海外展開を行わない理由」に関する アンケートによると、「国際業務に関する知識・情報が足りない」という回答が 50%以 上で、最大の要因となっている。7実際、海外進出を行う上で必要な情報は多い。具体的 には、販路先の確保方法、現地での法規制、商習慣の把握、市場の動向・ニーズなど、 その土地ならでは情報が必要となってくる。したがって、中小企業の海外進出をさらに 促進させるためには、この情報不足の解消が必要になると考えられる。 5 井本亨「現代中小企業の資金調達の動向」『立命館経営学』2006 年,立命館大学経営学会,166 貢. 6 同上 168 貢. 7中小企業庁 前掲 185 頁. 中小企業庁委託「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」(2015 年 12 月、(株) 帝国データバンク) 複数回答のため、合計は必ずしも 100%にはならない。また、海外展開投資を重要であると 回答しており、かつ海外展開投資を行っていない企業を集計している。
- 8. 8 第 2 章 クラウド・ファンディングによる資金調達 まず、中小企業の海外進出のための資金調達面の課題について検討する。我々は、イン ターネットで出資者を募る仕組みであるクラウド・ファンディングに注目し、この仕組み を中小企業の資金調達に運用できないか考えた。 2−1 クラウド・ファンディングの仕組み クラウド・ファンディングとは、企業と出資者との間をインターネット経由で結びつけ、 不特定多数の出資者から少額ずつ資金を調達する仕組みである。(図 3) クラウド・ファンディングの運営会社が、クラウド・ファンディングで用いるポータル サイトをインターネット上で立ち上げ、資金を調達したい中小企業は、そのポータルサイ トに資金が必要となる事業の概略を掲載し、その事業の情報を閲覧し賛同した出資者が運 営会社を介して資金を提供するというものである。 図 3 クラウド・ファンディングの仕組み(筆者作成) 2−2 利用者への影響 2−2−1 中小企業にとってのメリット・デメリット クラウド・ファンディングにおける中小企業のメリットは、資金調達手段の多様化が 挙げられる。資本力の弱い企業は、事業計画の達成の可能性の不透明さなどを理由とし て、金融機関からの資金調達が困難である場合が多い。しかし、クラウド・ファンディ 出資者 中小企業 運営会社 ポータルサイト 運営会社 利益供与 資金提供
- 9. 9 ングを用いることで、その事業の趣旨に共感、賛同した不特定多数の人々から資金を調 達することが可能になる。 一方、デメリットとしては、資金を集めるために新規の事業や新しいアイデアを公開 することで、資本力のある他の企業にそれらを盗用されてしまうというリスクがあるこ とが挙げられる。また、一度クラウド・ファンディングに失敗してしまうと、失敗した 事実が公に知れてしまうため、損をした出資者のみならず、これから資金を提供しよう としている者からも「失敗した事業」というレッテルを貼られてしまう。そのため、事 業内容を大きく変更しなければ、再度資金を調達するということが困難になることもデ メリットとして挙げられる。8 2−2−2 出資者のメリット・デメリット 資金提供を行う側のメリットとしては、事業に共感、賛同したといった気持ちや世に 出ていない商品を手に入れたい、サービスを受けたい、といった心理的欲求が満たされ ることの他、投資金額が比較的少額であるので、たとえ損をしたとしても、それを少額 に抑えることができる安心感があることが挙げられる。 一方、デメリットとしては、大きく分けて、①投資のリスクの高さ、②資金提供を受 ける企業の信頼性、③運営会社の倒産リスクの 3 つに分類される。①は、クラウド・フ ァンディングが企業の事業規模が比較的小さい時期に用いられることが多いため、その 分リスクの高い投資となり、元本割れを起こす可能性が高いということである。また、 ②は資金が中小企業に渡った後に、不特定多数の出資者が中小企業を管理・監督するこ とは困難であるので、資金の流用などを防止しきれない可能性がある、という点から生 じる。9 また、クラウド・ファンディングは中小企業に資金が渡るまでの間、その資金は 運営会社によって分別して管理されてはいるものの、運営会社の固有財産と法的には一 体となるので、③運営会社の倒産のリスクが生じる。これら出資者のデメリットは、中 小企業側のデメリットと比較すると、当事者への影響やリスクが大きいと考えられる。 したがって、クラウド・ファンディングの利用を促進するためには、①〜③の課題の解 決が不可欠である。 8 福士信太郎「信託型クラウド・ファンディングの可能性について」『信託フォーラム vol.3』 2015 年 日本加除出版株式会社 67-68 頁. 9 福士 前掲 68 頁.
- 10. 10 図 4 クラウド・ファンディングによる影響 (筆者作成) 中小企業 出資者 メリット ・資金調達手段の多様化 ・ 事業を応援するといった 心理的欲求が満たされる ・ 損失が発生しても少額で ある デメリット ・事業アイデアの流出の恐れ ・1 度失敗した場合の再調達 の困難性 ①投資リスクの高さ ②資金提供を受ける企業の 信頼性(資金流用の恐れ) ③運営会社の倒産リスク 2−3 クラウド・ファンディングに関する法改正 平成 26 年 5 月 30日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 44 号)が公布され、投資型クラウド・ファンディングに関する法整備がなされた。改正 の主な目的は、投資型クラウド・ファンディングが詐欺的行為に悪用され、それによっ て投資型クラウド・ファンディング全体に対する信頼が喪失することがないように投資 者保護を行うという点と、運営主体の参入要件の緩和による利用促進である。 以下では、上述の出資者のデメリット①〜③との関連について検討する。 2−3−1 改正内容 今回の法改正では、非上場株式及びファンド持分の募集または私募による投資型クラ ウド・ファンディングの制度整備が行われた。 まず、改正法は現行法のもとでは位置づけられていなかった電子募集取扱業務を新た に位置づけた。電子募集取扱業務とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより第 2 条第 8 項第 9 号に
- 11. 11 掲げる行為を業として行うこととされている(法 29 条の 2 第 1 貢 6 号)。さらに、改正法 では金商業者が一定の有価証券を電子募集取扱業務として取り扱う場合には、投資家保 護の観点から必要な義務を課すことにし、その義務が課されるのは法 3 条各号に掲げる 有価証券または金融商品取引所に上場されていない有価証券を対象として電子募集取扱 業務を行う金融業者とした。 改正法では、電子募集取扱業務のうち一定の要件を満たすものについて、第一種少額 電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務として位置付けている。第一種少額 電子募集取扱業務とは①,電子募集取扱業務のうち、非上場の株券又は新株予約券証券の 募集の取扱い又は私募の取扱いであって、これらの有価証券の発行総額や投資者一人当 たり投資額が少額であるもの及び②,①の業務に関して顧客から金銭の預託をうけるこ と10(法 29 条の 4 の 2 第 10貢)をいう。同様に、第二種少額電子募集取扱業務とは、電 子募集取扱業務のうち有価証券(法 2 条 2 項の規定により有価証券とみなされる同項 5 号 又は 6 号に掲げる権利であって、法 3 条 3 号に掲げるもの又は非上場のものに限る。) の募集の取扱い又は私募の取扱いであって、これらの有価証券の発行総額や投資者一人 当たりの投資が少額であるもの11(法 29 条の 4 の 3 第 4 貢)をいう。両者の有価証券の発 行総額や投資者一人当たり投資額については、政令において、発行総額 1 億円未満かつ 投資者一人当たり投資額 50万円以下と規定することとしている。 また、その他にも投資型クラウド・ファンディングの制度整備の内容について以下の ようなものがある。 ①少額の非上場株式及びファンド持分の募集又は私募をインターネット上で行うものに ついて参入要件を緩和する(金商法 29 条の 4 の 2、同 29 条の 4 の 3 等)。 ②ウェブサイト業者は、契約締結前交付書面の記載事項のうち投資者の判断に重要な影 響を与える事項について、インターネットを利用する方法により、投資者が閲覧するこ とができる状態に置かなければならないこととする(金商法 29 条の 2、同 43 条の 5、同 205 条)。 なお、次の改正点も、投資型クラウド・ファンディングに重要な影響がある。 ③金商業者が業務管理体制を整備しなければならないことを明確化する(金商法 29 条の 4 第 1 貢 1 号へ、同 33 条の 5 第 1 貢 5 号、同 35 条の 3)。 ④金商業者の登録拒否事由に、国内拠点を有しないもの等を加える(金商法 29 条の 4 第 1 貢 4 号ロ・ハ等)。 10 多田治樹「金融商品取引法の改正と投資型クラウドファンディングの制度整備」『信託フ ォーラム vol.3』2015 年,55-56 貢 11 同上 56 貢.
- 12. 12 ⑤金融商品取引業協会に加入しない金商業者は、協会規則等に準ずる内容の社内規則を 整備しなければならないこととする(金商法 29 条の 4 第 1 貢 4 号ニ、同 33 条の 5 第 1 貢 4 号等)。 ⑥第 2 種金商業者等が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されることを知りな がら、その募集の取扱い等を行うことを禁止する(金商法 40条の 3 の 2 等)。 最後に、少額電子募集取扱業務に係る登録要件等の緩和について、少額電子募集取扱 業務者の最低資本金については、第一種少額電子募集取扱業者については 1000 万円、 第二種少額電子募集取扱業者については 500万円としている。また、第二種少額電子 募集取扱業者は、預託を受けることが認められていないので、金融機関などの既存の第 二種金商業者については、資本金が 5000 万円以上である法人に限り、分別管理するこ とを条件に預託を受けることが可能とされている。(金融商品取引法第二条に規定する定 義に関する内閣府令 16 条 1 項 14 号)が、電子申込型電子募集取扱業務を行う場合には、 投資者保護の観点から、分別管理の方法として信託を用いることを要件とする予定であ る12。 この法改正の影響から、クラウド・ファンディングのサービスが増加していくことが 想定される。 2−3−2 出資者のデメリットにおける課題 クラウド・ファンディングには、企業側が資金を調達しやすいという大きなメリット がある一方、資金を提供する出資者のリスクが大きいことは否定できない。出資者に関 する主な問題点は、上述の通り、①投資のリスクが高さ、②資金提供を受ける企業の信 頼性、③運営会社の倒産リスクの3つである。それでは、この法改正によって、①〜③に ついては、どのように変化したのか。 まず、①に関しては、クラウド・ファンディングが、事業が小規模であるために金融 機関からの資金調達が難しい企業が資金調達を可能にするための仕組みであるため、① は、法整備されたことでは解消されないと考えられる。 次に、②は、金融商品取引法等の改正により、運営会社の出資者に対する情報提供義 務が法規制化され罰則も整備されたため、資金需要者の信頼性はある程度高まると想定 される。しかし、事業主である企業に対し、資金提供後も出資者が継続的に関与してい くことは、困難であると考えられるので、さらなる改善が求められる。 12多田 前掲 60 貢.
- 13. 13 最後に、③については、運営会社の倒産に関する規定は、置かれておらず、分別管理 は義務付けられていないため、依然として問題となる。13 以上のように、法改正後においても、上記①〜③については、依然として課題が残ると 考えられる。 図 5 出資者のデメリットと法改正との関連(筆者作成) ①投資リスクの高さ 法整備されたことでは解消されない ②資金提供を受ける企業の信頼性 情報提供義務や罰則により、ある程度高まるが、改善 の必要あり ③運営会社の倒産リスク 倒産に関する規定がないため、解消されない 第3章 制度提案 3−1 概要 我々は、中小企業の海外進出のための資金調達手段としてのクラウド・ファンディング の課題を解決するとともに、中小企業の情報不足を解決するため、金融機関による信託を 用いたクラウド・ファンディングと専門機関からの情報提供を掛け合わせた制度を提案す る。(図 6)それは、海外進出に必要な資金調達を、金融機関による信託を用いたクラウド・ ファンディングで行い、情報不足の課題を、金融機関と専門機関との連携による情報提供 によって解決を図るというものである。具体的には、金融機関が運営するクラウド・ファ ンディングのポータルサイトを利用することで、資金調達に成功した企業に対して、海外 進出をする際の事業展開について、金融機関が橋渡しとなって専門機関からの情報提供を 施すという制度枠組みである。情報提供の内容は、経済情勢や投資環境、市場情報等、中 小企業から受ける様々な相談に対して、専門機関が持つノウハウを提供するというもので ある。なお、金融機関も単に中小企業と専門機関との仲介を行うだけでなく、独自に持つ ノウハウを活用し、情報提供を行う。 13もっとも、第二種少額電子募集取扱業者は、預託が認められていないが、既存の金商業者 のうち、資本金 5000 万円以上である法人は分別管理を行うことを条件に、預託を受けるこ とが可能となる。(多田 前掲 60 頁.)
- 14. 14 図 6 制度枠組み(筆者作成) 3−1−1 金融機関による信託を用いたクラウド・ファンディング 本制度における金融機関による信託を用いたクラウド・ファンディングとは、金融機関 がクラウド・ファンディングのポータルサイトの運営者となり、出資者と信託契約を結ぶ という仕組みである。(図 6)出資者は金融機関のポータルサイトを通じて、金融機関を受託 者とする信託受益権の購入申し込みをすることになる。その際、出資者を委託者兼受益者 とした信託契約を締結することになる。この場合、出資者は通常のクラウド・ファンディ ングとは異なり、金融機関の定める口座に入金することになる。その後、受託者が信託を 設定することで、資金は金融機関にプールされ、受託者の固有財産とは分別して管理され る。そして募集金額が目標値に達すると、企業への貸し出しを行う。事業が成功し、貸出 金が返済されると、受益者である出資者に収益金が振り込まれる。14 3−1−2 金融機関と専門機関の連携 中小企業の海外進出の情報不足の課題について、金融機関は、海外に広がる拠点ネット ワークや多彩な金融サービスと長年により培ったビジネスのノウハウを提供している。主 に、金融ソリューションや為替等、海外展開に係る事業投資に必要な「金融ノウハウ」を 提供している。しかしながら、海外進出により市場拡大・事業拡大の成功率を上げるため には、中小企業の業務内容に通じている金融機関のノウハウを提供し支援するだけではな 14 福士 前掲 68 頁参照. 出資者 中小企業 運営会社ポータルサイト 貸 出 金 返 資金提供 貸出 収益金 信託契約 金融機関 専門機 関 情報提供 支援申込
- 15. 15 く、事業の策定から海外販売販路、進出後の対応まで一貫して支援する必要がある。そこ で、我々は、専門機関による情報提供により、海外進出の情報不足の課題を解消できるの ではないかと考えた。そのためには、金融機関と海外進出に関する各支援機関との連携が 不可欠である。 具体例として、名古屋におけるジェトロ名古屋貿易情報センターと金融機関の連携を参 考とする。日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センターと株式会社愛知銀行、株 式会社名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫の各地域金融機関が、国内の中堅・中小 企業等の海外展開支援を充実させるために 2015 年 4 月 30 日より従来以上に連携を強化さ せた。海外展開に係る事業投資の「金融ノウハウ」に加え、愛知県内に 360 支店、海外拠 点 4 点のネットワークを持つ地域金融機関と、「海外ビジネスに必要なノウハウ」と 57 か 国に 76 の海外事務所ネットワークを含む国内外 120 を超える拠点を有するジェトロが連携 することによって、地域企業の海外ビジネスのトータルで支援する体制が強化されている。 15 その他にも、様々な公的機関等の支援制度を活用し企業の海外進出を支援する事例16 や東 京都の金融機関と専門機関が連携した海外展開支援の例17 がある。具体的には、中小機構(独 立行政法人中小企業基盤整備機構)、JBIC(株式会社国際協力銀行)、NEXI(独立行政法人日 本貿易保険)と金融機関が連携し、中小企業に対し豊富な実務知識・経験・ノウハウを持つ 専門家からのアドバイスやセミナー、海外市場調査や現地視察による情報を提供している。 3−2 課題の解決 我々は、本制度を活用することによって、中小企業の海外進出の課題となっている資金 調達と情報不足は解決すると考える。 3−2−1 資金調達に対して 我々は、中小企業の資金調達をクラウド・ファンディングによって行うことを提案して きた。しかし、クラウド・ファンディングには出資者に関して、①投資のリスクの高さ、 ②資金提供を受ける企業の信頼性、③運営会社の倒産リスクなどの問題点が存在し、これ らは法整備が行われた後も依然として改善が必要な状況である。そこで、金融機関による 15 日本貿易振興機構(ジェトロ).ジェトロ名古屋貿易情報センターと地域金融の連携強化 https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2015/4e37be20c273707e.html 16 金融庁.金融機関による企業の海外進出支援の促進に向けて http://www.fsa.go.jp/common/about/01.pdf 17 東京都産業労働局.金融機関・専門機関と連携した海外展開支援 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/DATA/20q3n602.pdf
- 16. 16 信託を用いたクラウド・ファンディングによって①〜③の課題を解決することを提案した。 まず、②については、金融機関がポータルサイトの掲載について一定の要件を設定し、 掲載される企業を精査することで解決できると考えられる。金融機関が精査した企業であ っても、完全に信頼のできる企業であると考えることはできない。しかし一方で、金融機 関は事業融資のプロフェッショナルであり、他の運営会社と比較すると多くの情報や経験、 ノウハウを有している。したがって、従来のポータルサイトに掲載されている企業よりも、 金融機関が運営するポータルサイトに掲載されている企業の方がより信頼性が高いと考え られる。これにより、現状よりも改善が見込まれる。 また、信託契約により、受益者である出資者に対して様々な義務を負う受託者たる金融 機関が、中小企業に対して継続的に関与することが期待できる。18この点から考えても、② については、改善が見込まれるだろう。 次に、③であるが、信託を用いたクラウド・ファンディングでは、中小企業へ資金が渡 るまでの間は、信託によって金融機関が資金を分別管理する19 ので、倒産隔離機能が作用す る。したがって、運営会社および受託者の倒産のリスクについては、改善される。 以上より、金融機関による信託を用いたクラウド・ファンディングを活用することで、 従来のクラウド・ファンディングのデメリットである②、③を解消できるとともに、中小 企業の海外進出おける資金調達の課題を解消できると考える。しかし、①は、クラウド・ ファンディングの性質上、金融機関による信託を用いたクラウド・ファンディングのみで は、解決が困難であると考えられる。 3−2−2 情報不足に対して 金融機関とジェトロなどの専門機関との連携は、上述のように、実際に運用され成功し た事例が複数存在する。このことから、この制度を利用することによって、中小企業の海 外進出の課題のうち、海外事業に関する情報不足は解決されると考えられる。また、情報 不足の課題が解決することにより、中小企業の海外事業の成功率は上昇することが予想さ れる。事業の成功率が上昇すると、その事業をターゲットとする投資の成功率も上昇する と考えられる。したがって、海外事業を行う中小企業に対して、情報提供とクラウド・フ ァンディングを並行して行うことで、クラウド・ファンディングの課題である①について も改善が見込まれる。 18 福士 前掲 70 頁. 19 福士 同上 68 頁.
- 17. 17 図 7 クラウド・ファンディング出資者のデメリットの改善(筆者作成) ①投資リスクの高さ 情報提供による事業の成功率上昇によって改善が見 込まれる ②資金提供を受ける企業の信頼性 金融機関による企業の査定および資金提供後の継続 的な関与により、改善が見込まれる ③運営会社の倒産リスク 信託の倒産隔離機能により解決 3−3 新たなメリット 本制度を用いることにより、中小企業、出資者、金融機関にそれぞれ新たなメリットが 生まれると考えられる。 3−3−1 中小企業 中小企業のメリットは、まず、金融機関が運営するポータルサイトを活用して資金調達 をすることで、従来の運営サイトと比較して、より確実に資金提供を受けることが可能と なる。次に、金融機関が運営するポータルサイトに掲載を依頼することで、より多くの出 資者の目に留まることが可能となる。また、現在は専門の運営サイトもしくは個人による クラウド・ファンディングの 2 つの選択肢のみであったが、金融機関が参入することで、 中小企業はクラウド・ファンディングによる資金調達方法の選択肢が 3 つに増えることに なる。 3−3−2 出資者 出資者のメリットは、従来のクラウド・ファンディングの問題点が解決されることにあ る。それに加えて、中小企業と同じように、金融機関がポータルサイト運営に参入するこ とによって、信頼性の高い投資先の選択肢が増えるというメリットも考えられる。 3−3−3 金融機関 金融機関のメリットは、まず、インターネットを媒体とするポータルサイトを運営する ことにより、多くの人の目に留まることで銀行自体の宣伝効果も期待でき、更なる顧客獲 得のチャンスが生まれることである。次に、ポータルサイトを運営することで新たな利益 を獲得できる可能性がある。運営費や人材費が新たに必要となるが、ポータルサイトを運
- 18. 18 営することで掲載企業から掲載費、資本提供した際に発生する手数料などの収入が見込ま れる。したがって、資本募集企業と出資者の顧客を増やすことで運営する金融機関自体に 利益が生まれると考えられる。また、今後増加する可能性のある需要の獲得もメリットと して挙げられる。具体的には、上述の通り、海外進出する中小企業は今後も増加すると予 想されるが、外部資金の調達はそれらの企業にとって不可欠である。この場合、ポータル サイトを運営することで、より多くの企業の資金調達に関わる機会を得ることが可能であ ると考えられる。 図 9 本制度により新たに生まれるメリット(筆者作成) 中小企業 ・クラウド・ファンディングによる資金調達の確実性の向上 ・注目されやすくなる ・選択肢の追加 出資者 ・従来のクラウド・ファンディングのデメリットの解消 ・選択肢の追加 金融機関 ・宣伝効果による顧客獲得 ・新たな収益源 ・需要の獲得 3−4 今後の課題・展望 以上が我々の制度提案であるが、この方法を実用化するにあったては、解決しなければ ならない課題が存在する。それは、ポータルサイトに掲載する企業のデータの範囲どのよ うに設定するか、というものである。クラウド・ファンディングを用いるためには、出資 者のリスクを解消することが、重要である。出資者の取引の安全を図るには、金融機関が ポータルサイトを運営し、信託を用いることに加え、現在のポータルサイトよりも多くの 情報を金融機関が把握し、出資者に公開する必要がある。しかし、中小企業にとっては、 多くの情報を公開することで、同業他社などに今後の事業計画が知られてしまうという懸 念が生じる。そこで、出資者の保護と中小企業のリスクとの調整をどのように図るか、が 問題となる。 金融機関がクラウド・ファンディングのリスクを抑えることができれば、利用者の促進 だけではなく、今後拡大が予測されるクラウド・ファンディング市場での存在感は大きく なるだろう。
- 20. 20 参考文献 【書籍】 ・ 中小企業庁 『中小企業白書概要 2016 年版』、2016 年 ・ 経済産業委員会調査室 柿沼重志 東田慎平 「中小企業の海外展開の原状と今後の課題 TPP を通した「新輸出大国」の実現に向け て」立法と調査、2016 年 ・ 井本亨「現代中小企業の資金調達の動向」『立命館経営学』立命館大学経営学会、2006 年 ・多田治樹「金融商品取引法の改正と投資型クラウドファンディングの制度整備」 『信託フォーラム vol.3』日本加除出版株式会社、2015 年 ・福士信太郎「信託型クラウド・ファンディングの可能性について」 『信託フォーラム vol.3』日本加除出版株式会社、2015 年 ・河上正二「投資型クラウドファンディングと信託」 『信託フォーラム vol.3』日本加除出版株式会社、2015 年 ・坂勇一郎「リスクマネー供給等のための規制緩和策について(平成 26 年金融商品取引法改 正)―クラウド・ファンディングを中心に―」『消費者法ニュース No.100』2014 年 【Web サイト】 ・ 総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120.html (最終確認日 2016 年 11 月 23 日) ・ 商工中金調査部 上田 「中小企業の海外進出に対する意識調査」、2,015 年4月 2 日 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h22/h22/html/k221400.html (最終確認日 2016 年 11 月 25 日) ・ ミハエル A.ヴィット INSEAD 教授「なぜ日本は海外進出が下手なのか。」東洋経済 ONLINE 2014 年 7 月 7 日 http://toyokeizai.net/articles/amp/41560 (最終確認日 2016 年 11 月 25 日) ・ 日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページ https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2015/4e37be20c273707e.html (最終確認日 2016 年 11 月 23 日) ・金融庁.金融機関による企業の海外進出支援の促進に向けて http://www.fsa.go.jp/common/about/01.pdf (最終確認日 2016 年 11 月 25 日) ・東京都産業労働局.金融機関・専門機関と連携した海外展開支援 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/03/DATA/20q3n602.pdf (最終確認日 2016 年 11 月 25 日)