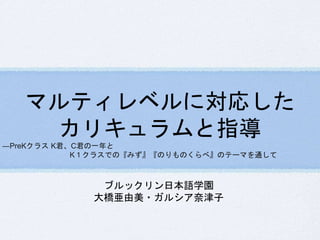More Related Content
Similar to NECTJ Annual Conference 2014: Brooklyn Gakuen
Similar to NECTJ Annual Conference 2014: Brooklyn Gakuen (10)
NECTJ Annual Conference 2014: Brooklyn Gakuen
- 6. 水の三態
*固体
水を冷やす実験
氷結点
色のついた氷実験
遊び:氷鬼
*気体
水を温める実験
水蒸気
沸点
*液体
溶解力実験
水の循環
水のたびジャンプ
水の性質
*水の変身
(雪、水玉レンズ、
表面張力)
雪の結晶作り
雪と氷の観察
水玉レンズ実験
表面張力実験
墨流し(表面張力)
*水の音
雨の音実験
クラシック音楽:
ドビュッシー「雨の
庭」ショパン「雨だ
れ」
実験
手
耳
体感体で表現
唱える
目
体
みず
- 13. 多くの読み教材に触れる
/レベル別認識(文字、語彙、文認識)
「みず」に関する読教材
*水の変身
「ゆきのかたち」ひさかたチャイルド
「ゆきのひ」偕成社
「ゆきがいっぱいふりました」福音館
「おおさむこさむ」福音館
*液体
「みずたまレンズ」福音館
*固体
「こおり」福音館
*みずの音
「あまがさ」福音館
*水のたび
「みずのたび」福音館
「ピチャン、ボチャン、ザブーン!水ってふしぎ」評論社
「しずくのぼうけん」福音館
- 15. 読む―理解する―活動する
陸のりものくらべ
じどうしゃくらべ
光村図書1下
乗用車とバス、トラック、ク
レーン車、はしご車
バス遊び
クレーン車作り
自動車くらべジャンプ
♪はたらく車
教材:
くるまはいくつ福音館
ちいさいしょうぼうじどうしゃ
福音館
のろまなローラー福音館
しょうぼうじどうしゃじぶた
福音館
いろいろなふね
東京書籍1下
船作り
船を浮かばせる実験
♪ふねがゆく
教材:
チムとゆうかんなせんちょうさ
ん福音館
せいそうせんのくるりんまる
福音館
空
ぼくひこうきに
のったんだ「あか
ね書房」
紙飛行機
ライト兄弟
♪そらとぶなかま
海
- 24. K君の場合
第二段階
②・読み聞かせ継続
・遊びを通して手指の力がつく
柔らかいクレヨンで描く事が容易に
ハサミを使ってお料理ごっこ
第三段階
サンドイッチ作り
③・理解を深める絵本の読み聞かせ読後に質問(質問事項のメモ書
きを添付)
・文字認識に繋げる絵本の中の平仮名の文字を認識させる
自分の名前のひらがなを見つけさせる→自分でわかると言う自信
- 31. K君、C君に対する実践例
・名前を書く
・掲示物
・マイ絵本
→ k:自分の名前を読める、書ける
c:自分の名前を読める、書ける
友達の名前を読める
→ k:写真や絵を見て日本語で話す
自分の名前も平仮名、「お」を読む
c:自ら文字を読み、内容理解
友達を助けて読む
→ k:文章を覚えて読んだ気持ちになる
「読めた」「また読みたい」
c:自分で絵本を読む
「(文字が)読める」「もっと読みたい」
Editor's Notes
- 継承語教育で、問題となるのは子ども達の日本語習熟度の差をクラスでどのように教えるかと言う事だと思います。ブルックリン日本語学園でも開園以来このマルティレベルをどのように対応するかが大きな課題になっています。今日は、ブルックリンのKー1のクラスでのマルティレベルに対応した「みず」と「いろいろなのりもの」のテーマでの実践と、PreKクラスでの二人の児童のケースをご紹介したいと思います。
- ブルックリン日本語学園ではできるだけ多くの継承語学習児童に日本語を学習する機会を与えるべく、家庭環境、日本語の発達レベルを超えて児童を受け入れてきました。学園のミッションとして、日本語学習が楽しくなるカリキュラムをとおして、子ども達が将来自律して学習を継続できる様な教育を提供すべく取り組んでいます。また、学校のみならず日本語母語話者である保護者、日本語以外の母語話者である保護者も子ども達の日本語学習に巻き込んでいく家庭学習、行事等を取り入れたり、必要であれば保護者へのアドバイスや働きかけを行ってきました。
- まず「水」のテーマを通したマルティレベルの実践についてです。「水」にうついては、性質、気体、液体、固体の三態、水の循環に着いて学習しました。様々な実験を通して、興味を持たせ、(日本語のレベルにかかわらず)知識を共有でき、それを言葉に繋げていきました
写真は、子ども達一人一人が水の分子になって実験した事を体で表して理解しました。語彙がくり返させる事で定着していきます。
- 子ども達に身近な、導入で、興味を惹き付ける
- 五感を通した実験や活動は子ども達のテーマに釘付けにし、発見は生きた言葉に繋がります。復習はゲームを通してくり返して唱える事で体、耳、口を通して定着させます。実験の発展として、家庭でも課題に着いて一緒に実験をし、それについて話し合ったり、書いたりする活動を起こしていきます。実験は日本語母語話者でない保護者とも一緒に共有する事ができます
実験するためのラボコートを着たり、
- 一人一人の既習の知識を発表し、テーマへの意識をたかめる。知っている事を発表し、教師が聞き取りをしたものを書き取る。 マルティレベルに応じ、なぞる、聞いて書き取る、自分で書く
実験室に入室するための注意(ルール)守れるとIDがもらえる
- 又、実験に着いては、予想、実験、結果をまとめるという 現地校でもおこなう理科の実験の過程を行う事で、知識が転移する事をねらいとする
- ここは、これだけの本を読んだと言う事で次に進む
- 同じような教材をくり返す事によって、説明文の文体、構造に慣れる そのために、2種類の乗り物に着いて書かれた教材を別の1年生の教科書からえらぶ
範読(先生・児童ー読む事のできる児童に範読する機会を)やまびこ読み(読めない子どもも一緒になって読める)
- 『子どもが自ら日本語を楽しむには』
Pre-Kクラスでの二人の児童のケースを通してご紹介致します。
- まずは、殆ど日本語の発話のなかったk君についてお話しさせて頂きます。
k君の家庭は英語話者の父親、日本語話者の母親、k君、そして生まれたばかりの赤ちゃんの4人家族。父親は自宅にて仕事、母親は平日はフルタイムで仕事に出ています。k君は小さい頃からデイケアに通っており、日本語を話す時間は、母親が仕事から帰宅後〜k君が就寝するまで。9月からは日本語学園に通い始め、土曜日も日本語の時間となりました。しかし、母親とは日本語のみではなく、母親も英単語を使用して会話をしていました。
- アセスメントでは、
英語のみ。
いくつかの語彙は理解。
文字の理解なし。絵は筆圧が弱くなぐり書き。
活動に興味を持ち、わからなくても積極的に参加。
という結果でした。
- 『授業への参加の様子/指導上の問題点』
活動へ参加意欲はあるが、日本語理解困難。特に絵本の読み聞かせ、工作やワークシートなどの説明等、『聞く』時間になると、立ち歩きや、自分の世界に入ってしまい、声が耳に入らず、参加できなくなってしまう。
宿題発表、積極的に思った事を言う。しかし、発表も発言も英語。
筆圧、握る力が弱い。
ということがあげられます。
- そういった状況の中、10月に保護者面談がありました。私もk君の興味をこちらに向けたい為、k君が現在好きなものは何かを保護者に尋ねましたが、分からない様子でした。普段は、自宅で仕事をしている父親が、一緒に工作をしたり、絵を描かせたりしているそうですが、絵を描きたがらないとのことでした。また、ハサミについて尋ねると、小さい頃に危なっかしくて片付けて以来、一度も使っていないとのことでした。
そういった話から、授業で興味を持った活動を報告する事、k君に何を授業でやったかを尋ねるなど、日本語での交流と、家庭での取り組みを段階的に提案していきました。
まず、
毎晩、日本語の本を読み聞かせすることで、日本語の時間をなるべく増やす
粘土遊びやハンバーグ作りなど、料理を通して手や指の力をつける
クレヨンではなく、色が出やすいカラーペンにしてみる
ように話ししました。
授業でも手や指の力をつける活動を入れていきました。少しずつ助けなしでできる事が増え、ハサミも上手になっていきました。
また、k君の描く作業を見ていると、アメリカのクレヨンでは色が良く出ず、その事で「もうおしまい」とやめてしまうことがわかり、日本のクレヨンを貸しました。すると、力を入れなくても色が出るので「おしまい」と言わずに最後まで描く事ができました。
- そこで次に、
・クレヨンを日本のクレヨンにすること、ハサミを使ってのお料理ごっこ等を提案しました。
残念ながら、読み聞かせによる日本語の発話には至らず、3学期からは、
こちらが指定した絵本を1週間読んでもらうようにしました。
読んだあとに、保護者が質問するように質問事項を書いて渡しました。
その本をクラスでも読み、同じように質問をして、k君が答えた所をたくさん褒めるようにしました。
それと同時に、文字認識も始めました。絵本の中に名前の文字があるときは「これは何と読むかわかる?そうだね、k君のkだね。」「k君のkはどれかな?」というように確認してみるようお伝えしました。
授業でも同様に文字を読んでもらい、読めたら褒める事を続けました。最終的には名前の平仮名は読めるようになりました。
- 続いて『日本語の発達の進んだc君の場合』です。
c君の家庭は、英語話者の父親、日本語話者の母親、c君、2歳の弟の4人家族です。母親は仕事をしていますが、日本人のシッターを雇っていて、日本語の時間はkくんよりも長いです。また、母親、弟とは日本語で話すことを続けていました。
- アセスメントでは、
質問に1〜2語で答えられる。
読み聞かせを聞ける。
名前、いくつかの平仮名が読める。
筆圧が強い。
という結果でした。
- 『授業への参加の様子/指導上の問題点』
日本語にには問題はない、行動面に問題。
宿題発表での態度、聞く態勢。
があげられます。
- c君は落ち着きはありませんが耳では聞いています。しかし、動く事で他の子も落ちつかなくなるわけです。
そこで、座っている時間を最低限にし、動作を付けたり、読ませたりと「参加型」にしました。座っている人から順に当てるようにすると、積極的にやりたいので、座って聞けるようになりました。また、友達に教える為に聞くようになりました。
発表に関しては、上手な子を褒めました。そして、c君の発表の真似をして見せ、客観的に見て、どちらが良いかを自分で考えさせました。それをきっかけに発表の仕方が変わりました。個人目標にもして、その日発表を頑張ったらシールを貼れるようにしました。最終的にはクラスで一番、上級生よりも発表が上手ではないか、という程に成長しました。
- 入園当初から日本語に差がある二人でしたが、活動に興味があり積極的に発言するという点、じっと座っていられないという点など、共通点も多い二人です。
色々な性格、発達に加え、日本語に関してマルティレベルであるPreKクラスで、同じテーマ、同じ活動をそれぞれの児童に学びのあるものにする為に、どのように進めていったかをいくつかご紹介させて頂きます。
1学期
二人に共通する「じっとしていられない」ことから活動を『参加型』にして、c君はたくさん日本語を話して活躍してもらい、k君は、友達と一緒にやりたい、楽しい、日本語で話したい、と思ってもらえるようにしていきました。
また、k君を初め、筆圧が弱い子がいましたので、手や指の力を養う活動を入れていきました。
粘土遊び、絵筆を使った絵の具遊び、手作りトングで小さい物を摘む、毛筆で書く、平仮名の学習ではクレヨンはもちろん、カラーペンやお菓子作りに使用するアイシングペン、チョーク、鉛筆など色々なものを使用しました。
k君の場合は、書くこと自体があまり好きではない所からスタートしましたが、日本のクレヨンにしたのをきっかけに書く事が好きになりました。それから少しずつコントロールできるようになり、3学期末の鉛筆を使った平仮名学習でも、しっかりとした線を書く事ができました。色々な物で力を養ってきたことで、ハサミも一人で上手になりました。
c君は初めから筆記具を上手に使う事ができていましたが、彼も様々な活動から、文字を書く時の線がきれいになったり、同じくらいの大きさで文章を書けるようになったり、また、細かい絵を描けるようになりました。
平仮名の歌として「あひるのあくび」を年間を通して歌っていました。こちらが使っていたものの一部ですが、k君には絵と語彙を一致させて、語彙を覚えるというねらいがあります。c君は語彙も意味もわかるので、文字を読む事と、同じ音の言葉に入れ替えて遊ぶことをねらいとしました。例えば、「あひるのあくびはあいうえお」の回では、k君は「あひる」「あくび」を知り、「あいうえお」の固まりを振りと共に覚えます。c君は、「あひる」「あくび」「あいうえお」の初めが全部「あ」という音である事に気付き、「あゆみせんせい」の「あしだ」「あいうえお」などに変えて遊びます。
- 2学期
机での活動時のペアを決め、自分が終わったらペアの友達と見せ合うことを始めました。先生の指示に対しては、お互いに合っているかの確認、絵を書く等の表現ではお互いに見せ合う事で刺激になります。
k君は教えてもらう事ばかりでしたが、3学期後半には、教える事ができるようになりました。c君は自分が教える為には先生の話をきちんと聞かないといけないので、話を聞く態度が改善されていきました。
発表では、k君は初めに「kです。」と名前を言う事と、単語で良いので日本語で言い、それに「です。」「ます。」を付けてもう一度言う事をしていきました。c君は、「ぼくの名前はcです。」その後、内容を話し、「終わりです。」と発表を終わることをしていきました。
また、「みてみてきいて」と題してshow&tellを始めました。好きな事を話し、それについて友達が質問してくれるので、どの子も発表が上手になった活動です。k君は、発表はもちろん、友達の話を聞く事を頑張りました。c君も友達の話を聞く事なのですが、それプラス質問がないか尋ねるようにしました。
全員に同じ目標を立てるのではなく、一ひとりに目標を立てて、どのレベルの子も達成感を味わい、次の目標を頑張れるようにしました。
- 3学期
名前を書くという目標の総仕上げとして、今までなぞっていた名前を、自分で書けるように、登園したらサインをするようにしました。k君は、サインをすること自体が楽しい様子で、自分の名前を読める、書けるという気持ちになり、名前を書く事に自信がつきました。c君は名前が書けるので、簡単な作業でしたが、日に日に4文字の名前のバランスが良くなっていきました。
テーマに関する掲示物も、1、2学期はk君のように語彙が少ない児童にもわかるように、写真や絵が多かったのですが、3学期はc君のように文字がすらすら読める児童もいるので、文字も多く入れていきました。
しかしk君も自分の名前の文字は読めるので、「この中に『い』があります。どれか教えてください。」、『い』を指して「これは何と読みますか?」と一文字を読ませました。c君は、少し読める児童が読んだ後、「全部をもう一度読んでください。」というように長い言葉や文章を読んで友達を助けることをしました。
マイ絵本も掲示物と同様です。
c君は読む機会が増えた事で、1学期にあまり自信がなかった濁音、半濁音、拗音も読めるようになっていきました。
私はそれぞれの児童が自分のペースで伸びていって欲しくて、こども達を観察し、どういった指導方法が良いかを考えていました。こども達は一生懸命応えてくれました。一年でそれぞれが伸びたと思います。まだまだ問題点はありますが、自ら日本語を楽しむ気持ちは芽生えたのではないかと思っています。