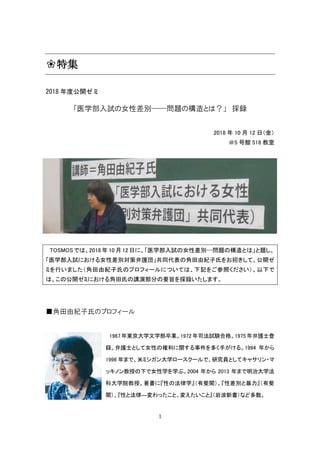
角田由紀子氏(「医学部入試における女性差別対策弁護団」共同代表)講演採録(2018年度公開ゼミ)
- 1. 1 ❀特集 2018 年度公開ゼミ 「医学部入試の女性差別―問題の構造とは?」 採録 2018 年 10 月 12 日(金) @5 号館 518 教室 TOSMOS では、2018 年 10 月 12 日に、「医学部入試の女性差別―問題の構造とは」と題し、 「医学部入試における女性差別対策弁護団」共同代表の角田由紀子氏をお招きして、公開ゼ ミを行いました(角田由紀子氏のプロフィールについては、下記をご参照ください)。以下で は、この公開ゼミにおける角田氏の講演部分の要旨を採録いたします。 ■角田由紀子氏のプロフィール 1967年東京大学文学部卒業。1972年司法試験合格。1975年弁護士登 録。弁護士として女性の権利に関する事件を多く手がける。1994 年から 1996 年まで、米ミシガン大学ロースクールで、研究員としてキャサリン・マ ッキノン教授の下で女性学を学ぶ。2004 年から 2013 年まで明治大学法 科大学院教授。著書に『性の法律学』(有斐閣)、『性差別と暴力』(有斐 閣)、『性と法律―変わったこと、変えたいこと』(岩波新書)など多数。
- 2. 2 ■角田由紀子氏の講演 皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました角田です。 私は、50 年くらい前にこの大学の学生でした。私が入学したのは 1962 年です。歌手 の加藤登紀子さんと同じ学年ですので、おそらく、皆さんのご両親よりも上の世代だと思 います。私は 1975 年に弁護士登録をしてから、これまで基本的に弁護士としての仕事を してきました。 皆さんは、私が「なぜ文学部を出て弁護士になったのか?」と思うかもしれません。私 は、文学部で日本文学を専攻していました。私は一応、高校の国語の教員免許を取ったの で、国語の先生になれるだろうと思い、東京都教育委員会に「どういう手続きを取ったら 国語の先生になれるのですか?」と聞きに行きました。そうしたら、「女性の国語の先生は 余っているから、もう要らない」「理科や数学の先生なら、女性でも採らないことはない」 と言われたんです。そこで仕方なく、とりあえず文科系でも何か資格を取れそうな司法試 験を受けることにしたのです。 その当時は、司法試験の予備校などというものはなかったので、文一(法学部)前期課 程生向けの法律の授業を勝手に聞きに行きました。そういう意味では、私は法学部的な法 律の勉強はしていないんですね。でもそのことは、後から考えたら、とてもよかったと思 っています。つまり、法学部の勉強だけではなく別のことを少しやって、別の見方を持て たいうのはよかったな、と思っているんです。 ●男女不平等が著しい日本の現状 さて、本日のテーマである「医学部入試の女性差別」についてです が、「東京医大事件」について最初に聞いたとき、私がとても驚いた のは、あまりにも明々白々な女性差別だという点でした。今の日本社 会では、多くの「間接差別」はありますが、女子学生の小論文の点数 を一律に減点するというのは、あまりに分かりやすい「直接差別」で す。このような差別が今も存在することに、私はたいへんショックを 受けました。私は弁護士になって、女性の権利や差別に関する多くの 問題に取り組んできましたが、こんなことがまかり通っていることに、 「自分が今までやってきたことは何だったのだろうか」との思いを抱きました。 それで、今回の問題は、日本社会における女性差別の現状を正直に表している出来事だ、 というふうに思ったんです。「世界経済フォーラム」が毎年秋に発表している「ジェンダー ギャップ指数」報告書というものがあります。昨年(2017 年)の報告書によると、日本 は 144 か国中 114 位です。項目別の順位では、経済参画が 114 位、政治参画は 123 位、
- 3. 3 教育は 76 位、健康は 1 位です。健康が 1 位なのは長寿が理由なのですが、それ以外の項 目の順位の低さが問題なんですよね。こういう状況が社会の基礎にあって、それを象徴的 に表すものとして、東京医大の入試の不正事件が出てきたのだ、と私は思うんです。 教育の順位の低さについて言えば、日本においては、女子学生は男子学生と平等に高等 教育を受ける機会が与えられていないのが現状です。たとえば、東大の女子学生の比率は 2 割ですが、1960 年代は、東大法学部では、女子学生は 1 学年に 4 人しかいませんでした。 大学進学率では、男女間で 3 倍もの開きがあります。女子学生も高等教育を受けるように なったといっても、全体でみると非常に少ないということですね。 さらに、大学で進学する学部にも男女差があります。東大もおそらく、工学部や法学部、 経済学部などは女子学生が少ないのに対して、教養学部や文学部系の学部は、相対的に女 子学生が多い。将来的により有利な職業につける分野は、女性が少ないという構造です。 そして、この社会の様々な意思決定をする機関においては、男性が圧倒的多数を占めて います。このことは、たとえば政治家の女性比率に表れていますし、弁護士もそうです。 日本に女性の弁護士はどれくらいいるかというと、18.6%しかいないのです。私が弁護士 になった 1975 年には、女性の弁護士の比率はわすか 3%でしたが、今も女性弁護士は 18.6%で、圧倒的多数が男性のままです。そして、このような日本社会の男女不平等の現 実が、東京医大事件にも反映されているのだと私は思います。 ●明治憲法の時代の女性 日本の近代的国家としての出発点である、明治憲法の時代には、女性の人権というのは ほとんどありませんでした。当時は、男性も含めて、基本的人権という考え方がなかった 時代ですが、とくに女性は、ほとんど権利のない時代でした。たとえば参政権も、1945 年までは女性にはありませんでした。 また、当時の民法においては、法律婚の妻は法的に無能力ということで、夫の許可なし に、意味のある行為はできなかったわけです。それから、子どもは「家」に所属している 存在なので、母による親権もありませんでした。だから、離婚するときは、子どもは家に 置いて、母親だけが出て行きました。妻は離婚の際の財産分与請求権もなかった。なぜな ら、財産は夫の家のものだからです。離婚すると、女性は何も持たずに出ていくというこ とです。また、遺産相続など、様々なところで女性は無権利者でした。 さらに、政治活動についても、政党に加入して活動する自由は、戦後に「治安維持法」 が廃止されるまで、女性にはなかったんです。今の日本社会の中で、女性の政治参加が非 常に遅れているというのは、こうした歴史と関係があるのだと私は思うんですね。 それから、この社会全体が、家父長制で運営されている、男性優位の社会でした。そこ では、女性は家の中に閉じ込められて、家事労働をするだけの存在でした。教育について
- 4. 4 も、今とは違って、戦前は男女別学が基本であり、高等教育を女性が男性と同じレベルで 受けることはできなかったわけです。 当時の社会においては、女性の進出を受け入れないところが圧倒的でした。たとえば、 司法試験の受験資格は男子に限られていました。これに対して、市川房枝たちの「婦人参 政権同盟」が、司法試験の受験資格の「男子たる者」という規定を削除せよと議会に陳情 した結果、1938 年から女性が司法試験を受けられるようになったのです。ですから、今 でも女性の法律家や法学部生が少ないというのは、こうした歴史と関係していると私は思 うんですね。 もう 1 つ重要なのは、家制度を維持するために、非常に厳格な性別役割分業が貫かれて きたということです。それは、私たちの個人的な生活だけではなくて、社会的生活もそれ によって組織され、男女が上下の関係になっているような社会でした。性別役割分業は、 今でも日本社会における平等を阻害する非常に大きな問題だと私は思っているのですが、 前史としてこういう時代が、明治以来ずっとあったということなのです。 ●日本国憲法の制定と女性の地位 戦後になって、日本国憲法が女性を個人として認め、基本的人権も 保障されたのですが、問題は、実際にそうなっているのか、というこ とです。 日本国憲法では、個人の尊厳を定めた憲法 13 条や、法の下の平等 を定めた憲法 14 条、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定 めた憲法 24 条などの条文が制定されました。とくに、女性を家の中 に閉じ込めて、社会的な活動をさせないような家制度を廃止したのが、 憲法 24 条でした。家族や男女の見方というのは、民主主義社会の要 になるものなのです。ところが、自民党が 2014 年に作った「改憲草案」では、憲法 24 条について、明治憲法下のような、縦の家族の関係に戻したいという内容となっており、 これは絶対に困ったな、と思っているんです。 それから、家族を縦の関係で捉えている例として、「尊属」とか「卑属」という用語や、 2013 年にようやく最高裁が憲法違反だという決定をした「婚外子の相続差別」の問題が あります。また、法律婚のできる年齢について、男女間では 2 歳の差がありますが、これ らは全部、明治民法にあったものです。だから本当は、1946 年に、民法の規定はすべて 憲法にきちんと適合しているのかを、審査しなければいけなかったのですが、ものすごく たくさん漏れたまま、ずっときてしまいました。 もう 1 つの大きな問題は、「戸籍法」です。戸籍というのは、家制度を見える形にして、 人間の序列をつけるわけです。皆さんも、戸籍を見ると「長男」「長女」「次男」などと書
- 5. 5 いてあると思います。でも、なぜ家族の中で序列をつける必要があるのか、ということで す。昔は、家制度の維持のために、そういう序列が必要でした。そして、今はその必要は ないけれども、こうした序列がそのまま残っているわけです。 ですから、今の社会というのは、基本的には、戦前からそれほど変わっていないのでは ないかというのが、私の疑問です。すなわち、制度の中身が変わったにもかかわらず、「戸 籍法」というものを、同じ名前で残した結果、人々は制度が変わったというふうに理解で きない。むしろ、変わったと思われないために、あえてそういう名前を残したのだと私は 思っています。 それから、いま話題になっている天皇の問題です。これも、戦前と今の憲法では、全く 違うものになっているのですが、だったらなぜ同じ名前を使うのでしょうか。それから、「皇 室典範」は、今ではただの法律なんですけども、明治時代の「皇室典範」は、国会の審議 を経ずに天皇が作る法律でした。にもかかわらず、戦後も「皇室典範」という名前は残っ ているのです。残っていることによって、人々は、何か特別なものというふうに勘違いを する。 また、「皇室」の人たちは、家父長制が生きている見本だと私は思うんです。一番恐ろし いことは、あの世界の女性は、男子を産むことが義務づけられているということです。こ れはたしかに、皇族の女性に対する大きなプレッシャーでもあるのですが、「後継ぎの男の 子が大事だ」という考えは、一般社会の中でもまだまだ生きている。そのことを見える形 にするというのが、皇室の制度だろうと思うんですね。 さらに、皇室というのは、「男が上、女が下」という家父長制のあり方を、生きた人間が 見せているところだと思います。それがどこに一番出てくるかというと、天皇と皇后、皇 太子と雅子さんとの、公式の場でのお互いの呼び方です。天皇は、皇后を「皇后」と呼ぶ が、皇后は天皇を「陛下」と呼ぶ。皇太子夫妻の場合も、お互いの呼称は「雅子」と「皇 太子殿下」です。 また、昨年(2017 年)に改正された、刑法の強姦罪に関する規定についても、「憲法違 反である」という議論がほとんどされてこなかった、ということがあるわけです。1907 年にできた法律が、社会の仕組みは 1945 年で変わったにもかかわらず、110 年間もその まま使われてきていたということなんです。つまり、今の憲法ができたときに、「刑法 177 条の強姦罪の規定は憲法 14 条違反である」という議論が、全然なかったのです。刑法 177 条は、昨年の改正前までは、強姦罪の被害者を女性に限っていたんです。それは女性を保 護するためではなくて、家父長制の男性中心・男性優位の社会を維持するために、性暴力 犯罪を処罰する必要があるということで、強姦罪があったということなんです。 さらに、昨年の改正前までは、性犯罪は親告罪とされており、告訴という特別な手続き が必要でした。政府の説明としては、「被害者のプライバシーを守る」という説明を後付け でしていたのですが、実際はそうではなくて、特別な手続きを要することによって被害を 訴えにくくするということで、被害の隠蔽に奉仕していたのではないか、と思うんです。
- 6. 6 そのようにして、この社会は、被害者に「恥じよ」という強制をするのです。 昨年(2017 年)に米国で「#MeToo」という運動が始まりましたが、日本ではこれは あまり盛り上がっていません。私の見るところ、日本では、性暴力の被害者は恥じるべき だという考えがすごく強い。まわりが「恥じよ」というわけです。そうすると、「私は被害 に遭いました」ということは「私は恥ずべき存在です」と自分で言っていることになるわ けです。だから、そういう運動になかなかつながっていかない。まだ日本では、隠すこと によってプライバシーを守ろうとする段階にある。だから日本では「#MeToo」運動が弱 いんじゃないかな、と思うのです。 ●憲法の変化と人々の生活 さて、憲法が変われば、人々の生活もそれに伴って変化するかというと、必ずしもそう ではないんです。だから、日本社会の生活の中で、家制度的な要素っていうものは、たく さんあるんです。毎日の切れ目のない生活の中では、法律が変わったから私たちの生活も 変わるというふうには、なかなかならないんじゃないかと思うんです。 もう 1 つは、憲法が変わったときに、民法や刑法などの法律はそれほど変わらなかった という点です。というのも、その当時、民法や刑法の改正に携わった人たちは、みんな明 治憲法下で生まれて大人になった人たちなんですね。だから、その人たちにとって、「新し い憲法に照らしてここがおかしい」というのは、ほとんど見えない話だったのではないか。 だから、民法や刑法がそのままになってしまったのではないか、と思うのです。 私は、「東京医大事件」によって、社会の根底にみじんも揺るがない岩盤のようにして、 女性差別の意識や制度が今でもあるということを思い知らされました。 憲法を変えても、新しい憲法が規定する個人の尊厳や、法の下の平等、両性の平等のよ うな新しい価値観というのは、黙っていては受け入れらません。よほど意識的に、「こうい う新しい価値観でこれから私たちはいくんだ」ということが説明され、理解されないと、 それにしたがって人々の生活が変わっていくというふうにはなりません。さらに新憲法は、 たんに新しいというだけでなくて、内容がほ ぼ 180 度違うものに変わったわけです。女 性が無権利だったところから、男女平等で、 女性も人権の主体であるというふうに変わ ったときに、そのことについて、よく分かる ように繰り返し説明する、という周知行為が ない限りは、現実はなかなかそうはなりませ ん。ところが実際には、それがほとんどなさ れていなかったということなのです。
- 7. 7 ●国による女性差別―司法の現場の実態 それから、私が今回の東京医大事件から思うことは、私自身の経験に照らしても、国に よる女性差別が許されてきた実態があるということです。 司法試験に合格すると、司法修習生として、司法研修所というとこ ろで研修を受けるのですが、司法研修所というのは最高裁判所の組織 の一部です。だから、司法研修所で女性差別が行われているならば、 最高裁がそのことを容認しているということになるわけです。 私は 1975 年に司法研修所を卒業したのですが、司法研修所の事 務室の前に、法律事務所からの求人情報が展示されていました。それ を見ると、「女性は採らない」って書いてあるわけです。あるいは、 「年齢の高い男性は取らない」と書いてあるのですが、これらは東京 医大事件にも通じるような内容ですね。そして、こうした求人は、司法研修所の事務室の 前に展示されていたわけですから、最高裁判所がそれを許していたということになる。 そこで、私たちは卒業を前にして、司法研修所と団体交渉のようなことをやって、翌年 以降はそうしたことはやめさせました。ただ、それで終わったわけではなくて、その後も、 女性の検察官はなるべく採らないとか、女性は裁判官に採用しないようにするということ が、結構続いていたと思います。 当時、私は検察官の教官に「私が検察官になりたいと言ったらどうしますか?」って聞 いたんです。そうしたら、その検察官は「あなたが男だったら、検察官に採用するのだが」 って言ったんです。これは「女は採らない」と言っているのと同じことです。それが普通 に通用していた時代があって、しかも、そんなに古い時代の話ではないのです。 最高裁判所の 15 名の裁判官の中には、現在では女性の裁判官もいますが、最高裁の裁判 官に女性が初めて就任したのは、最高裁が発足して 47 年目の 1994 年のことなんです。 それまではずっと、男性の裁判官だけでやってきたのです。それから、最高裁判所には 3 つの小法廷がありますが、すべての小法廷に 1 名ずつの女性裁判官が初めて配属されたの は、2013 年になってからのことです。だから、2013 年以前は、女性の裁判官がいない、 男性の裁判官だけの小法廷があって、そこに係属した事件は、たとえ女性の問題であろう と、男性の裁判官だけで裁判が行われていました。なお、現在では、3 つの小法廷のうち「第 1 小法廷」については、再び女性の裁判官が存在しない法廷へと戻ってしまいました。 ●法律家が憲法を無視するのはなぜか? このように、法律家が堂々と憲法を無視するような時代が、長く続きました。そうした 状態は、今でも続いているのではないかと思います。
- 8. 8 なぜこんな状態になっているのかといえば、「法律は男の分野」という固定観念が、まだ まだ強いからではないかと思うのです。すなわち、「法律は女のやることではない」という 考えが、この社会において漠然と共有されているのではないか、と思います。 それから、憲法学の教科書で最も有名な、芦部信喜氏の憲法の教科書には、憲法 24 条に 関する独立した解説がないのです。法律学の本というのは普通、法律の条文が 1 条から 100 条まであったら、濃淡はあっても、全ての条文について解説が書かれているものなのです。 ところが、憲法に関しては、女性にとってすごく大切な規定である 24 条について、一番信 頼されている芦部氏の教科書に、独立した解説が載っていないのです。それは別に、芦部 氏の本に限ったことではなく、圧倒的に多くの憲法学者の本が、24 条について知らん顔を している。せいぜい、13 条とか 14 条の解説のところの脚注で、これが家族の関係に持ち 込まれたのが 24 条である、と 1 行書いてあるだけなんです。この点については、男女の 不平等を支持している、とても大きな問題ではないか、というふうに私は思っています。 ●法律学はジェンダー嫌い? 近代法というのは、公私二元論の産物です。そして、「公」の部分 は、政治や経済や法律ですが、これは全部、男の分野だったんです。 その中でも法律といえば、公の部分のいわば屋台骨のようなところで す。他方、「私」の部分は、家族などに関する部分で、そこには女や 子どもがいるけれども、そこでもやはり、トップは家長である男なの です。だから、法律っていうのは、最初から女性を排除する仕組みに なっていた。そのことは、日本の明治時代からの法学教育の中でもず っと貫かれてきた、と私は思っています。 だから、「法律は男の分野」だと皆が思っている根底には、そうした実態があるわけなん ですね。そして、そもそも法律や法学は、男性が作ったわけです。というのも、戦前は女 性は法律によって排除されていたので、参加できなかったわけです。このような、法律や 法学は男性が作って男性が運用するという「伝統」の影響は、今でも続いています。 たとえば、法律の教科書は誰が書いているかというと、ほとんどが男性の学者です。ま た、法律を誰が教えているかというと、ほとんどが男性の学者なんですね。東大の法学部 を見ても、女性の教員はわずか数名で、ほとんどは男性です。そうすると、教科書で書か れている「経験」というものは、ほとんどが男性の経験だということになります。だから、 たとえば刑法の性暴力犯罪についても、被害者についての話が出てこないわけです。それ は偏っているんだけど、自分たち男性が主流だから、偏っているとも思わないのです。 ところで、法律学では「経験則」(経験から生まれた社会の一般的なルール)という用語 が用いられます。ところが、それが「誰の経験なのか」については、誰も問わないのです。
- 9. 9 たとえば、性暴力被害の問題で、「経験則に照らして、被害者の女性が言っていることは信 用できない」と男性が言うのです。私から見れば「それはあなたの経験にすぎない」と思 うのですが、「経験則」という言葉を使うことによって、それがあたかも普遍的なものであ るかのように受け取られて、法律の世界を支配している、という実態があるわけです。 私の友人に、フランスと日本を行き来している法律学者がいるのですが、彼女によると、 フランスでは、裁判官の 75%は女性なのだそうです。それでもフランスは、さらにジェン ダー平等を進めようとしているというので驚きなのですが、日本はものすごく遅れている。 東京医大事件について、いくつかの弁護士会は会長声明を出して批判しましたが、日弁 連は意見がまとまらないらしく、声明を出せていないんです。困ったことだと思います。 そして、東京医大事件については、シカゴ大学の統計学の先生である山口一男教授の論 考(https://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/098.html)が、問題のありか をはっきりさせています。OECD の統計によれば、日本の「医師の女性割合」は OECD 諸 国内で最下位です。にもかかわらず、日本で「女性の医師が増えたら困る」と言っている のはおかしいことなのです。 なお、この問題については、女性医師の一部から「東京医大がやったことは仕方がない んじゃないか」「女性医師が増えると困るという考えも、ある程度支持できる」というよう な意見も出ているのですが、「これって、なぜなんだろう?」と思うわけです。 そこで、私自身の弁護士としての経験から思うのは、男性がものすごく多い社会で、し かも、ある程度エリートだと思われるところにいる女性というのは、いつの間にか「二流 男性」になっている自分のことを誇らしく思うのではないか。本当は「二流市民」にすぎ ないんだけれども、男性と同じところに「入れてもらってる」ということで、誇らしいと いうように勘違いをしてしまうんじゃない かと思うんです。というのも、私自身も弁護 士になったはじめの頃は、そうだったんです。 だから、今度の東京医大事件における、一部 の女性医師の肯定的な対応というのは、そう した考えからきているのではないか、と思い ました。 駆け足での話となりましたが、以上で私の 講演を終わります。 (編集:TOSMOS 会員 須藤) ※この講演採録は、当日の角田由紀子氏による講演をもとに、編集を加えて文章にしたものであ り、文責は編集担当者にあります。
