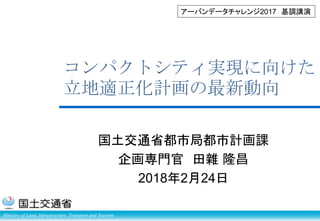
UDC2017_ファイナル_コンパクトシティ実現に向けた立地適正化計画の最新動向
- 1. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism コンパクトシティ実現に向けた 立地適正化計画の最新動向 国土交通省都市局都市計画課 企画専門官 田雜 隆昌 2018年2月24日 アーバンデータチャレンジ2017 基調講演
- 4. コンパクト・プラス・ネットワークのねらい ○医療・福祉・商業等の生活 サービスの維持が困難に ○公共交通ネットワークの縮小・ サービス水準の低下 ■ 地域経済の衰退 ■ 都市の生活を支える機能の低下 ○地域の産業の停滞、企業の撤退 ○中心市街地の衰退、 低未利用地や空き店舗の増加 ○社会保障費の増加 ○インフラの老朽化への対応 ■ 厳しい財政状況 都市が抱える課題 生活サービス機能の維持 生活サービス施設へのアクセス確保 など利用環境の向上 高齢者の社会参画 サービス産業の生産性向上、投資誘発 外出機会・滞在時間の増加による消費拡大 インフラの維持管理の合理化 行政サービスの効率化 地価の維持・固定資産税収の確保 健康増進による社会保障費の抑制 コンパクトシティ 生活サービス機能と居住を 集約・誘導し、人口を集積 まちづくりと連携した公共交通 ネットワークの再構築 + ネットワーク エネルギーの効率的利用 CO2排出量の削減 中心拠点や生活拠点が 利便性の高い公共交通で結ばれた 多極ネットワーク型コンパクトシティ 高齢者や子育て世代が安心・快適に 生活できる都市環境 ビジネス環境の維持・向上により 地域の「稼ぐ力」に寄与 財政面でも持続可能な都市経営 低炭素型の都市構造の実現 ○ 人口減少・高齢者の増加 ○ 拡散した市街地 都市を取り巻く状況 ○都市のコンパクト化は、居住や都市機能の集積による「密度の経済」の発揮を通じて、住民の生活利便性の維持・ 向上、サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等による行政コストの削減 などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策手段。 コンパクトシティ化による効果 の例 生活利便性の維持・向上等 地域経済の活性化 行政コストの削減等 地球環境への負荷の低減 3
- 7. 行政コストの削減効果 人口密度と 1人当たり財政支出(普通会計歳出額)との関係 ◎市街地が集約化するほど、公共施設やインフラの維 持・管理業務やゴミ収集等の行政サービスが効率化。 ⇒コンパクトシティ化により、行政サービスの効率 化が図られ、市民一人あたりの行政経費が縮減。 出典:H26国土交通白書 地価の維持効果(固定資産税確保効果) ◎固定資産税の多くは”まちなか“から徴収。他方、これま では、”まちなか“も郊外と同様に地価が下落。 ⇒コンパクトシティ化により、“まちなか”の土地利用 が増進し、地価が維持され固定資産税収が確保。 【地価の維持効果の一例(富山市)】 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 中心市街地平均 居住推進区域内 居住推進区域外 全国の地方部平均 H15を1とした各地区の公示地価の推移(富山市) 出典:富山市資料をもとに国土交通省作成 公共交通沿線居住推進地区外と比較して 中心市街地で約17%の地価の維持効果 約17%公共交通沿線居住 推進地区の設定 地区類型 面積比 税収比 市街化区域 5.8% 74.0% うち都心地区 0.4% 22.2% 上記以外 94.2% 26.0% 固定資産税と都市計画税の地区別徴収額(H25当初) コンパクトシティ化の効果②…行政コストの縮減と固定資産税の維持 公共交通沿線居住推進地区内 公共交通沿線居住推進地区外 都心地区 6
- 8. 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 男性 歩数分布比較 大都市+23区特別区 5万人未満の市 分布割合(%) (歩数) 中央値:5,929 中央値:7,000 男性 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 6,0003,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 大都市+23特別区 人口5万人未満の市 0.0 中央値:5,929 中央値:7,000 (歩数) ◎都市が集約化され、居住地と拠点地区が近接するほど徒歩や公共交通を利用して日常生活を営む市民が増加。 ⇒コンパクトシティ化により、高齢者の外出機会、市民の歩行量が増加し、健康な市民の増加や医療費の抑制が見込まれる。 拡散型都市構造では 自動車への依存度が増大 ■移動行動における一日一人あたりの歩行量(歩/人・日) 出典:H22全国都市交通特性調査データ、「健康増進のための歩行量実態調査とその行動群別特性分 析への応用(筑波大学谷口教授ほか)」をもとに国土交通省作成 ※H22全国都市交通特性調査対象都市のうちDIDを有する69都市の20歳以上の移動データをもとに分析 集約型都市構造だと 徒歩、公共交通による外出 、 移動機会が増大 ■高齢者の外出率(%) ※H26国土交通白書より抜粋 ■大都市と地方都市 歩数分布比較 出典:国民健康・栄養調査(2008~13,12除く)をもとに国交省作成 よく歩く人は都市規模に関係なく 歩くが、あまり歩かない人の割合 は地方都市の方が高い ○健康増進効果を把握することを目的に、まちづくりの指標 となる「歩行量(歩数)の調査のためのガイドライン」を策定 (H29.3発出) ○既往の研究等から歩行による医療費抑制効果の原単位 を整理 (1日1歩あたりの医療費抑制効果を0.065~0.072円と整理) 7 コンパクトシティ化の効果③…健康の増進
- 10. 9 2.データの重要性の高まり
- 11. EBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング) 「証拠(エビデンス)」に基づく 「政策立案(ポリシー・メイキング)」 統計改革推進会議最終取りまとめ(H29.5)より 地方公共団体における社会保障改革、公共施設の再編・集約化や老朽化対策等 への計画的な取組を 促すため、需要やコスト等について、将来見通しの検討を含 め、更なる「見える化」に向けて取り組む。 国土に関する長期計画の実行・実現に 向けて、KPIや工程表を具体化し、エビデンスに基づくPDCA サイクルを通じて政 府横断的な取組を推進する。 経済財政運営と改革の基本方針2017(H29.6)より 第3章 経済・財政一体改革の進捗・推進「2.改革に向けた横断的事項」 我が国の経済社会構造が急速に変化する中、限られた資源を有効に活用し、国民 により信頼される行政を展開するためには、政策部門が、統計等を積極的に利用 して、証拠に基づく政策立案(EBPM。エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング) を推進する必要がある。 10
- 13. コンパクトシティ形成支援チームによる省庁横断的な 支援○コンパクトシティの推進に当たっては、医療・福祉、地域公共交通、公共施設再編、 中心市街地活性化などのまちづくりと 密接に関係する様々な施策と連携し、整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的な取組として進めていくことが重要。 ○このため、まちづくりの主体である市町村において施策間連携による効果的な計画が作成されるよう、関係府省庁で構成 する「コンパクトシティ形成支援チーム」を通じ、市町村の取組を省庁横断的に支援。 府省庁横断的な支援 ○関係府省庁において関係施策が 連携した支援施策を具体的に検討 し、制度改正・予算要求等に反映 コンパクトシティ化に 取り組む市町村 モデル都市の形成・横展開 具体的な効果・事例を 目に見える形で提示 取組成果の「見える化」 ○他の市町村のモデルとなる都市 の計画作成を関係府省庁が連携 して重点的にコンサルティング ○コンパクトシティ化に係る評価指標 (経済財政面・健康面など)を開発・提供 し、市町村における目標設定等を支 援 ○人口規模やまちづくりの重点 テーマ別に類型化し、横展開 ○市町村との意見交換会等を通じ、 施策連携に係る課題・ニーズを把握 現場ニーズに即した支援施策の充 実 “横串”の視点での 施策間連携を促進 コンパクトシティの 取組の実効性を確保 国土交通省 〔事務局〕 コンパクトシティ形成支援チーム (H27.3設 置) 内閣官房/内閣府 復興庁 経済産業省 総務省 財務省 金融庁 農林水産省厚生労働省文部科学省 (施策連携イメージ) 医療・福祉 防災 都市農業 住宅 公共施設再編地域公共交通 学校・教育 子育て 広域連携 コンパクトシティの形成 都市再生・ 中心市街地活性化 ○市町村の取組の進捗や課題を関係 府省庁が継続的にモニタリング・検証 (支援チームの主な取組) 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』 (H26.12.27閣議決定)に基づき設置 環境省 12
- 15. ○384都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。 (平成29年12月31日時点) ○このうち、116都市が平成29年12月31日までに計画を作成・公表。 立地適正化計画の作成状況 ※平成29年12月31日までに作成・公表の都市(オレンジマーカー) 都市機能誘導区域、居住誘導区域ともに設定した市町村(赤字:70都市)、都市機能誘導区域のみ設定した市町村(青字:46都市) (平成29年12月31日時点) 合計384都市 鶴岡市 境町 小川町 魚沼市 森町 天理市 宇部市 行橋市 札幌市 酒田市 鳩山町 南魚沼市 長野市 舞鶴市 桜井市 山口市 小郡市 函館市 寒河江市 宇都宮市 上里町 胎内市 松本市 名古屋市 亀岡市 五條市 萩市 宗像市 旭川市 長井市 栃木市 寄居町 田上町 上田市 豊橋市 長岡京市 葛城市 防府市 太宰府市 室蘭市 中山町 佐野市 湯沢町 岡谷市 岡崎市 八幡市 宇陀市 岩国市 朝倉市 釧路市 鹿沼市 千葉市 飯田市 一宮市 京田辺市 川西町 光市 那珂川町 美唄市 福島市 日光市 松戸市 富山市 諏訪市 瀬戸市 南丹市 田原本町 柳井市 遠賀町 士別市 郡山市 小山市 成田市 高岡市 小諸市 春日井市 王寺町 周南市 北広島市 いわき市 真岡市 佐倉市 魚津市 駒ヶ根市 豊川市 豊中市 河合町 小城市 石狩市 須賀川市 大田原市 柏市 氷見市 茅野市 刈谷市 池田市 徳島市 嬉野市 福島町 喜多方市 那須塩原市 市原市 黒部市 塩尻市 豊田市 吹田市 和歌山市 阿南市 基山町 八雲町 二本松市 那須烏山市 流山市 小矢部市 佐久市 安城市 高槻市 海南市 古平町 国見町 下野市 酒々井町 入善町 千曲市 蒲郡市 守口市 有田市 高松市 長崎市 鷹栖町 猪苗代町 芳賀町 安曇野市 江南市 枚方市 新宮市 丸亀市 大村市 東神楽町 矢吹町 八王子市 金沢市 小牧市 茨木市 湯浅町 坂出市 芽室町 新地町 前橋市 府中市 小松市 岐阜市 東海市 八尾市 善通寺市 熊本市 高崎市 日野市 輪島市 大垣市 知立市 寝屋川市 鳥取市 観音寺市 荒尾市 青森市 水戸市 桐生市 福生市 加賀市 多治見市 田原市 河内長野市 多度津町 玉名市 弘前市 日立市 伊勢崎市 羽咋市 関市 東郷町 大東市 松江市 菊池市 八戸市 土浦市 太田市 相模原市 白山市 瑞浪市 和泉市 大田市 松山市 黒石市 古河市 館林市 横須賀市 野々市市 大野町 津市 箕面市 江津市 宇和島市 大分市 五所川原市 石岡市 渋川市 鎌倉市 穴水町 四日市市 門真市 八幡浜市 竹田市 十和田市 龍ケ崎市 藤岡市 藤沢市 静岡市 伊勢市 高石市 岡山市 新居浜市 杵築市 むつ市 下妻市 吉岡町 小田原市 福井市 浜松市 松阪市 東大阪市 倉敷市 西条市 常総市 明和町 秦野市 敦賀市 沼津市 桑名市 阪南市 津山市 大洲市 都城市 盛岡市 常陸太田市 邑楽町 厚木市 小浜市 熱海市 名張市 総社市 伊予市 花巻市 高萩市 大和市 大野市 三島市 亀山市 神戸市 高梁市 四国中央市 鹿児島市 北上市 笠間市 さいたま市 伊勢原市 勝山市 富士市 伊賀市 姫路市 赤磐市 西予市 薩摩川内市 取手市 川越市 海老名市 鯖江市 磐田市 朝日町 尼崎市 真庭市 奄美市 仙台市 牛久市 本庄市 あわら市 焼津市 西宮市 高知市 姶良市 大崎市 つくば市 東松山市 新潟市 越前市 掛川市 大津市 西脇市 広島市 南国市 利府町 守谷市 春日部市 長岡市 越前町 藤枝市 彦根市 高砂市 呉市 土佐市 那覇市 常陸大宮市 深谷市 三条市 美浜町 袋井市 草津市 朝来市 竹原市 須崎市 秋田市 坂東市 戸田市 新発田市 高浜町 裾野市 守山市 たつの市 三原市 大館市 かすみがうら市 志木市 小千谷市 湖西市 栗東市 福崎町 福山市 北九州市 湯沢市 つくばみらい市 坂戸市 見附市 甲府市 菊川市 甲賀市 太子町 府中市 大牟田市 大仙市 小美玉市 鶴ヶ島市 燕市 山梨市 伊豆の国市 野洲市 東広島市 久留米市 大洗町 日高市 糸魚川市 大月市 牧之原市 湖南市 奈良市 廿日市市 直方市 山形市 城里町 毛呂山町 五泉市 笛吹市 函南町 東近江市 大和高田市 飯塚市 米沢市 東海村 越生町 上越市 上野原市 長泉町 大和郡山市 下関市 田川市 佐賀県 奈良県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 鳥取県 島根県 大阪府 兵庫県 長崎県 熊本県 大分県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 山口県 岐阜県 岡山県 富山県 愛知県 滋賀県 和歌山県 山梨県 三重県 広島県 京都府 静岡県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 千葉県 福井県 長野県 山形県 栃木県 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 北海道 福島県 茨城県 埼玉県 群馬県 14
- 17. 都市計画に関するデータの利用環境の充実 平成29年度に検討会を設置し、個人情報保護との関係に係る課題の整理等を踏まえつつ、データの共通フォーマットを作成するなど、平成30年度 中にガイドラインの作成等を行い、都市計画基礎調査情報のオープンデータ化等を促進。 都市計画基礎調査情報のオープン化に向けた検討 都市構造カルテのイメージ Y 基礎情報 Y市 人口18万人 都市の状況 人口 面積 人口密度 都市計画税率 市町村合併状況 都市計画区域の変遷 土地利用 地域地区 市街地再開発事業 建物 都市インフラ 公共施設 交通 財政 地価 産業 環境 災害 etc… etc… Z Y市 V W X E D市 A市 人口18万人面積 人口密度 都市計画税率 都市インフラ 公共施設 交通 財政 地価 産業 環境 災害 etc… etc… B A C B A 基礎情報 A市 人口○○万人 都市の状況 人口 面積 人口密度 都市計画税率 市町村合併状況 都市計画区域の変遷 土地利用 地域地区 市街地再開発事業 建物 都市インフラ 公共施設 交通 財政 地価 産業 環境 災害 etc… etc… 平均 基礎情報 人口10~40万人 平均 都市の状況 人口 面積 人口密度 都市計画税率 市町村合併状況 都市計画区域の変遷 土地利用 地域地区 市街地再開発事業 建物 都市インフラ 公共施設 交通 財政 地価 産業 環境 災害 etc… etc… D 基礎情報 D市 人口15万人 都市の状況 人口 面積 人口密度 都市計画税率 市町村合併状況 都市計画区域の変遷 土地利用 地域地区 市街地再開発事業 建物 都市インフラ 公共施設 交通 財政 地価 産業 環境 災害 etc… etc… さらなる「見える化」への活用も検討 都市規模別の 平均値との比較 都市間 比較 検討項目 ・地方公共団体が保有する都市計画情報のオープン化は進んでいない ⇒GIS化の促進や個人情報保護との関係の整理が 必要。 ・各自治体を横並びで比較することができない。 ⇒共通化された項目やフォーマットの整理が必要。 課 題 ○人口減少、高齢化の更なる進展が見込まれる中、日常生活 に必要な都市機能が維持された持続的でコンパクトなまちづ くりの推進が強く求められる。 ○地域の状況や人口動態等を総合的に勘案しつつ、いかなる 都市構造を目指すべきか、客観的かつ定量的な分析、評価 のもと、市民、民間事業者、行政等、地域の関係者でコンセン サスを醸成することが必要。 ○各都市におけるコンパクトなまちづくりを支援する参考図書と して都市構造のコンパクトさを評価する手法をとりまとめ。 1.評価分野 都市構造を評価する分野として以下の6分野を設定 ①生活利便性 ②健康・福祉 ③安全・安心 ④地域経済 ⑤行政運営 ⑥エネルギー/低炭素 2.評価指標 ・各評価分野ごとに、都市のコンパクトさとの関連性、当該 分野における市民・民間、行政等の視点等を勘案し、評価 指標を設定(下記「指標例」参照) ・評価指標の一部は、現況評価のみならず、将来予測評価 も可能 3.全国平均値の提示 評価指標毎に、可能な限り、現状における全国平均値、都 市規模別平均値を算定・提示 都市構造の評価に関するハンドブック(H26.8作成) 評価手法の概要 これまでの取 組 現在の取組 分析、評価の基礎となるデータの利用環境を充実 1.都市計画基礎調査情報について (1)情報の内容、取得方法 2.個人情報保護等の観点からの留意事項 (1)法令に規定する個人情報に該当する情報の範囲 (2)利用目的および利用主体に応じた利用・提供の一般的な整理 ⅰ)全体概観(見取り図) ⅱ)都市計画目的での利用 ⅲ)都市計画以外の目的での利用 3.情報を利用・提供する方法 4.より利用しやすくするための方策 (1)基本的な考え方 (2)GIS化 (3)オープンデータ化 (4)均質なデータ整備 (5)データのフォーマット、コーディングの共通化・互換性確保 (6)G空間情報センターとの連携 5.その他留意事項 (1)二次利用の考え方 ① 著作権、所有権、利用権 ② 免責等利用条件 (2)情報の正確性の確保 (3)セキュリティー 6.オープン化の取り組みをPDCAサイクルで評価 ①生活利便性 日常生活サービスの徒歩圏充足率、生活サービス施設の利用 圏平均人口密度、公共交通の機関分担率 等 ②健康・福祉 徒歩と自転車の機関分担率、高齢者徒歩圏に医療機関がない 住宅の割合、歩行者に配慮した道路の延長比率(都市機能を誘導する区 域) 等 ③安全・安心 市民一万人当たりの交通事故死亡者数、公共空間率、空き家 率 等 ④地域経済 従業者一人当たり第三次産業売上高、従業人口密度(都市機能 を誘導する区域)、都市機能を誘導する区域における小売商業床効率 等 ⑤行政運営 市街化調整区域等における開発許可面積の市街化区域等におけ る開発許可面積に対する割合、市民一人当たり税収額(個人市民税・固 定資産税) 等 ⑥エネルギー/低炭素 市民一人当たりの自動車CO2排出量、家庭部門におけ る一人当たりのCO2排出量 等 指標例 16
- 18. まちづくりにおける「健康増進効果」の把握 Ⅰ ガイドラインの背景 ・コンパクトシティの取組によって 歩行量(歩数)の増大が期待される ・歩行は身体活動の基本、歩行量 (歩数)の増大により健康増進効 果が期待される Ⅱ 日常生活における歩行量(歩数)の特性 ・多く歩く人の存在が平 均を押し上げており、 モニタリングには中央 値を採用することを推奨 Ⅳ 目標の設定と効果の試算 ・目標設定の考え方を提示(健康日本21(第二次)の歩数目標等) (例 +約1,500歩、男性(20~64歳)9,000歩,(65歳~)7,000歩) ・既往の研究等から歩行による医療費抑制効果の原単位を整理 (1日1歩あたりの医療費抑制効果を0.065~0.072円と整理) Ⅴ 調査手法の特徴とモニタリングのための調査手法の提案 ・パーソントリップ調査、プローブパーソン調査、歩数計調査、 アンケート(IPAQ)調査の特徴を整理 ・モニタリングのための調査手法の提案と分析における留意事項 を整理 〇コンパクトシティの多様な効果の一つである健康増進効果を把握することを目的に、身体活 動の基本であり、まちづくりの指標となる歩行量(歩数)の調査のためのガイドラインを策定 図1 移動行動における 一日一人あたりの歩行量 (歩/人・日) 図1出典:「健康 増進のための歩 行量実態調査と その行動群別特 性分析への応用 (筑波大学谷口 教授ほか)」をも とに国交省作成 Ⅲ 取組の流れと検討のポイント ・地方公共団体における取組フロー、留意点を提示 ・特に重要な目標・効果・調査手法はⅣ・Ⅴで詳細化 1.目標の設定 ・立地適正化計画制度の活用 ・目標の設定と効果の試算 2.調査手法の選定 ・各種調査手法の特徴を踏まえて調査手法を選定 3.調査の実施、分析 ・歩行量(歩数)の特性を踏まえた分析の留意点 4.モニタリング(継続調査) ・継続調査とPDCA 都市規模別・年代別 (男女計中央値)(例) 大都市+ 23区特別区 15万人 以上 15~ 5万人 5万人 未満 20代 7,568 7,038 6,954 6,507 30代 7,001 6,794 6,549 6,220 40代 7,398 6,973 6,815 6,905 50代 7,528 6,812 6,628 6,449 60代 6,521 6,155 5,961 5,624 図2 男女別歩数の分布 ・都市規模別、男女別、年齢 別の中央値を整理(都市規 模が大きいほど歩行量(歩 数)が多い→Ⅰと合致) ・よく歩く人は都市規模 に関係なく歩くが、あ まり歩かない人の割合 は地方都市の方が高い 表1 1日当たりの歩数分布 ※ 健康増進効果に着目したまちづくりの取組については、「健康・医療・福祉の まちづくりの推進ガイドライン(平成26年8月)」を参照。 表1、図2,3出典:国民健康・栄養調査(2008~13,12除く)をもとに国交省作成 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 男性 女性 分布割合(%) 中央値:5,740歩 平均値:7,146歩 中央値:6,500歩 2,000歩 4,000歩 6,000歩 8,000歩 10,000歩 12,000歩 14,000歩 16,000歩 18,000歩 20,000歩 平均値:6,231歩 差 491 差 646 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 男性 歩数分布比較 大都市+23区特別区 5万人未満の市 分布割合(%) (歩数) 中央値:5,929 中央値:7,000 図3 大都市と地方都市 歩数分布比較 男性 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 6,0003,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 大都市+23特別区 人口5万人未満の市 0.0 中央値:5,929 中央値:7,000 (歩数) 17
- 19. 「まちの活性化」を測る指標の開発 分野 経済効果、財政効果を表す指標候補 経済効果 にぎわい 歩行者通行量、空き店舗率 など 雇用 従業者数、昼間人口 など 地価 地価公示、地価調査 など 財政効果 市税 法人・個人市民税、固定資産税、都市計画税 など コスト 上下水道料金、維持補修費 など ②既存の統計データだけでは、市町村毎の現状把握やモニタリ ングができないものでも、必要に応じて、その有用性や調査 手法を併せて市町村に示すことも重要 画像解析の例 収集画像 AI技術を用いて各緑枠内 の人数を推定 数取器を用いた人手による計測結果との 比較検証 計測時の留意事項等を整理してガイドラ インを作成 指標選定にあたっての視点 ①利用データは、既存の統計データを活用し、容易に入手が可 能なもの 既存統計データから、都市のコンパクトさを示す指標(人口密度 等)との相関を分析中 経済効果、財政効果を表すふさわしい指標を選定予定 ○歩行量(歩数) → 歩行量(歩数)調査のガイドライン (H29年3月発出) ○歩行者通行量 → 新技術※を活用した新たな調査手法 (検討中) ※カメラ画像解析 など 18
- 22. ご清聴ありがとうございました
Editor's Notes
- 4
- ○コンパクトシティ政策の健康増進効果は、社会保障費削減に寄与することへの期待から、政府内で注目度が高い。 ○計画の効果指標になり得る、歩行量(歩数)について、データの特性や、調査方法や分析の際の留意点を整理し、計画を作成し施策を実施する際のガイドラインをまとめた。 ○調査手法の留意点としては、 パーソントリップ調査は、出発地・目的地の移動行動時間の調査のため建物内や短距離トリップが捕捉できない プローブパーソン(GPS機器)調査や、歩数計(・行動日誌)調査は、被験者負担が大きく大規模調査困難、モニター調査となりサンプルに偏りがある 身体活動質問票は、歩行時間把握のため歩数への推計誤差あり、回答する歩行時間が課題になる傾向がある など。 ○歩行による健康増進効果の原単位として、医療費抑制額が1日・100歩で6~7円となることを、既往の研究からまとめた。
