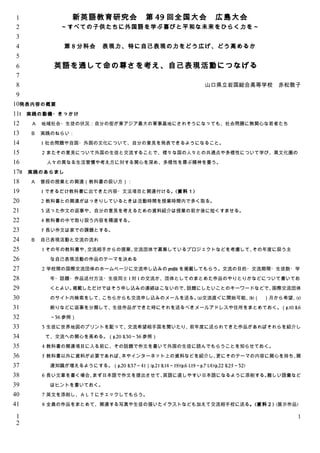More Related Content
Similar to 2012年新英研全国大会第8分科会発表原稿 赤松敦子
Similar to 2012年新英研全国大会第8分科会発表原稿 赤松敦子 (18)
More from Atsuko Akamatsu
More from Atsuko Akamatsu (14)
2012年新英研全国大会第8分科会発表原稿 赤松敦子
- 1. 新英語教育研究会 第 49 回全国大会 広島大会
~すべての子供たちに外国語を学ぶ喜びと平和な未来をひらく力を~
第 8 分科会 表現力、特に自己表現の力をどう広げ、どう高めるか
英語を通して命の尊さを考え、自己表現活動につなげる
山口県立岩国総合高等学校 赤松敦子
発表内容の概要
Ⅰ 実践の動機・きっかけ
A 地域社会・生徒の状況:自分の街が東アジア最大の軍事基地にされそうになっても、社会問題に無関心な若者たち
B 実践のねらい:
1 社会問題や自国・外国の文化について、自分の意見を発表できるようになること。
2 またその意見について外国の生徒と交流することで、様々な国の人々との共通点や多様性について学び、異文化圏の
人々の異なる生活習慣や考え方に対する関心を深め、多様性を尊ぶ精神を養う。
Ⅱ 実践のあらまし
A 普段の授業との関連(教科書の扱い方):
1 できるだけ教科書に出てきた内容・文法項目と関連付ける。(資料1)
2 教科書との関連がはっきりしているときは活動時間を授業時間内で多く取る。
3 送った作文の返事や、自分の意見を考えるための資料紹介は授業の前か後に短くすませる。
4 教科書の中で取り扱う内容を精選する。
5 長い作文は家での課題とする。
B 自己表現活動と交流の流れ
1 その年の教科書や、交流相手からの提案、交流団体で募集しているプロジェクトなどを考慮して、その年度に扱う主
な自己表現活動の作品のテーマを決める
2 学校間の国際交流団体のホームページに交流申し込みの profile を掲載してもらう。交流の目的・交流期間・生徒数・学
年・話題・作品送付方法・生徒同士 1 対 1 の交流か、団体としてのまとめた作品のやりとりかなどについて書いてお
くとよい。掲載しただけではそう申し込みの連絡はこないので、話題にしたいことのキーワードなどで、国際交流団体
のサイト内検索をして、こちらからも交流申し込みのメールを送る。(a)交流直ぐに開始可能、(b)( )月から希望、(c)
断りなどに返事を分類して、生徒作品ができた時にそれを送るべきメールアドレスや住所をまとめておく。(p.10 ll.6
~36 参照)
3 生徒に世界地図のプリントを配って、交流希望相手国を聞いたり、前年度に送られてきた作品があればそれらを紹介し
て、交流への関心を高める。(p.20 ll.30~36 参照)
4 教科書の関連項目に入る前に、その話題で作文を書いて外国の生徒に読んでもらうことを知らせておく。
5 教科書以外に資料が必要であれば、本やインターネット上の資料などを紹介し、更にそのテーマの内容に関心を持ち、関
連知識が増えるようにする。(p.20 ll.37~41)(p.21 ll.14~19)(p.6 l.19~p.7 l.4)(p.22 ll.25~32)
6 長い文章を書く場合、まず日本語で作文を提出させて、英語に直しやすい日本語になるように添削する。難しい語彙など
はヒントを書いておく。
7 英文を添削し、ALTにチェックしてもらう。
8 全員の作品をまとめて、関連する写真や生徒の描いたイラストなども加えて交流相手校に送る。(資料2) (展示作品)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 2. 9 返ってきた返事を紹介する。返事に対するお礼や感想も短くてもよいのでできるだけ送るようにする。(展示作品)
10 交流の作品を、文化祭や外部の展覧会、生徒の意見を発表できるホームページなど様々な所に出して、生徒が「自分たちの
意見が、教室の中だけでなく、様々なところで読まれている」という意識を持てるようにする。(p.20 ll.30~34)
11 交流相手校からの交流作品のリクエストにも授業の予定に差し支えない範囲でできるだけ応える。授業では時間を取れ
ない時は、課題にしたり、ボランティアの生徒だけの参加という形もある。(p.23 ll.2~3) (p.25 ll.5~ 6)
C 生徒はどう変わったか:(pp.18~20)(資料3)
1 英語は本当に外国の人と意見を交わすのに使えるのだと実感し、英語にも外国の人々や文化に関心を持った生徒が多く
いた。
2 社会問題についてもっと関心を持って、改善のためにできることから始めたいと感想に各生徒も多かった。
3 実際に問題解決に取り組んでみた生徒もいた。
4 平和や環境の問題について深く考えることで命の尊さを改めて認識した生徒もいた。
Ⅲ 実践の成果と課題
A 実践の意義:
1 長い英文を書くことに慣れた。
2 学習意欲が高まった。
3 異文化の人々の生活様式や考え方について関心が高まった。
4 学んだことを行動につなげることができた。
B 課題:
1 交流の継続。
2 学年のスケジュールのずれを考慮した作品の送付時期、返事を返す時期の調整。
3 学習以前の問題を抱えている生徒への対応。
Ⅳ 生徒作品の紹介 (資料4)(展示作品)
はじめに
広島大学で行われた平和教育についての教員免許更新講習で、『アメリカはなぜ日本に原爆を投下したのか』(ロナルド・タカキ
著)という本が紹介された。原爆が投下された理由は複数あるが、側近・軍・科学者達から反対意見が出されても、その投下の最終
決定を下したハリー・トルーマンが人種差別主義者で、学歴コンプレックスなどから「強いアメリカの強い大統領」になることにこ
だわりがあったこともその一因の可能性があるとして記述されていた。自分で教えているクラスの中に、または自分の生徒と交流す
る外国の生徒の中に、将来トルーマンのような決断を下す生徒がいる可能性もある。生徒達が、人権教育や平和教育を充分に受けて、
学歴が人間の価値であるかのような思いこみに囚われない大人に育つよう手助けすることは、戦争・犯罪者・自殺者のいない平和
な社会を創るために大変重要なことだと改めて認識した。
人権や平和や環境等、世界的に重要な問題を、ALTと一緒に何かの活動をしたり、インターネットや郵便を利用して外国の生徒
たちと交流したりといった「体験」から学ぶ機会を増やすと、より強く学んだことが心に残り、視野が広がるという教育的効果がある
のではないかと思われる。それが英語学習の重要な動機づけとなることを実際に度々見てきた。また、そうした「体験」を共有するこ
とで、ALTや外国の生徒たち、その生徒たちを教えている先生方の、日本人に対する固定観念や偏見を少しでも変えることができ
るかもしれないという草の根の国際交流の価値も測り知れない。
生徒達と授業以外の時間に図書室でいろいろ雑談をしていると、自分の人生に対しても、社会のあり方に対しても悲観的な発言を
する生徒が時々いる。自分の人生も、今の問題が山積みの社会も、自分一人の力ではどうしようもないから変えようという努力は無
駄だという考えで、努力している人をあざ笑ったりもする。自分に欠点があっても、ありのままの自分を愛するという自己肯定感が
足りないために、本当の意味で他を愛するということもできないことからそういう無力感が生じるとカウンセリングのセミナーで
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 3. 聞いたことがある。そういう基本的な心の問題も考えながら、英語を通しての交流で、前向きな考えを生徒が自分の中から引き出せ
るような機会を作れないものだろうか。できるだけいろいろな場面で長所を褒めるということがまず基本かもしれない。それはただ
教科書や問題集の問題が解けたとか、その例文を正確に覚えることができたということで褒めるより、日本語では言いたいことが伝
わらない世界に住んでいる人たちに、自分で考えて字や絵なども使って個性豊かに表現したことを褒めるほうが、本人の達成感や自
尊感情を高めるのではないだろうか。日本人の生徒達のそうした感情や学業に対する興味が他国に比べて大変低いことは学力低下
の問題よりももっと重大な問題であると OECD の調査結果等で指摘されている。
また、岩国市で空母艦載機移転拒否を理由に 35 億円もの補助金がカットされた後に、空母艦載機移転を拒否する集会が市内で何
度か開かれたが、参加者は年配の方が多く、高校生・大学生ぐらいの年頃の人は大変少なかった。自分の街が極東最大の軍事基地に
されようというのに、若者は知っていてそんなものは大人の考える問題と思い参加する気がないのか、単に事実を知らされていない
のかどちらだろうか。受験勉強の籠の鳥になっているうちに、社会の動きに疎くなっているのだろうかと考えると、センター対策の
問題集にずいぶん時間を割いている自分の授業が恐ろしくなった。
前置きが長くなったが、以上のような理由で、2008 年から、「平和」のテーマを中心にして生徒が自己表現する機会を作り、作品で
国際交流をする活動を英語の授業に取り入れた。平和メッセージという自己表現の試みが生徒の学びを深めるという報告が英語教
育雑誌などにこれまでも掲載されてきたし、自分でも英会話部の活動として以前取り組んだことがあったので、改めて授業の中で規
模を広げて取り組もうと考えた。
<前半>山口県立高森高等学校での実践
前任校である山口県立高森高等学校で、3 年生のWriting・時事英語・国際コミュニケーション、そして 2 年生の国際コミュ
ニケーションを担当した。高森高校はクラス数は 9 で、生徒数は約 350 人の普通高校である。併設の中学校から進学する生徒と高校
から入学する生徒の間での学力差が大きい。この時は図書館運営も担当していて、読書を通じて考え行動する生徒を育てる必要性を
常に感じていたので、図書館を利用した調べ学習も活用する計画を立てた。以下にその概要を述べる。
Ⅰ 平和についての関心を喚起する教材提示
A Writing
1 オードリー・ヘップバーンのインタビューのビデオ視聴
Writing の教科書に紹介の文章が載っていたので、関連資料としてインタビューのビデオを視聴。その中に出て
くるアフリカの飢餓の状況と、飢餓に苦しむ子ども達を助ける理由は「愛」というヘップバーンの言葉を紹介。
2 ジョン・レノンの歌を元にして大勢の歌手が平和を訴えるビデオクリップ視聴
Writing の教科書にジョン・レノンの紹介の文章が載っていたので、関連資料としてジョン・レノンの ”Give
Peace a Chance”の曲を元にして特に湾岸戦争に反対するメッセージを大勢の歌手が共同で録音したビデオ(販
売元 Wienerworld)を視聴。湾岸戦争の映像について説明を補足する。歌詞とジョン・レノンに対するアメリ
カ政府の対応の資料を配布。
B 時事英語
1 チベット問題についての資料紹介
時事英語で、『週刊 ST』という英字新聞の 2009 年 3 月 20 日号の”Dalai Lama blasts ‘brutal crackdown’”の記
事を読み、チベット問題について山際素男氏の『チベット問題』など図書室にあるチベットに関する本を紹介。チ
ベット人が拷問を受ける場面の記述だけを読んで中国人全体に対して「怖い」という偏見を持たないように解説。
アブグレイブなどの強制収容所での虐待や戦時中の日本人によるアジアの様々な国の人々に対する虐待、様々な国
での先住民虐待など、巨大な権力によって殺人が正当化される異常な環境の中では様々な人が同じような行動を取
る可能性があることを考えてみるように指導。
2 イラク戦争の実情についての DVD 視聴(2009 年度)
時事英語で、『週刊 ST』の 2009 年 5 月 1 日号の”Release of ‘torture memos’ sparks fury”
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 4. (ブッシュ政権時代に使用された CIA による拷問に関する覚え書きをオバマ大統領が公表したニュース) と 5 月 22 日号
の”U.S soldier kills five comrades in Iraq”(イラクで長期に軍務についた兵士が同僚を射殺し、米軍事司令部が兵士の心の
健康について調査を開始したことと、アフガニスタンの兵力増強を求めてきた現地司令官が解任されたニュース)の記事を
読んだので、その参考資料として「イラクの子どもを救う会」の西谷文和氏がイラクの現状をレポートしたDVD『イラ
ク・・・戦場からの告発』と『ジャーハダ イラク民衆の闘い』の一部を視聴。
記事を読み、DVD を視聴した生徒の感想:
「数字の上に数倍の被害がある」という言葉がとても心の中に響いた。新聞やニュースで見る「死者何人」という言葉だけでは伝わ
らない現場の状況や人の苦しみというものを見た気がした。何の罪もない人々が、ただ戦争を起こした国に住んでいたということだ
けで傷つけられないといけないということは全くおかしなことである。遊んでいたら不発弾に触れてしまって友人や体の一部を失
ってしまった子供や、通学中に突然発砲され夢を失ってしまった子どもたちにどう言葉をかければいいのか分からない。平和に暮ら
している私達にとって、毎日生死の境に立たされている彼らの気持ちはとうてい分かり得ないだろうと思う。しかし、彼らを助ける
ために何かできることが必ずあるはずだ。私達は言葉を武器に戦争と闘うことができると思う。今回の DVD では、アメリカ合衆国が
一方的に悪く流れていたように思うが、それは違うと思う。戦争を起こす世界が悪いのだ。どうして殺人をすると罰せられるのに戦
争で人を殺しても良いとされるのだろうか。どうして地雷を埋めた人や作った人達は罪を感じずに生きていけるのだろうか。一国だ
けが悪いわけではないと思う。戦争を良しとするこの麻痺しきった世界全体の責任だろう。私達がここで戦争反対の声を上げ、何か
行動に移すことができれば理不尽な傷を負う人々は少しずつ減っていくと思う。世界の現実を突きつけられるこの映像はショッキ
ングなものではあるが、現状を把握し、私達にできることを考えて行く時間も必要だと思った。
生徒の感想のいくつかを紹介し、加害の事実を学ぶときに注意すべきこととして、加害者もそのような行動を取
るように精神的に追い詰められるような原因があることを考えると被害者としての側面もあること、一部の人のマ
イナスイメージの行動を見聞きしたときに、その国民全員がそういう特徴があるかのように思いこんで偏見を持た
ないように気をつけるべきことなどを説明した。裁判員制度も始まったので、自分が人を裁くという立場になった
時には特にこのような視点から総合的に状況を捉える必要があることについて付け加えた。
C 国際コミュニケーション
1 「日本は平和」かどうか考えるための資料
生徒の平和メッセージに「日本は平和」という言葉が大変多くあったので、本当に平和かどうか考えてみる資料として紹介
した資料:『横浜市歴史教科書採択問題』(日本平和大会平和教育分科会発表資料)・『今の日本は米兵犯罪を裁けない?!
~この日米密約を許せますか』・『米軍ジェット機事故で失った娘と孫よ』(神奈川県米軍機墜落事件被害者遺族の書いた実
話)・『ネルソンさんあなたは人を殺しましたか』(沖縄で訓練しベトナムで市民を大勢惨殺した米兵の体験記)・『祈・恒
久平和 郷土の戦争体験記』(印刷:(株)ぎょうせい中国支社 地元の戦争体験を語り継ぐ有志の方が 20 名集まって出版
されたこの本を読んで、自分達の住む町にあった戦争の実態を学び、これまでなぜそれを知らずにすんできたかを考える予定
だったが、時間が足りず実施できなかった)
2 ALT(アメリカ合衆国出身)の故郷の話と関連して平和について考えるための資料
経済的に大学に進学するのが難しい高校生が、奨学金などがあるので軍隊に志願するよう勧められ、入る時には、自分が実
際に戦場でどんな目に遭わされるか、自分がどのような行動を取るよう強いられるかよくわからずに入ってしまう。しかし、
戦場に実際に送られて、精神的にも身体的にも大きな傷を負って帰ってきたり、帰ってこない人もいる。そういった、ALTの
故郷の町の話と関連して、『貧困大国アメリカ』に描かれている、社会的弱者を戦場に送り込む差別的金儲けシステムとしての
戦争について紹介した。
3 教育と平和の関連を考える資料
APEC ジュニア会議が広島で開かれた折に、海外からの参加者に生徒の平和メッセージや日本紹介のエッセイを配布した。
その会議のワークショップで、平和を創るための教育の重要性が話し合われていたので、特に台湾から来た生徒の提案「東ア
ジアに多い、講義を聴いて暗記中心の受験勉強を、発表や討論などコミュニケーション能力を育て創造性を生かす教育に変え
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 7. 争感』『戦争』『家も学校も焼けてしまった』『戦争と占領』『絵で読む広島の原爆』『非常事態のイラクを行く』『ひめゆりの沖縄
戦』
G Peace Message の書き方の説明
選んだ本を読んで、単にその感想だけでなく、「平和を創るために何をするべきか」を提案するメッセージを書くという主題
を説明する。最初に簡単に自己紹介を入れることとした。
B4縦の横書き罫線の入った作文用紙を配布。半分以上(200語程度)は書くように指示。
H Peace Message の送り先紹介
インターネットの英語教育についてのホームページや、帰国した ALT、現職 ALT の友人、日本にホームステイに来たことが
ある人などを通じて海外の多くの学校に実際に送ることを説明。本校内で参考作品として紹介したり、他校に送ったり、イン
ターネットのホームページに作品を公表するかどうかは後日アンケートを実施。
I その他の課題設定例
1 加害の歴史を中心に・・・前年度の反省から
前年度(2008 年)、資料として世界中の様々な戦争や平和や飢餓についての書籍を紹介したが、多くの生徒が日本人が
犠牲になったこと(特に原爆の被害)、地雷の問題などを採り上げており、日本の加害の側面について言及した生徒が少な
かった。戦争という異常な状況の中では様々な人が残虐になるのであり、日本人だけが異常に残酷な国民であるかのような
印象を与えることはよくないと思われる。しかし、親族や友人知人から聞いた日本軍の戦時中の行動について強い印象を持
っている外国の人と話す機会が多々あり、加害の歴史を日本人の若者がきちんと学んで、同じことは繰り返さない社会を自
分達が作るという意識を持つことは、英語かまたはその他の外国語を通して外国の人と親睦を深めるにあたって、基本的に
重要なことの一つではないかと思った。
そこで 2009 年度は国際コミュニケーションと時事英語の授業で、加害の歴史の一部として従軍慰安婦の問題を平和メッ
セージを書く前の資料として紹介した。アムネスティー・インターナショナル日本支部の出した従軍慰安婦問題に対する
声明文と岩波ジュニア新書の『「従軍慰安婦」にされた少女たち』(石川逸子著)の抜粋を紹介し、図書室カウンター横に展
示してあるその他の加害の歴史についての本も紹介した。
加害の歴史についてほとんど知らなかった生徒や、歴史上には様々な国による加害の事実があったのに日本人だけがい
つまでも第二次世界大戦中の加害を責められるのはおかしいと主張する生徒もいた。英語の授業の中だけで様々な国の起
こした加害の事実をすべて教えるということは難しいが、他教科の教員と相談・協力しなから、図書室の資料の幅広い紹介
も含めて生徒の認識が広く深くなるように援助していく必要があると思われる。
また、外国から送ってもらった平和メッセージの中に、自国の他国への攻撃を正当化するだけで、被害者の痛みに対する
思いやりが感じられないメッセージもあった。そうしたメッセージを書いた生徒がいる学校に、自国の加害によりどのよう
な被害があったのか学ぶことから考えた平和メッセージを送ることにより、被害者の視点から戦争について学ぶことの重
要さを理解し、自分の国の加害により何の罪も犯していない人々まで残酷な目に遭っていることを学び、どうするべきかを
考えるきっかけにしてもらえないかと考えている。常にすべての人・環境の被害を避け、新たな憎しみを生み出さないため
には、どのような武力攻撃よりも、多くの人々の協力で平和的解決方法を模索し、行動していく方がよいということに気づ
いてもらえることを希望している。
2 詩と絵の取り組み
冬休みの課題として、自分で英語の詩で平和な世界を表現するか、外国から送られてきた平和メッセージや詩の内容を表す
絵を描くかを選択して提出することを課した。英語のテストで高得点を取ることは苦手でも、このような課題では、素晴らし
く深い美しい作品を創る生徒が多い。
3 日本の美しさ伝統の良さを紹介
日本の過去の戦争犯罪を読むと日本に嫌悪感を持ってしまう生徒もいる。しかし、日本の伝統の素晴らしさを意識するこ
とも大事なので、教科書の課題に旅行の勧めの手紙を書く課題があったのに合わせて、自分の住む町や日本の他の街を紹介す
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 10. なぜ、人は人を殺すのか? 他人を殺してはいけないことは当たり前のことです。昨年、私は滋賀県に、全国高校生交流集会に参
加しに行きました。そこで、戦争が始まった後も、イラクに行っている最後の人である西谷文和さんによる講演を聴きました。そこで、
今まで知らなかった多くの事実を知ったのです。
政府やマスメディアがそれらの事実を意図的に隠蔽しています。私達、日本人もまた、税金を払うことにより、戦争に荷担してい
る、殺人者でもあるのです。しかし、すぐには、私達にはそのような状況を変えることができません。
私達には何ができるだろう。私達は自発的に、ただ真実を知るべきなのです。私達は、簡単に、メディアからの情報を信用しては
いけないのです。そして、自分自身の意見を持つことが大事なのです。私達はプロパガンダに騙されてはいけないのです。
Ⅳ 交流相手の見つけ方
A 学校間の国際交流促進のためのホームページの利用
1 ePals
約140の学校に ePALs http://www.epals.com/ というホームページを通じて生徒たちの平和メッセージを韓国から届
いたメッセージと一緒に送った。他の類似のホームページの掲示板でも呼びかけたが、このサイトが一番反応がよかった。ま
ず peace という言葉を担当者の自己紹介や プロジェクト説明の中に入れている学校を検索してそこへ送った。次に地域別
検索で、現在戦争や紛争が実際にある地域の学校に送った。
数多くの返事をいただいたが、特にインドの St. Marks Senior Secondary Public School とイスラエルの Ein Ganim
School、イタリアの San Filippo School からは多くのメッセージに加えて絵や写真・ポスターなども送られてきた。Ein
Ganim School で長年平和教育に貢献してこられた Marsha Goren さんは自分で運営している平和教育のホームページに
生徒の作品を載せてくださり、これまでに平和関連プロジェクトで協力してきた多くの学校に本校の生徒の平和メッセージ
を紹介してくださった。そのホームページ http://www.globaldreamers.org/09peace/ に21の学校からの大勢の生徒のメ
ッセージが紹介されている。
2 NAISの国際交流プロジェクト参加
アメリカの学校間交流を促進している全米私立学校協会NAISの Newsletter に、Andrea Mennella さんの紹介で広
島平和記念公園で配布した平和メッセージ紹介の手紙が掲載された。その手紙を読まれたNAISの国際交流プロジェク
トオーガナイザーの方から、NAISの国際交流プロジェクト”Challenge 20/20” に応募したらパートナースクールを紹介
できるので是非応募するようにとのメールをいただいた。NAIS の URL は http://www.nais.org/ 。アメリカの高校を 3 校紹
介していただいた。
B 交流相手からの紹介
また、交流相手から更に紹介されて交流が始まった学校もあった。イタリアの San Filippo School の Andrea Menella さんか
らは、アメリカのオハイオ州の国際交流に熱心な Hathaway Brown School やオーストラリアのいくつかの学校を紹介いただ
いた。Hathaway Brown School からは平和をテーマにした1.5m×3mくらいの大きな共同制作の絵(16 人の生徒が参加)
とその絵の説明のビデオメッセージが届いた。ビデオメッセージにはこちらから送った生徒作品に対するコメントもあり、生徒
の印象に残ったようだった。
こちらからもインドの St. Mark’s Senior Secondary Public School の Lakshmi Srinivas さんをイスラエルの Ein Ganim
School の Marsha さんに紹介したところ、Lakshmi さんは、その Marsha さんの紹介で知り合ったアメリカの2つの学校と自
分 の 学 校 の 生 徒 と の 共 同 制 作 で ” Save Earth” と い う 環 境 と 平 和 学 習 の ホ ー ム ペ ー ジ を 開 設 し
(http://gvc0901.gvc09.virtualclassroom.org/main.html)、その取り組みで最近 Global Virtual Classroom Award を受賞さ
れた。(http://www.virtualclassroom.org/win09.html#E_CAT) 互いにいろいろな人を紹介しあうと、交流の輪が広がっていっ
て、生徒は多種多様な文化背景を持つ人々と交流し、協働する機会が増える。
C 講演会・シンポジウム等で講師やパネリストの方に協力を依頼する
昨年 12 月に神奈川で行われた日本平和大会の国際シンポジウムに、ドイツ平和評議会のメンバーで、ボン市議会議員のハネ
ロア・トゥルケさんが参加されておられ、シンポジウム後に生徒達のメッセージを紹介させていただく機会があった。ボン市長
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 13. いきましょう。目標は庭のようなものにはしないで。人が上を踏んで歩くでしょうから。そうではなく、目標は空のようなものにして
ください。みんなが手を伸ばして触りたいと願うようなものに。
「生きることに熟練すること」を学んで、今日あなたが分担できることをしてください!
2 イスラエルの小学生からのメッセージ
イスラエルの小学生からの平和メッセージに次のようなものがあった。
1 8 年間ガザはイスラエルを爆撃
していた。8 年間の沈黙。
2 軍事行動の前の週に 1 日に80
のロケット弾がイスラエルに対
して撃たれた。
3 スデロットとイスラエル南部は
爆撃された。全ての人が防空壕
にいた。
4 政府は何かがなされなければな
らないと理解していた。
5 その何かとは Oferet Yetzuka 作戦
だった。⑥ある天気のよい土曜
の朝にイスラエルはガザを空か
ら爆撃した。⑦それからイスラ
エルの地上軍がガザに入った。
⑧その戦争は終わった。今は私
達は、平和になってガザとイスラエルが敵ではなくなることを望んでいる。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
返事のメッセージを紹介するにあたっては、紛争の当事者になっている地域の子供は、報道規制などもあり、身近な大人の話
を鵜呑みにしていることもあるせいか、自国の攻撃を正当化する意見を書くこともあるので、生徒に紹介する時に注意が必要で
ある。
全国高校生交流集会と山口県ハイスクールフォーラムでこのメッセージを生徒が分科会で紹介した時は、「大人の話や報道を
鵜呑みにしているのだろう」「相手の被害の状況をわかっているのだろうか」「最後に敵でなくなることを望んでいると言ってい
るのだからこのメッセージに悲観的になるよりも、平和を望む気持ちはやはりあるということに希望を持つ方がよいのではな
いか」といった意見が出た。また、分科会助言者から、イスラエル軍の中にもイスラエルの市民団体の中にも、軍事力による市民
の虐殺・虐待や農作物などの資産の破壊に反対する行動を起こしている人達がいることも知っておくべきという助言があった。
立場を超えて、被害者の苦しみを理解し、何の罪もない人々を巻き込む攻撃はどんな理由も正当防衛にはならないという視点
で見ないと、罪のない人々を殺された憎しみがまた新たな攻撃を生むばかりで、憎しみの悪循環に陥ってしまうのではないだろ
うか。甘い考えと思う人もあるかもしれないが、核兵器に限らず、国内に貧困に苦しむ人がいても大金をかけて作った無差別大
量殺戮の兵器による恐怖感で互いを脅しあっている不信感に基づく戦争回避状態は、本当に平和な状態とは言えないのではな
いか。脅迫よりも、もっと医療や農業、環境保護など庶民の暮らしを良くするために国際協力を進めることに人材とお金を回す
ほうが、本当に一人一人が感謝の気持ちで幸せに暮らせる世界を創ることになるのではないか。将来そうした地道な国際協力の
仕事をしたいと平和メッセージに書いている生徒がいることは大変心強いことである。
B 大人の方々からの返事
生徒同士のメッセージ交換だけでなく、様々な体験を積んでこられた大人の方々からも今の子供達へのメッセージをいただい
た。子供同士だけでなく、実際に平和のための活動に取り組んでおられる方々からのメッセージを共有することで更に平和を創る
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 14. 意識と行動の重要さが認識できるとよいと思う。メッセージを書く時に日本語の段階で、どんなことを書いていいか思いつかない
という生徒には特に、このような参考になる文章を紹介すると刺激になってよい。
1 オーストラリアの元学校司書 ルース・カルジー氏
女性のためのホームステイを通じて国際交流促進を図る団体である Women Welcome Women Worldwide のメンバー。
(この団体はイギリスに本部を置いているが世界中に多くのメンバーを抱えており、世界各地で様々な会員交流のイベント
を開いている。)またカルジー氏は児童虐待防止のNPOでも長年活動しておられた。
オーストラリアに移民してきたばかりの頃、学校の先生が第 1 次世界大戦での体験談を聞かせてくださり、もうあのような
戦争はしてはいけないと戦争の愚かさを説いてくださったが、また第 2 次世界大戦が始まって、メディアに焚き付けられ特定
の国の人間はみんな鬼と思い込み大量殺戮も躊躇しなくなるという歴史を目の当たりにしてきたという体験談を手紙で語っ
てくださった。若者が本当に歴史から学び行動することで、今度こそ平和な世の中を創ってくれると期待しているというメッ
セージを送ってくださった。
2 The Hunger Project の Japan Country Director 古谷球子氏
地元の人々の自立を助けることで飢餓を世界からなくす活動を世界的に展開しているハンガープロジェクトという団体の
日本代表をしておられるという立場から、以下のようなメッセージを送って下さった。以前ボランティア活動で、この団体の
世界大会報告書の和訳をしたご縁で依頼に応えてくださった。
ハンガープロジェクトは、地球上から飢餓をなくすという目的を持ち、アフリカ・南アジア・ラテンアメリカ等の途上国において、
人々の自立を支援する活動を推進しています。
私は、8年前にアメリカ・ヨーロッパのメンバー約20名と、アフリカ大陸のウガンダを訪れ、ハンガープロジェクトの活動に参
加している人々(パートナー)と交流しました。
空港に到着すると、多くのパートナーたちが私たちの訪問を歓迎し、アフリカ独特の演奏とダンスを披露してくれました。はじけ
るような人々の活気と笑顔!にびっくりです。
途上国においては、極端な貧困のため一日一回の食事をとることさえ難しく、食べない日もあるのです。
女性たちは地位や権利が守られていません。出産で死ぬことも多く、水汲みやマキ拾いのため毎日20 Km も歩かなければなりま
せん。家事・育児・畑仕事と休む間もなく働きます。
このような生活が半永久的に続くとあきらめていた時、ハンガープロジェクトの活動がスタートしました。
ハンガープロジェクトのワークショップに参加し、自分たちの手で飢餓をなくすことができる!ということを学び、自分たちの意識
を変える努力をし、行動に移していきます。
私たちは、小口のローン(3,000~5,000円)を借りた女性の畑に行きました。彼女は「私はローンで、この畑を借り、種
を買い、一生懸命に農作業をし、作物を収穫することができました。おかげで家族も食べられるようになり、市場で販売できたのでお
金が入り、ローンを返済することができました。こんなことができるなんて信じられません。」と目を輝かせて語ってくれました。
ハンガープロジェクトの飢餓をなくすということは、ただ食べるということだけではなく、人間としての尊厳があり、目標と希望
を持ち、生き生きと生きることです。飢餓をなくすその一歩は、ひとりひとりの人間の意識の変革から始まり、その実現のための行動
を起こすことです。
“ ” ”私に何ができるのか “今、何ができるのか を探求しつつ
ハンガープロジェクト協会 古谷 球子
3 広島大学環境平和センター所長 町田宗鳳教授
『愚者の知恵』という『イワンの馬鹿』などのトルストイの民話をいろいろ採り上げて本当に平和的に生きると
はどういうことかについて書かれた著書や、『なぜ宗教は平和を妨げるのか「正義」「大義」の名の下に』などを書かれておられ
る町田氏に平和メッセージ交換のことをご説明し、『教育は壮大な実験である~<いのち>と向き合う』という御著書の前書
きの部分を平和メッセージを送ってくれた学校に送ってもよいというご承諾をいただいた。町田氏の公式ホームページにそ
のメッセージ「<いのち>麗わし」が掲載されている。また、以前広島を訪問された、イスラエルにあるパレスチナ人とイスラ
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
- 16. に紹介し、図書便りにも掲載した。
「道徳的に何が正しいかということも大切だけど、戦争で金儲けしている人達がいるという事実をよく知ることが大事
です。戦争で金儲けするよりも、平和の方が儲かるというように経済の仕組みを変えていくことが必要ではないでし
ょうか。」
9 アメリカの平和運動団体である Fellowship of Reconciliation USA の John Lindsay-Poland 氏
日本平和大会国際シンポジウムのパネリストとして来日された折に、歓迎会で生徒の書いたメッセージをお渡しして、お返
事をお願いした。子ども達のための平和メッセージを書いておくりましょうと申し出てくださった。また、世界中の外国軍事
基地撤去に関する市民運動の成果を特集した所属団体の発行する雑誌をプレゼントしてくださった。内容を外国の学校に伝
えて良いか伺ったところ、電子メールに添付して送りやすいようにその雑誌のデジタルデータをメールで送って下さった。
10 フィリピンの平和運動家 Corazon Valdez Fabros 氏
日本平和大会シンポジウムのパネリストで何度も来日しておられる Fabros 氏にも生徒のメッセージを紹介した。フィリピン
では国民の意思で米軍基地を撤去させ、基地がなくなった後も跡地に民間企業を誘致し、基地があったときの1.5倍の雇用
を生み出したという事実を紹介して下さった。「基地の後にも生活はあります」という言葉が印象的だった。「フィリピンに来
られる機会があれば米軍基地跡地がどうなっているか案内しますよ」と申し出てくださった。
Ⅵ 生徒作品を校外のより多くの人に紹介する方法
A ホームページへの掲載
前述のイスラエルの学校の平和教育のページ http://www.globaldreamers.org/09peace/ に生徒作品を掲載していただいた
ことで、作品自体を印刷して配るよりも楽に、多くの方々に読んでいただくことができた。
B 研究紀要への発表と教育研究大会等の分科会での発表
山口県高教研英語部会の研究紀要や日高教の高校生憲法意識調査結果のまとめの冊子に実践報告を投稿した。また
日本平和大会の平和教育の分科会、山口県の教員組合主催の教育研究大会の英語教育の分科会で発表した。より多くの方に生徒
の真剣なメッセージを読んでいただくことができ、また、質問・ご意見をいただくことで、勉強になった。
C 高校生交流集会等の分科会での生徒の発表
昨年度広島で行われた全国高校生交流集会と山口県ハイスクールフォーラムで、平和メッセージに取り組んだ 3 人の生徒が
その過程と感想を発表し、他校の生徒と意見交換をした。他の学校の生徒にも「このようなメッセージ交換に取り組んでみたい」
と言ってくれた生徒がいたと発表した生徒から聞いた。発表する生徒には、準備のためによりこの交流について深く考える機会
となり、他校の生徒にも、このような国際交流の方法があることを知り、実際に送られてきたメッセージの内容に対して自分の
意見を考えてもらうよい機会となった。
D 教育関係の実践報告コンテストへの応募
外務省のグローバル教育コンテスト http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/edu/contest/2009/index.html に応募。前述の
ePals や NAIS などにも同様の実践報告のコンテストがある。入賞すればより多くの方に生徒のメッセージを読んでいただく
良い機会となるが、入賞しなくても、審査員の皆さんに読んでいただけるということはそれだけでもありがたい機会と思われる
また過去の受賞者の作品紹介を読むことで参考になる取り組みを学ぶことができた。
E 平和美術展覧会への参加
毎年 8 月に岩国市シンフォニア岩国で開かれているジュニア平和美術展覧会で、中国・韓国・イラク・アメリカなどの国の
子ども達の絵が展示されている。本校に送られてきた平和のメッセージと絵も一部展示していただけることになった。出展者は
1500~2000 人、来場者は米軍基地内の学校の生徒・保護者も含め、1 週間で約 2000 人。
本校の生徒が平和メッセージを書くときにも、クラスにより、平和のイメージの絵を描いて、その中にメッセージを書き込む
という形で取り組んだ。英語の文章を自分で書くのは苦手な生徒にも、英文を解釈して、絵ですばらしく美しい平和のイメージ
を描く生徒がいる。授業で紹介したダライ・ラマの平和についてのスピーチや、アメリカ先住民の平和の祈りや、外国から送ら
れてきた平和メッセージの中で感動したところを選んで書き込んだ。言語活動に関連して様々な才能が発揮できる機会がある
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2