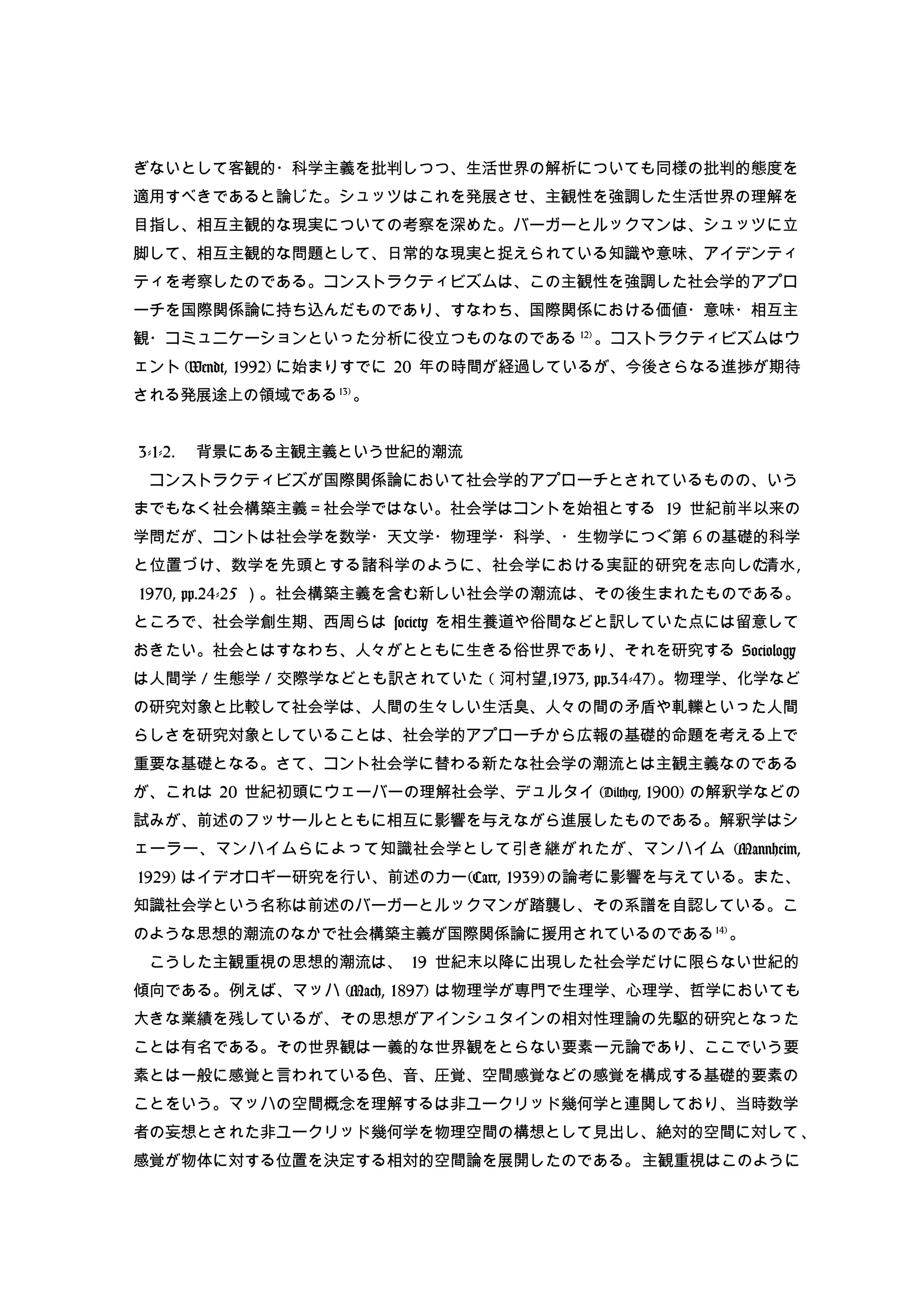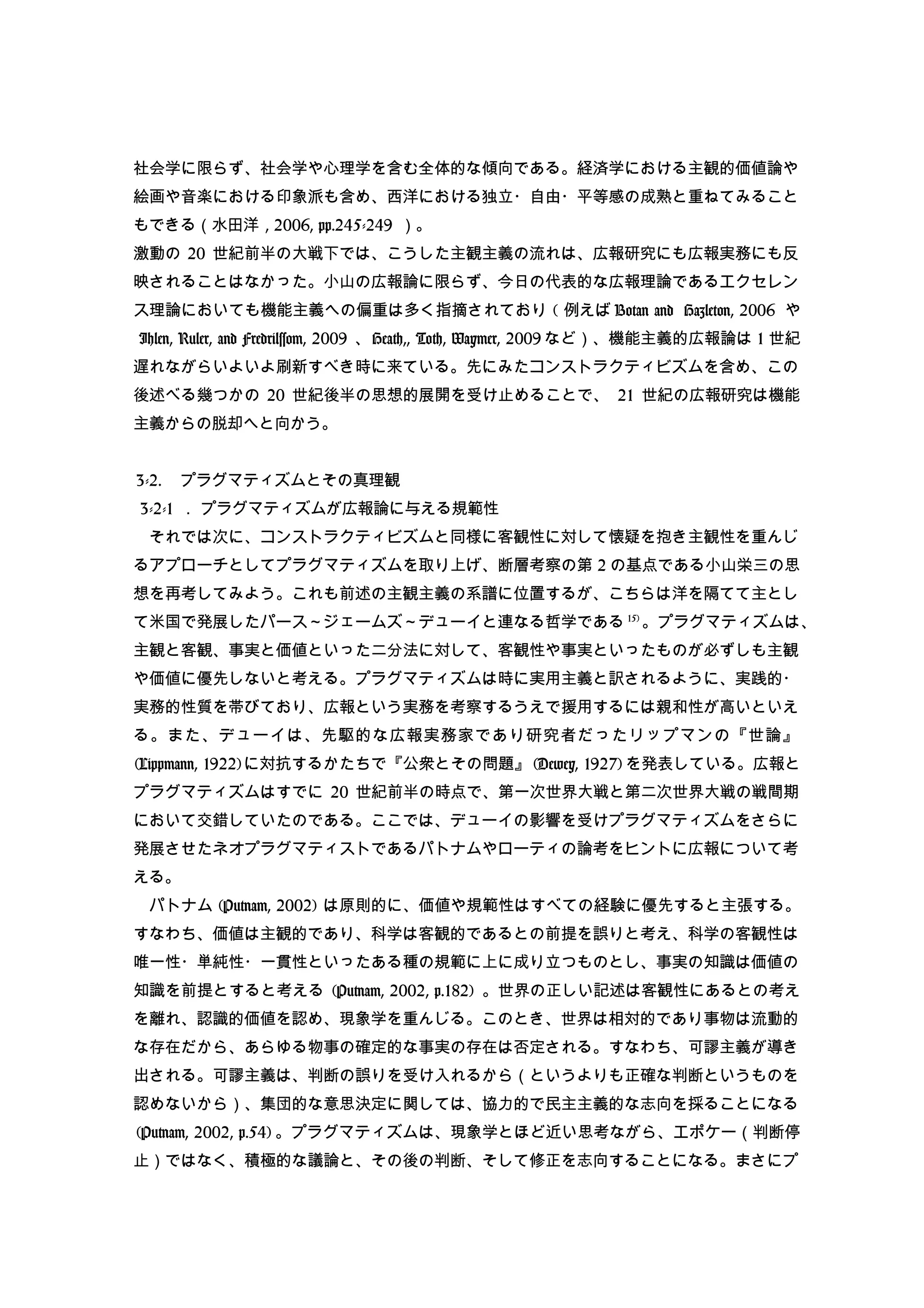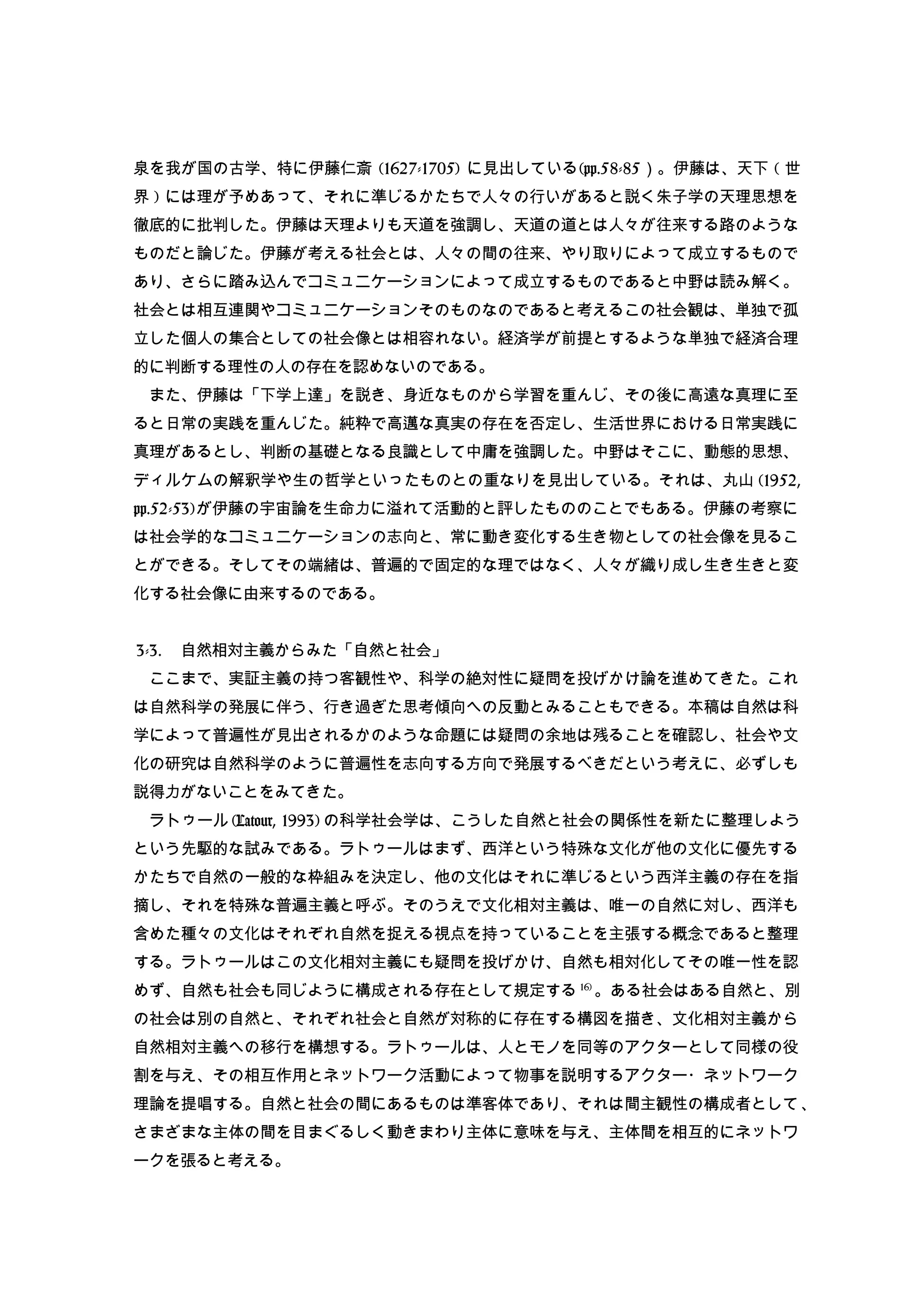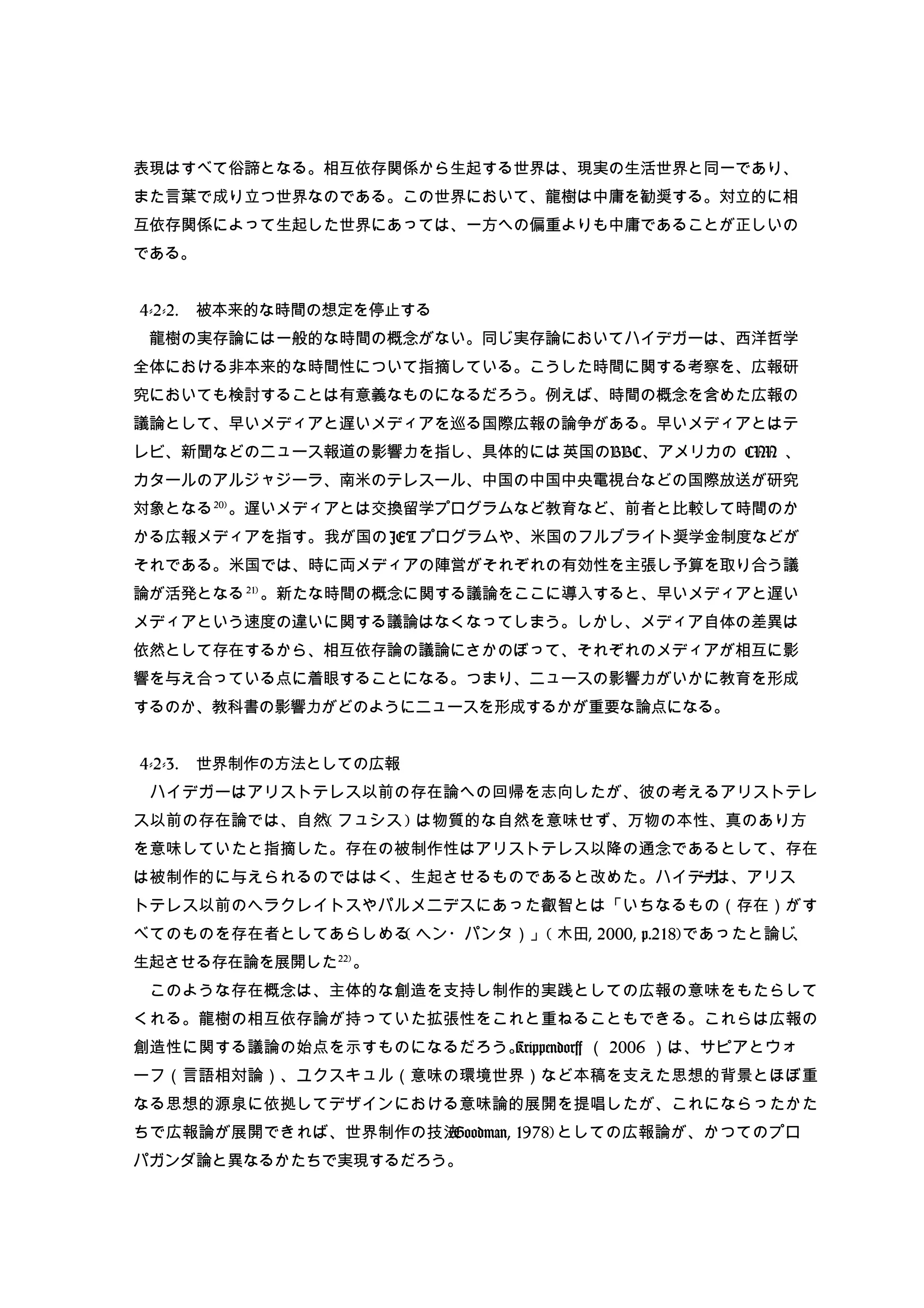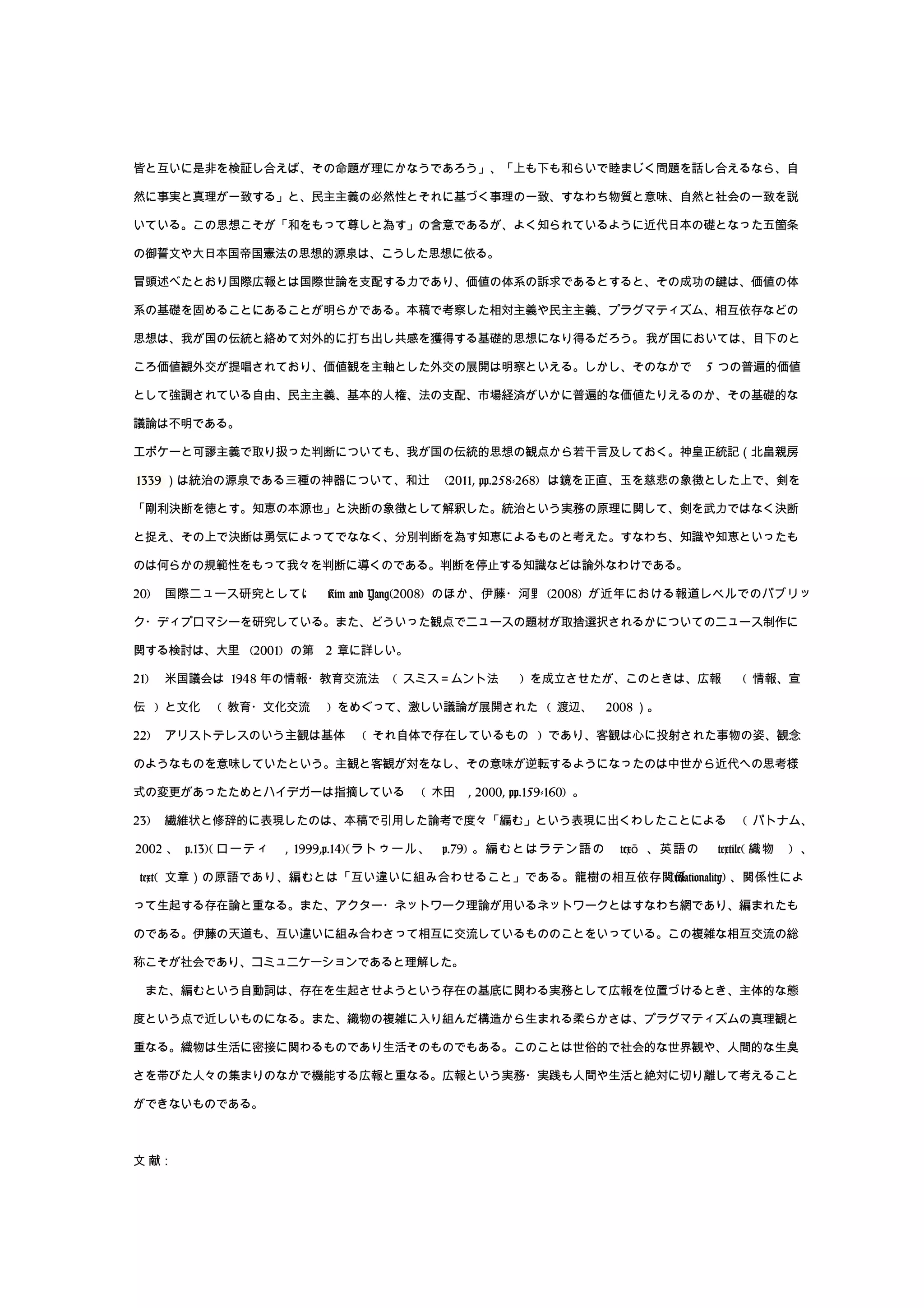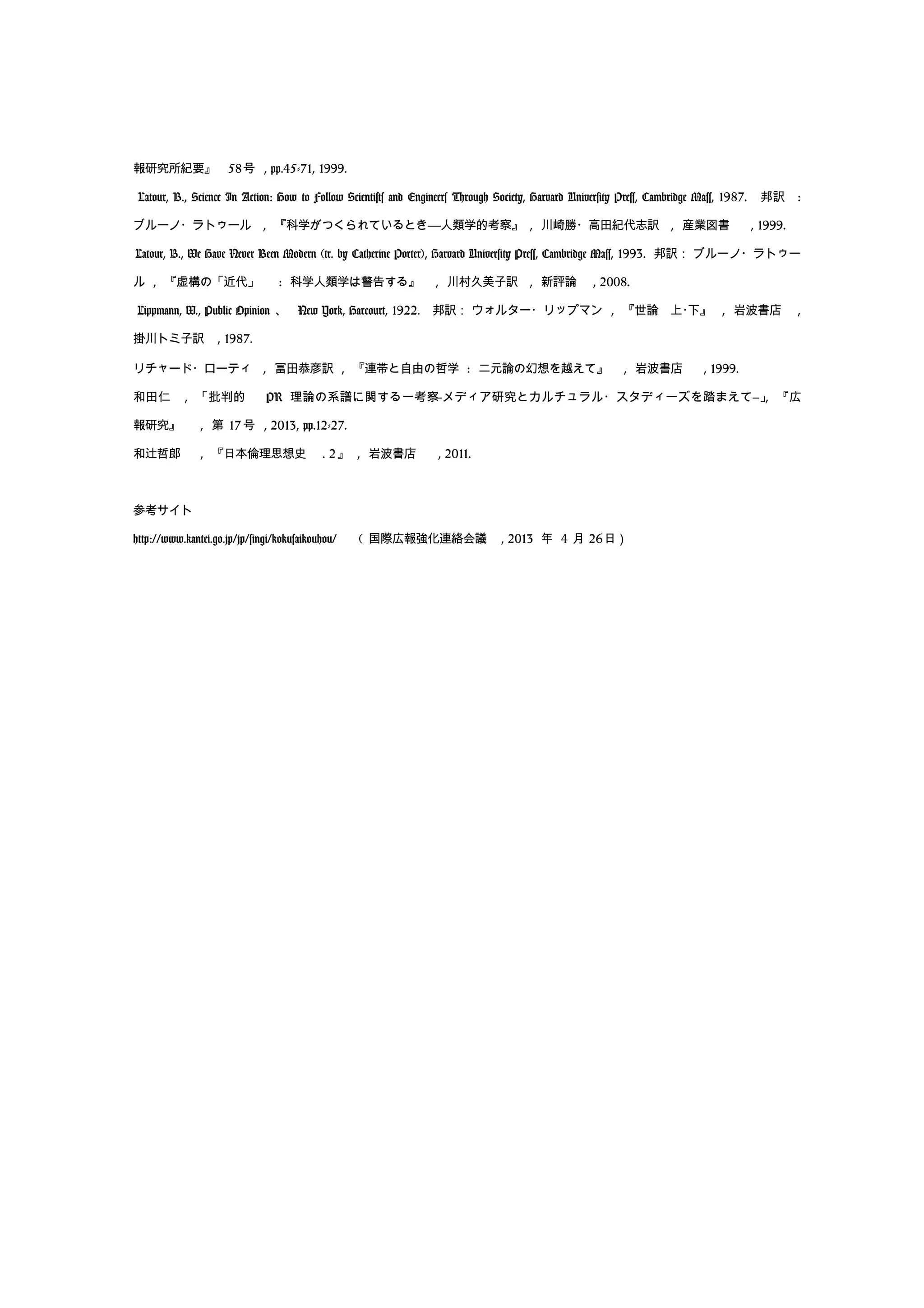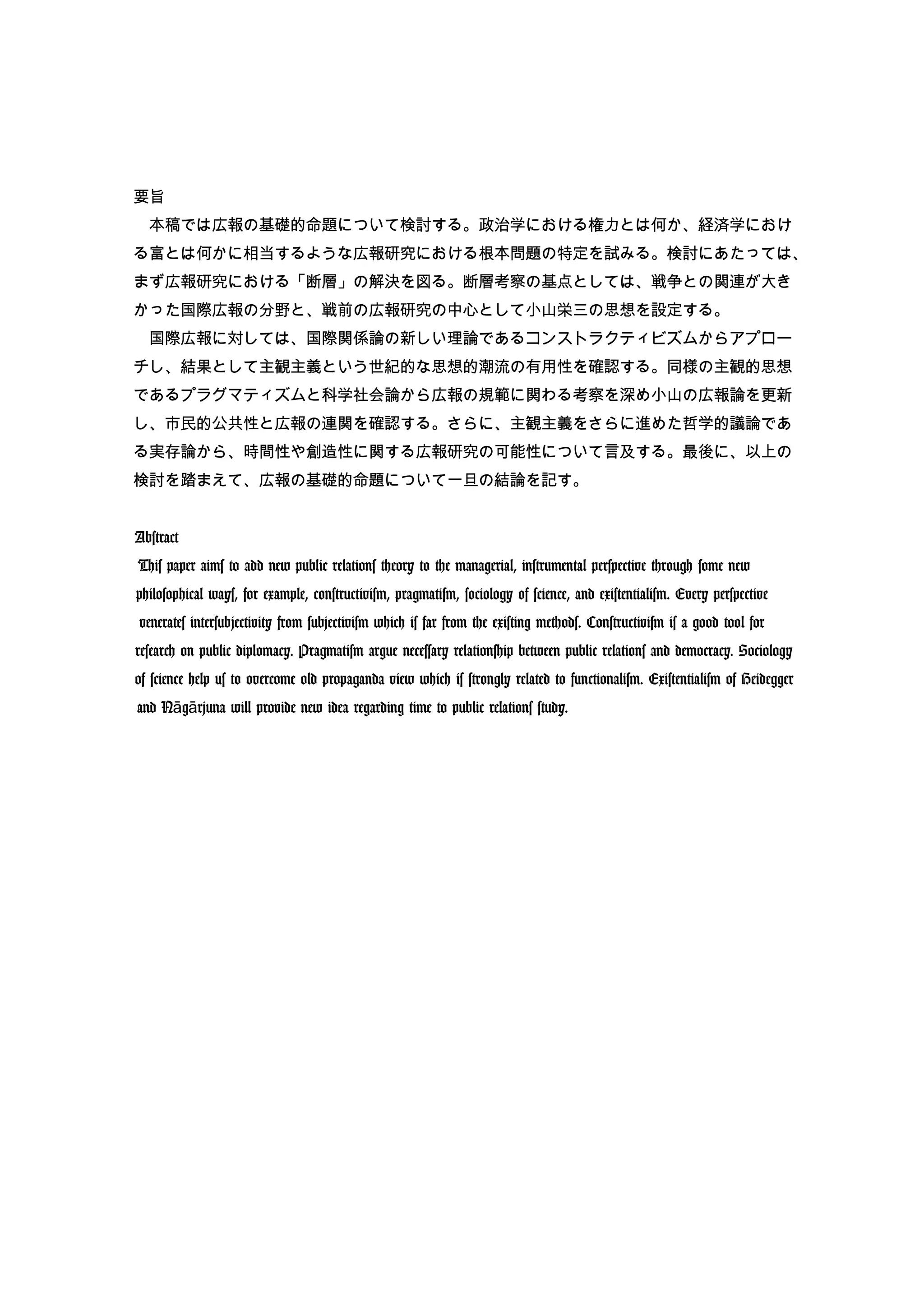本稿では広報の基礎的命題について検討する。広報の基礎的命題とは、政治学における権力とは何か、経済学における富とは何かに相当するような広報研究における根本問題の特定を試みることである1)。検討にあたっては、まず、佐藤(2000)の指摘する広報研究における「断層」の解決を図る。断層とは第二次世界大戦の敗戦を機に我が国において寸断された、戦前・戦中と戦後の広報研究の非連続性のことである。断層考察の基点として2点、戦争との関連が大きかった国際広報の分野と、戦前の広報研究の中心として小山栄三(1954)の思想を設定する。国際広報に対しては、国際関係論の新しい理論であるコンストラクティビズムからアプローチし、結果として主観主義という世紀的な思想的潮流の有用性を確認する。小山の思想については科学志向と機能主義をその特徴として指摘し、その規範論の欠如に伴う問題点を確認した上で、コンストラクディビズムと同様の主観重視の思想であるプラグマティズムと科学社会論から広報の規範に関わる考察を深め小山の広報論を更新し、市民的公共性と広報の連関を確認する。さらに、主観主義を一層哲学的に深めた議論である実存論から、時間性や創造性に関する広報研究の可能性について言及する。最後に、以上の検討を踏まえて、広報の基礎的命題について一旦の結論を記す。