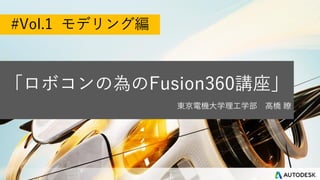
ロボコンの為のFusion360講座 vol1.モデリング編
- 2. # 目次 1 1. Fusion360とは 2. 基本操作 3. スケッチ 4. ボディ 5. アセンブリ 6. 参考文献 ※本資料は電大ヒュー研に所属していたころに作成した「ロボコンの為のFusion360講座#CAD 編」と内容は同じです.本資料では2017年での標準UIである非タブ操作で行っています.
- 3. #1.1 Fusion360とは そもそも3DCADを使うメリットは何か? →作成した3Dデータをもとに様々な応用が可能 例)CAM, CAE, 図面, レンダリング, アニメーションなど 2 問題点:これらの応用に対しそれぞれのソフトが必要だった。 Fusion(統合)しようぜ!
- 4. #1.2 Fusion360がオススメな理由 3 3DCADに手を付けられない人によくあるコメント Q1. 有料なんでしょ? →A. 学生や趣味での利用は永遠に無料です。 Q2. 機能に制限かかるんでしょ? →A. 基本的にフル機能使えます。 Q3. 操作難しくない? →A. 非常にわかりやすい操作。Officeが使えれば問題ないレベル。 Q4. 処理重くて使えなくない? →A. パーツ数にもよりますが第四世代corei5、メモリ8GB、SSD程度のスペック のノーパソで動きます。動作の軽量化も可能です。 Q5. 時代は2D(二次元)だろ! →A. そんなこと言ってるから彼女ができないんです。現実を直視してください。
- 5. #1.3 補足 作成過程の動画とサンプルデータを Autodesk Knowledge Networkで公 開しております. 不明な点がございましたら恐縮です が以下URLを参照ください. https://autode.sk/2NxWWZx 4
- 6. #2.1 画面構成 5 ① データパネル ② 作業スペース ③ ツールバー ④ ViewCube ⑤ ブラウザ ⑥ ナビゲーション ⑦ 履歴バー ① ⑤ ② ③ ④ ⑥ ⑦
- 8. #2.3 下準備 7 モデルの作成をする前に以下の二つのことを行う。 1. 動作の軽量化 →右上にあるヘルプをクリックしグラフィックスの診断を選択。現れたウィンドウの「サポートと 診断」にある「パフォーマンスを最適化するために効果を制限」という項目にチェックを入れる。 2. ファイルの保存 →Fusion360は基本的にクラウドベースのCADのためデータの保存先はサーバー(A360)となる。 フォルダなどの細かな分類は左上のデータパネルより行う。まぁこまめに保存しましょう。
- 9. #2.4 Modelingの流れ 平行リンクを以下のステップに従い作成します(所要時間45分) 8 Step1. スケッチ 立体の元となる平面図(ス ケッチ)を作成する。 Step2. ボディ化 作成したスケッチを元に 立体(ボディ)化する。 Step3. アセンブリ 作成したボディをそれぞ れ組み合わせる。
- 10. #3.1 スケッチ作成① 9 台座のスケッチ作成 1 ① ② ③ ④ ① ツールバーからスケッチ を選択 ② 長方形を選択 ③ 中心の長方形を選択 ④ X-Z平面を選択 (ViewCubeで軸を確認)
- 11. #3.2 スケッチ作成② 10 台座のスケッチ作成 2 ① 中心点を原点にあわせク リック ② 横の寸法を「20」と入力 しTabキーを押す ※③と手順が逆でも可 ③ 縦の寸法に移動「40」と 入力しTabキーを押す。単 位が確定されたことを確 認しEnerを押す ④ スケッチの停止をクリッ ク ※数値を入力せずにカーソル操作で値 を調節してもよい ① ② ③ ④
- 12. #3.3 スケッチ作成③ 11 リンクAのスケッチ作成 1 ① ② ③ ④ ① ツールバーからスケッチ を選択 ② スロットを選択 ③ 中心合わせスロットを選 択 ④ Y-Z平面を選択 (ViewCubeで軸を確認)
- 13. #3.4 スケッチ作成④ 12 リンクAのスケッチ作成 2 ① ② ① 長さの寸法を「60」と入 力Tabキーを押す ② 角度の値に「90」と入力 しTabキーを押す。単位が 確定されたことを確認し 任意の位置でクリックす る
- 14. #3.5 スケッチ作成⑤ 13 リンクAのスケッチ作成 3 ① ① カーソルを動かしスロッ トの幅の寸法に「10」と 入力しEnterキーを押す。 単位が確定されたら再度 Enterキーを押す。
- 15. #3.6 スケッチ作成⑦ 14 リンクAのスケッチ作成 4 ① ② ③ ① ツールバーからスケッチ を選択 ② 円を選択 ③ 中心と直径を指定した円 を選択
- 16. #3.7 スケッチ作成⑧ 15 リンクAのスケッチ作成 5 ① ② ③ ① 円の中心をスロットの中 心線上部末端に合わせる ② 円の直径を「3」と入力し Enterキーを押す。単位が 確定されたことを確認し 任意の位置でクリック ③ 同様にして中心線下部末 端にも直径「3」の円をス ケッチする ④ スケッチの停止をクリッ ク ※同じ操作は画面上で右クリックで呼 び出すことも可能 ④
- 17. #3.8 スケッチ作成⑦ 16 リンクBスケッチ作成 1 ① ③ ① ツールバーからスケッチ を選択 ② 線分を選択 ③ Y-Z平面を選択 (ViewCubeで軸を確認) ②
- 18. #3.9 スケッチ作成⑧ 17 リンクBスケッチ作成 2 ① ② ① グリッドに合わせ底辺を 「20」の位置でクリック ② グリッドに合わせ高さを 「10」の位置でクリック ③ 線を結び三角形を作る ③
- 19. #3.10 スケッチ作成⑨ 18 リンクBスケッチ作成 3 ① ② ① ツールバーからスケッチ を選択 ② オフセットを選択 ③ 前項で作成した三角形を 選択し「5」を入力し Enterキーを押す③
- 20. #3.11 スケッチ作成⑩ 19 リンクBスケッチ作成 4 ① ② ① ツールバーからスケッチ を選択 ② フィレットを選択 ③ 前項で作成した三角形の 斜辺と底辺を選択し「5」 を入力しEnterキーを押す ④ 同様にして斜辺と対辺を 選択し「5」を入力し Enterキーを押す ③ ④
- 21. #3.12 スケッチ作成⑪ 20 リンクBスケッチ作成 5 ① ② ① ツールバーからスケッチ を選択 ② 円を選択 ③ 中心と直径で指定した円 を選択 ④ 三角形の頂点に中心をあ わせ「3」入力しEnter キーを押す。単位が確定 されたことを確認し任意 の位置でクリック ⑤ 同様にして円を頂点にス ケッチする ⑥ スケッチの停止をクリッ ク ③ ④ ⑤ ⑥
- 22. #4.1 ボディ化① 21 台座ボディ作成 ① ② ① ツールバーから作成を選 択 ② 押し出しを選択 ③ 台座のスケッチを選択 ④ 矢印をドラッグしY軸方向 正に引っ張り「4」を入力 しEnterキーを押す ③ ④
- 23. #4.2 ボディ化② 22 リンクAボディ作成 ① ② ① ツールバーから作成を選 択 ② 押し出しを選択 ③ リンクAのスケッチを選択 ④ 矢印をドラッグしX軸方向 正に引っ張り「1.5」を入 力しEnterキーを押す ③ ④
- 24. #4.3 ボディ化③ 23 リンクBボディ作成 1 ① ② ① ツールバーから作成を選 択 ② 押し出しを選択 ③ リンクBのスケッチをすべ て選択(計6) ④ 矢印をドラッグしX軸方向 負に引っ張り「-1.5」を入 力しEnterキーを押す ③ ④
- 25. #4.4 ボディ化④ 24 リンクBボディ作成 2 ① ② ① ブラウザでスケッチをす べて表示(ランプをク リック) ② ツールバーから作成を選 択 ③ 押し出しを選択 ④ リンクBのスケッチの穴部 分のみ選択(計4) ⑤ 矢印をドラッグしX軸方向 負に引っ張り「2」を入力 しEnterキーを押す ③ ④ ⑤
- 26. #4.5 ボディ化⑤ 25 リンクAボディのコピー ① ② ① ツールバーから修正を選 択 ② 移動コピーを選択 ③ リンクAのボディを選択 ④ ウィンドウ下部の「コ ピーを作成」にチェック を入れる ⑤ Z軸方向の矢印をドラッグ し正に任意の距離を移動 させEnterキーを押す ④ ⑤ ③
- 27. #4.6 ボディ化⑥ 26 リンクBボディのコピー ① ② ① ツールバーから修正を選 択 ② 移動コピーを選択 ③ リンクBのボディを選択 ④ ウィンドウ下部のコピー を作成にチェックを入れ る ① Y軸方向の矢印をドラッグ し正に任意の距離を移動、 Z軸の回転アイコンをド ラッグし「-180」と入力 した後にEnterキーを押す ④ ③ ⑤
- 28. #5.1 アセンブリ① 27 ボディのコンポーネント化 ① ② ① ブラウザよりCtrlを押しな がらすべてのボディをク リックする ② 選択状態されたブラウザ 上で右クリックしボディ からコンポーネントを作 成を選択する ※コンポーネント(部品)化すること でそれぞれのジョイントや原点を一つ にまとめ、アセンブリ(組立)が可能 になる
- 29. #5.2 アセンブリ② 28 土台とリンクB(下)のジョイント1 ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② ジョイントを選択 ③ 視点を回転させリンクBの 底面中心をガイドに従い クリックする ① ② ③
- 30. #5.3 アセンブリ③ 29 土台とリンクB(下)のジョイント2 ① ② ① 台座の上面の中心をガイ ドに従ってクリックする ② ウィンドウ内のモーショ ンのタイプを剛性にしOK をクリックする
- 31. #5.4 アセンブリ④ 30 リンクA (後)とリンクB (下)のジョイント1 ① ② ③ ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② ジョイントを選択 ③ リンクAの穴の奥側をガイ ドに従いクリックする
- 32. #5.5 アセンブリ⑤ 31 リンクA (後)とリンクB (下)のジョイント2 ① ② ① リンクの突起部付け根を ガイドに従いクリックす る ① モーションのタイプを回 転にしOKをクリックする
- 33. #5.6 アセンブリ⑥ 32 リンクA (前)とリンクB (下)のジョイント3 ① ② ③ ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② ジョイントを選択 ③ リンクAの穴の奥側をガイ ドに従いクリックする ※アセンブリ④と同じ操作
- 34. #5.7 アセンブリ⑦ 33 リンクA (前)とリンクB (下)のジョイント4 ① ② ① リンクの突起部付け根を ガイドに従いクリックす る ② モーションのタイプを回 転にしOKをクリックする ※アセンブリ⑤と同じ操作
- 35. #5.8 アセンブリ⑧ 34 リンクA (前)とリンクB (上)のジョイント5 ① ② ③ ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② ジョイントを選択 ③ リンクの突起部付け根を ガイドに従いクリックす る ※アセンブリ⑤⑦と同じ操作
- 36. #5.9 アセンブリ⑨ 35 リンクA(後)とリンクB(上)のジョイント 6 ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② ジョイントを選択 ③ リンクAの穴の奥側をガイ ドに従いクリックする ※アセンブリ④⑥と同じ操作 ① ②
- 37. #5.10 アセンブリ⑩ 36 リンクA(前)とリンクB(上)のジョイント 7 ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② 位置固定ジョイントを選 択 ③ リンクB(上)をクリック ① ② ③
- 38. #5.11 アセンブリ⑪ 37 リンクA(前)とリンクB(上)のジョイント 8 ① リンクA(前)をクリック ② リンクA(前)の手前の穴を ガイドに従いクリック ③ モーションのタイプを回 転にしOKをクリックする ① ③②
- 40. #5.13 アセンブリ⑬ 39 台座の固定 ① ブラウザ上で台座を右ク リック ② 固定を選択 ① ②
- 41. #5.14 アセンブリ⑭ 40 接触の有効化 ① ツールバーからアセンブ リを選択 ② すべての接触を有効化を 選択 ① ②
- 42. #5.15 アセンブリ⑮(終) 41 リンクを動作させる ① 任意のリンクをドラッグ し動作させる ② 気が済んだらツールバー より位置を選択 ③ 元に戻すを選択し初期位 置に戻す ① ② ③
- 43. #6 参考文献 1. Fusion360操作ガイド スーパーアドバンス編、3Dワークス株式会社 http://www.cutt.co.jp/book/978-4-87783-390-9.html 動画とは違い自分のペースで参照しながら進められるので使いやすかったです。大学にも購入して頂いたので発展的内容や細かな操作はこの本を参考 にするといいと思います。 2. Fusion360BASE http://fusion360.3dworks.co.jp/ Fusion360に関わるコンテンツがまとめられています。前述の3Dワークス株式会社様が運営しています。困ったらこのサイトで調べれば大半のことは 解決するのではないかと。セミナー情報なども載っているのでそういったものに参加するのも一つの手だと思います。 3. Autodesk公式チュートリアル https://www.autodesk.co.jp/products/fusion-360/learn-training-tutorials 英語で説明されるのでTOEICのリスニング対策になります。 4. 誰でも見やすいパワーポイントを作るための パワーポイントバイブル https://www.slideshare.net/JunAkizaki/ss-54342283 大変勉強になりました。このスライド以外の作成でも参考にします。 42
- 44. # おまけ 43 名前:高橋 瞭 所属:東京電機大学 ライセンス: Fusion 360 Certified User 目指したい姿:行動で示す男 オススメのアニメ:風立ちぬ