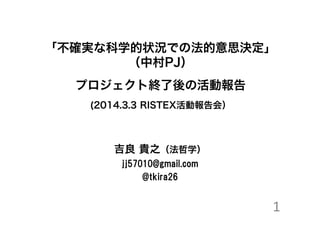2014.3.3.JST-RISTEX 活動報告会
- 2. 本報告の構成 1) 【導入】本PJ の目標、活動の紹介 2) 【本題】PJ終了後の活動報告 (1) その後の社会実装 (2) 現状認識と今後の課題 2
- 3. 本PJの目標設定 • 先端科学技術が社会にもたらす問題 → 特に 司法 の場での紛争解決 → そのために必要な「法と科学」の協働 → 各種の意識改革、制度提言へ 3
- 4. PJ終了時点での成果 • 「法と科学のハンドブック」作成(公開中) • 国際シンポジウム「科学の不定性と社会」開催 • 法律家/科学者のネットワーク構築 → 法律家と科学者の「ズレ」の原因を考察 → 固い科学観/固い法律観の克服へ → 科学的不確実性下での法的意思決定理論 4
- 5. PJ終了後の活動 (1) テレビ番組での特集 • BSフジ テレビ番組「ガリレオX」 「静粛に!法廷でぶつかる科学と法律」 2013年11月24日放映 本PJメンバーの多くが出演・協力 → 内容詳細は、配布の印刷を参照 → あわせて「法と科学の哲学カフェ」実施 → 一般層の関心の持続 5
- 7. PJ終了後の活動 (2) 継続的な研究プロジェクト • 科研費研究(基盤A)(代表:本堂毅) 「科学の多様な不定性と意思決定」 → 有志による後継プロジェクト(詳細は添付資料) → 東北大学法学研究科の研究者各氏との協働 → 本領域の他PJメンバーも参加 アカデミズムにおける「法と科学」ネットワークの 組織的構築へ 7
- 8. PJ終了後の活動 (3) 「科学と法」科目の開設 • 国内初の「科学科学科学科学とととと法法法法」科目の開講 立正大学法学部、担当:小林史明 → 鈴木利廣氏(弁護士、東京HIV訴訟弁護団事務局長) など、多彩なゲスト講師を招聘 • 詳細は添付シラバスを参照 • 今後、ロースクールなどでの開講可能性も? 8
- 10. PJ終了後の活動 (4) その他の各種の社会実装(予定含む) 弁護士会での各種活動、統計数理研究所「法と統計」研究(中村) 東京大学公開講座「人間の発展」「科学技術は制御可能か?」 太田「進歩か進化か:科学・技術・人文・社会科学に 於ける発展とは?」(2014年4月26日予定) SSHほか、各種の科学教育に関する活動(久利・村上) 「法と科学の哲学カフェ」をはじめとするアウトリーチ活動の継続 ほか、各種の書籍発行、学会発表 → STS学会でのWS開催(2013年度は3件) → 亀本編『岩波講座 現代法の動態(6) 法と科学の交錯』刊行 → シーラ・ジャサノフ『法廷に立つ科学』翻訳刊行 → 立花・JAIST修士論文(法と科学のコミュニケーション) 10
- 12. 現状認識と今後の課題 (2) 社会実装に向けて • 一足飛びの法的制度改革は困難であるため、 地道な意識改革が必要であるが…… • 参加メンバーの特性による問題 → アカデミズムの報奨システムに閉じがち → 実務家、技術者を含む人的ネットワークの構築に 向けた制度的基盤構築の必要性 → 対象のさらなるしぼり込みを 12
- 15. 参考資料 2(科研プロジェクト) 1 「科学の多様な不定性と意思決定」 科研費・基盤研究(A) (2013.4~2017.3) 研究目的 科学・技術には、その知見自身では答えや選択が決まらない不定性がある.不定性は社会 との関わりの中で多様な類型と,その類型に応じた性質を帯びて現れる.先端技術が関わ る社会的意思決定では,それゆえ不定性類型を前提とした制度設計が求められる.しかし 従来の科学論では,科学的不定性が社会との接点で顕在化させる類型と,その性質の解明 が不十分であり,社会的意思決定のための制度設計と,制度設計の前提となるべき科学リ テラシー教育双方へのボトルネックとなっている.そこで本研究は,科学的不定性の類型 化と,これを活用したリテラシー教育カリキュラム開発,そして不定性を前提とした意思 決定制度に必要な条件を明らかにすることを目的とする 研究組織 本堂 毅 (東北大学大学院理学研究科) 平田 光司(総合研究大学院大学学融合推進センター) 関根 勉 (東北大学高等教育開発推進センター) 尾内 隆之(流通経済大学法学部) 米村 滋人(東京大学大学院法学政治学研究科) 笠 潤平(香川大学教育学部) 辻内 琢也(早稲田大学人間科学学術院,在ハーバード大学) 吉澤 剛 (大阪大学大学院医学系研究科) 渡辺 千原(立命館大学法学部) 小林 傳司(大阪大学コミュニケーションデザイン・センター) 中島 貴子(政策研究大学院大学) 鈴木 舞 (東京大学大学院総合文化研究科) 水野 紀子(東北大学大学院法学研究科) 中原 太郎(東北大学大学院法学研究科,在パリ第一大学) Hon. Justice Peter McClellan (Supreme court of NSW & Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse) Prof. Andy Stirling (SPRU, University of Sussex, U.K.) Prof. Rafael Encinas de Munagorri (Universite de Nantes, France) 大石 亜依(事務局,東北大学大学院理学研究科)
- 16. 参考資料 2(科研プロジェクト) 2 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 新着情報 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 【テレビ放送のお知らせ】 BS フジの科学ドキュメンタリー番組「ガリレオ X」に,本プロジェクトメンバーの小林傳 司,渡辺千原,本堂毅が出演します. 11 月 24 日(日)11:30~12:00 「静粛に! 法廷でぶつかる科学と法律」 [BS フジ HP]http://www.bsfuji.tv/top/pub/galileox.html [番組詳細] http://web-wac.co.jp/program/galileo_x/ … 3.11 以降の科学のあり方を問う内容になるかと思います. 是非ご覧ください. 関連情報: 1)コンカレント・エビデンスのビデオ(日本語字幕版):YouTube で全編公開中 (マクレラン判事の許諾を得ています) 2)国際シンポジウム「科学の不定性と社会:いま法廷では」: 資料コーナーに当日のビデオや関連論考が多数あります. 3)法律時報 2013 年 1 月号: 国際シンポジウムの報告が掲載されています. 4)実際の法廷での誘導尋問の様子: 「法廷における科学」科学(岩波書店)2010 年 2 月号に掲載された論考 を参照ください(ダウンロード可能.岩波書店許諾). ------------------------------------------------ 2013 年 11 月 6 日 本メンバーの笠潤平さんの新刊「原子力と理科教育:次世代の科学的リテラシーのために」 (岩波ブックレット)が出版されました.定価 525 円です. ------------------------------------------------ 本プロジェクトの一環として, 2013 年度 科学技術社会論学会総会・年次学術大会の2つのワークショップで発表を行い ます.会員以外の方も参加可能です. 11 月 17 日(日) 13:30 – 15:00 A-2-3【ワークショップ】
- 17. 参考資料 2(科研プロジェクト) 3 裁かれる科学者ー科学の不定性と専門家の責任 オーガナイザー:平田 光司(総合研究大学院大学) [プログラム] 平田 光司(総合研究大学院大学) 「はじめに」 纐纈 一起(東京大学) 「ラクイラ地震裁判」 米村 滋人(東北大学) 「医療『過誤』訴訟」 ディスカッサント:藤垣 裕子(東京大学) 15:10 – 16:40 A-2-4【ワークショップ】 科学の不定性と科学教育:判断力を育む理科教育の可能性と課題 オーガナイザー:関根 勉(東北大学) [プログラム] 関根 勉(東北大学) はじめに 大木 聖子(慶應義塾大学) 科学の限界と情報発信:生き抜くための判断を育む防災教育を例に 笠 潤平(香川大学) 考え・判断する力を育む理科教育の可能性と課題:英国の理科カリキュラム改革から ディスカッサント:小川 正賢(東京理科大学) ------------------------------------------------ 9 月 25 日(書籍の発売) メンバーの尾内が(調さんと)編者を務め,尾内,笠,吉澤,中島,本堂の論考が収載さ れた書籍が,9 月 25 日に岩波書店より発売されます.詳細はまたご報告します. 7月5日(金) 東北大学大学院理学研究科で,大木聖子さんを迎えてのセミナーを開催します. 大学院講義「科学コミュニケーション」の授業を兼ねます. どなたでもご参加いただけます.
- 18. 立正大学法学部「科学と法」シラバス(小林史明) 科学と法 2011 年の原発事故を思い返せば明らかであるが「科学的なもの」が問題となる法的紛争は増加している。 そこで科学的知見と法が関わる様々な場面(民事訴訟、刑事訴訟、行政行為、立法手続)について具体例 をもとに概説し、法律家や行政職員や科学者がそれぞれ現実にどのような営みをしているのか、してきた のかを検討する。また科学と法が共に不確実性を抱えていることから生じる問題を提示する。 科学に関わる裁判が行われる様々な手続き(民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法)の仕組みを説明できる。 「科学」と「法」それぞれの領域の実態と性質を理解しそこから法的な場面で生じる問題を指摘できる。 科学的不確実性と法的不確実性の内容を説明できる。 教科書の該当箇所を読んでから授業にのぞみ、同様に復習すること。問題となるテーマは社会情勢との関 連が非常に強いので、日頃からニュース等に目を配って、科学と法、科学と行政、科学と政治に関する情 報に接すること。テーマの性質上、法や科学だけにとどまらない広い分野に触れることになるので、科学 哲学、政治、メディア、情報論などに関心のアンテナを広げておくこと。 【第1回】科学と法を学ぶにあたって 【第2回】科学をめぐる裁判 【第3回】民事訴訟と鑑定 【第4回】民事訴訟と証明 【第5回】因果関係(1)法的因果関係と自然的因果関係 【第6回】因果関係(2)統計と疫学的証明 【第7回】科学の不確実性(1) 【第8回】科学の不確実性(2) 【第9回】法の不確実性(1) 【第10回】法の不確実性(2) 【第11回】科学政策と法 【第12回】科学をめぐる行政訴訟 【第13回】法律家養成と科学者養成 【第14回】刑事訴訟と科学捜査 【第15回】まとめ レポート(60%)、授業への参加(20%)、リアクションペーパー(20%)で評価する。受講者の人数によ ってはこの割合を若干変更することがある。はっきりした答えがない問題を扱うことになるので積極的に 考えようとする姿勢が重要になる。 1,法と科学のハンドブック JST-RISTEX プロジェクト「不確実な科学的状況 での法的意思決定」 1,裁判をめぐる法と科学 中村多美子 成文堂 2013 年刊行予定 教科書『法と科学のハンドブック』は参考 URL のサイトで配布しているのでこれを用いる。数に限りがあ るがこれを印刷製本した冊子があるので授業の初回で配布する。
- 19. 1 RISTEX 中村プロジェクト活動報告(2014.03.03) 吉良 貴之 【1】 それでは中村プロジェクトの終了後の活動報告を始めます。私はメンバーの 1 人で法哲 学専攻の吉良と申します。よろしくお願いいたします。 【2】 本報告ですが、まず本プロジェクトがどういう目標で、どういった活動をしたかを簡単 にご紹介します。で、本プロジェクトは取りまとめ期間も含めまして 2013 年に終了したわ けですが、その時点での成果を踏まえた上で、その後、現在に至るまでどういった活動、 社会実装を行っているかということについて、15 分程度ということですので簡単に羅列す るような感じでご紹介します。 【3】 本プロジェクトの目標ですが、現状、さまざまな先端科学技術が社会的に問題になって いる。象徴的なものは福島第一原発の事故になりますが、他にもたとえば遺伝子組み換え 作物の安全性だとか、携帯電話電波基地局の健康影響だとか、高度に専門的で複合的な高度に専門的で複合的な高度に専門的で複合的な高度に専門的で複合的な科 学技術問題について、社会の側で意思決定意思決定意思決定意思決定が求められている。本プロジェクトはそういっ たさまざまな社会的意思決定のうち、特に司法、裁判所司法、裁判所司法、裁判所司法、裁判所に持ち込まれる法的紛争法的紛争法的紛争法的紛争に焦点を あて、そこにおいてどのようにすれば法律家と科学者の生産的な協力が可能か、それをは ばむものがあるとすれば何か、それを克服してよりよい判決をもたらすためにはどうした らよいか、といったことを考えてまいりました。そして、地道な意識改革とともに、最終 的には制度的な提言に結びつけることを目標にしてまいりました。 【4】 その成果は、「法と科学のハンドブック法と科学のハンドブック法と科学のハンドブック法と科学のハンドブック」という小冊子にまとめまして、プロジェクトの 公式サイトにアップロードしております。印刷版をかなりの部数、用意いたしまして関係 者のみなさまにはお配りしましたので、この中にもご覧くださった方もいらっしゃるので はないかと思います。そのハンドブックはどちらかといえば一般向けのものでありますが、 よりアカデミックな、あるいは法律実務家向けのイベントといたしましては、オーストラ リアで先進的な試みを行っている裁判官の方などをお呼びした国際シンポジウム「科学の科学の科学の科学の 不定性と社会不定性と社会不定性と社会不定性と社会」というものを 2012 年 8 月に開催しました。約 250 名程度の参加がありまし た。こうした成果は、法律家と科学者の間でどういう「ズレズレズレズレ」が生じているからうまくい かなくなっているのか、という問題意識から、ここに書きましたように、固い科学観・固
- 21. 3 【8】 ほか、法学教育において「法と科学法と科学法と科学法と科学」の問題を扱うのも重要でありまして、本日来てい るメンバーの小林史明さんが立正大学の法学部で「科学と法」という科目を担当されてい ます。これはおそらく、単体の科目としては日本初のものでありまして、今後、たとえば ロースクールなどで同様の科目が開講されていくならば、これまでの文系理系の溝を超え た有意義な法学教育が可能になっていくのではないかと思います。 【9】 これは授業の風景ですね。ご覧のとおり、大人気科目のようで、250 名ぐらい履修者がい るそうです。また、法学部学生だけでなく、理系学部からの受講もあったようで、そうし た相互乗り入れがもっと活発になればたいへんすばらしいことかと思います。【以下、小林 さん本人による解説を少し】 【10】 各メンバーが個別的にいろいろと活動していらっしゃいます。代表の中村さんは弁護士 会を中心に、法律実務家への実装活動を活発になさっています。ほか、こんなふうにいろ いろありますが、最後に書いている、今日いらっしゃっている立花さんの論文、法と科学 のコミュニケーションとありますが、これは本プロジェクトでの人間関係、えー、まあい ろいろとごたごたもあったわけですけれども、それを見事に学問的に昇華学問的に昇華学問的に昇華学問的に昇華された研究を完 成されたようで、今後の公刊が楽しみなところでございます。これは後でよろしければご 本人から内容補足をいただければと思います。【以下、立花さんによる解説】 【11】 で、時間も短いのでまとめに入りますが、現状認識と今後の課題です。本プロジェクト の成果物であるハンドブック、これわりと評判がいいみたいですね。ほか、さきほどご紹 介した BS フジの番組とか、その他いろいろな活動もおおむね好評なようで、これは本領 域・本プロジェクトの課題への社会的関心が、震災後数年がたったいまでも持続している ということかと思います。が、それでいいのかというと気になるところもございまして、 どうも、ものすごく関心を持っている人々がいる一方で、すっかり風化してしまっている ような、そういう二極化はどうしたものかと思っております。また、より法的なことでい いますと、たとえば最近、理研の小保方さんが開発された STAP 細胞が話題になりました が、あれも、割烹着のリケジョがどうのこうのといった報道姿勢の問題がある一方で、そ の基盤にあるところの法的問題、生臭い話で言えば特許競争とか、将来的な話でいえば今 後の応用にかかわる倫理的問題、エルシーといったことですが、そういったものへの関心 はあまり強くない。そこはまだ、掘り起こしの必要があるところかと思います。