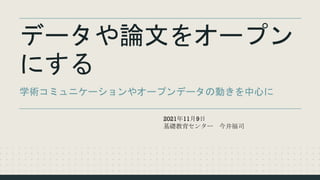
データや論文をオープンにする:学術コミュニケーションやオープンデータの動きを中心に
- 2. 1. はじめに:本講義のコメントシステム、自己紹介 2. 背景情報:本オムニバス講義のテーマに引き付けて 3. 査読をオープンにする:オープン査読 4. 論文をオープンにする:オープンアクセス 5. データをオープンにする:オープンデータ 6. まとめ 目次
- 3. はじめに
- 4. • 本講義では、授業中の質疑応答をオンラインで行います。 • システムとしてはImakikuというシステムを使用します。 • お手元のスマートフォンなどから、以下のURLでご参加下さい。 - 出席管理などに使うために氏名と学籍番号を記載してもらいますが、授業 中のコメント画面には一切表示されませんのでお気軽にお使い下さい。 • https://sugukiku.com/p/new?t=543280 本講義のコメントシステム
- 5. • 基礎教育センターで普段は司書、司書教諭の養成を担当しています。 • 専門としている学問分野は図書館情報学です。 - 科研費の区分としては、大区分A、中区分02:文学、言語学およびその関 連分野、小区分:図書館情報学および人文社会情報学関連です。 - ただし、私自身は教育学での学位を取得しているので、文学研究というよ りは社会科学系の研究アプローチを多く行っています。 - また国立国会図書館の情報誌『カレントアウェアネス』の編集企画員を担 当しており、その会議などで国内外の学術コミュニケーションに関わる情 報に触れています。 - 自己紹介
- 6. 背景情報
- 7. • 本講義のテーマ「パンデミックの言説」 • 私自身はこのテーマを聞いた時に、以下のテーマを連想しました。 - フェイクニュースとファクトチェックのせめぎ合い - “正しい”情報源とその判断(リテラシーの観点から) - 専門家vs非専門家 - 情報のアクセス可能性とオープン化 本オムニバス講義のテーマに引き付けて(1)
- 9. • 小学館ランダムハウス英和大辞典で“Open”の定義を調べる • 形容詞だけで48種類の定義がある。 - 今回の定義としては、以下の「公開」「利用できる」というニュアンスと 定義しておきたい。 - 〈場所・行事が〉公開の;〈場所・物が〉利用[入手]できる;(…に) 開放されている,(…の)参加を認めている((to ...));出入り[参加]自 由の ところでオープンとは?
- 10. • 図書館情報学の世界では次の定義が行われます。 • データ: - 既知の事項や判断材料。研究活動においては調査や実験により得られ,考 察の材料となる客観的な結果である。(中略)また,データは情報を生み 出す材料と見なされることがあり,評価の加えられたデータを情報と定義 し,データ。情報,知識という階層関係を強調する立場がある。 ところでデータとは?(1)
- 11. • 図書館情報学の世界では次の定義が行われます。 • 情報: - 送り手と受け手の存在を想定したときに,送り手から チャネルやメディアを通じて受け手に伝えられるパタ ーン。図書館情報学では,ブルックス(Bertram Claude Brookes 1910--1991)による「受け手の知識 の構造に変化を与えるもの」という定義が広く知られ ている。(中略)日常的な用法では,知識が蓄積であ るのに対し,情報は流れと見なされる傾向がある。 ところでデータとは?(2)
- 12. • 図書館情報学の世界では次の定義が行われます。 • 知識: - 経験や教育によって得られ,判断の際の基準となるもの。哲 学における認識論とは異なり,図書館情報学では,メディア を通じて蓄積,伝達される。(中略)情報との関連に関して ,一般化や形式化の進んだ情報,構造が複雑な情報を知識と 見なしたり,流れるのが情報で蓄積されるのが知識とするな どの考え方がある。一方では,知識と情報を同一視したり, 認知機構の内部か外部かで区別する場合もある。 ところでデータとは?(3)
- 14. • 学術研究成果を誰もが無料でオンラインで利用できるようにすること、 またその理念。商業出版社による学術雑誌の寡占化、価格の高騰化な どによって引き起こされたシリアルズ・クライシスのなかで、研究成 果を広く公開したい、あるいは公開するべきといった考え方から生ま れた。 • 2002年に設立されたブダペスト宣言(BOAI: Budapest Open Access Initiative)では、オープンアクセスの方法として、セルフアーカイビ ングとオープンアクセス雑誌の二つが示された。 オープンアクセスの定義(図書館情報学用語辞典より)
- 18. • arXiv - https://arxiv.org/ - 物理学、数学、計算機科学、計量生物学、統計学、電子工学・システム科 学、経済学、プレプリントを含む様々な論文が保存・公開されている • EdArXiv - https://edarxiv.org/ - 非営利団体Center for Open Science(COS)は、教育学分野のプレプリ ントサービス プレプリントサーバーの例
- 20. 査読制度とは • 学術雑誌に投稿された論文の内容を査読者(referee)が審査し,当 該雑誌に掲載するか否かを判定する制度.レフェリー制度,審査制と もいう.この制度によって,投稿論文と著者は専門的承認を受け,一 方学術雑誌は質を維持することができる. • 査読は,雑誌の編集委員や投稿論文の内容に詳しい専門家に依頼する .審査を公正に行うために,論文の著者と査読者の両者に互いの氏名 を知らせず,投稿論文を審査し,それに応じた書き直しを求める場合 が多い.(日本図書館情報学会用語辞典編集委員会(編). 『図書館情報 学用語辞典』 第4版, 丸善出版, 2013)
- 21. • 『日本図書館情報学会誌』掲載原稿および審査に関するルール • 送付された投稿原稿は,投稿規程および執筆要綱に合っているか,また, 投稿者(共同執筆の場合は,第一著者)が会員であることなど,要件を満 たすかどうかを,編集委員長と,必要に応じて編集補佐担当専従が点検す る(略)点検の結果,問題がないと判断した投稿原稿は受け付けられる。 • 学会誌で取り扱う 7 種類の投稿区分のうち,論文・研究ノ一トについては ,本委員会 が査読者を選んで査読を依頼する。 • 査読者は,研究の意義,研究上の手続き,構成や表現の点について,査読 を行う。ま た,原稿の取り扱いに関する判定を行う。 https://jslis.jp/wp-content/uploads/2021/01/rule20210401.pdf 査読ルールの例(1)
- 22. • 『日本図書館情報学会誌』掲載原稿および審査に関するルール 査読者は,原稿の取り扱いに関する判定に際して、次の 5 つの中から、最 も適切なものを選択する。 • A判定:このまま掲載可 B判定:掲載可。ただし,別記の点につき修正,加筆を求む C判定:別記の点につき書き直しを求めて再審査 D判定:掲載不可 E判定:判定不能 • 査読者は,B判定を選択した場合は掲載の条件を,C判定を選択した場合 は書き直し を求める点を,D判定およびE判定を選択した場合は判定理 由を記入する。 査読ルールの例(2)
- 23. 査読ルールの例(3)
- 24. • 以下、佐藤翔の記事を参考に説明を行う。 - 佐藤翔. オープン査読の動向:背景、範囲、その是非. カレントアウェアネ ス. 2021, (348), CA2001, p. 20-25 https://current.ndl.go.jp/ca2001 オープン査読とは
- 25. • 広島大学の解説( https://www.hiroshima- u.ac.jp/wrc/resource/predatory) • 「ハゲタカジャーナル(predatory journal)」とは、著者が論文投 稿料(APC=Article Processing Charge)を支払い、だれでも自由に 論文を読むことができる、いわゆる「オープンアクセスジャーナル」 のビジネスモデルを悪用した雑誌です。ハゲタカジャーナルは、学術 雑誌の重要な機能である査読をほとんど、あるいは全く行わないため、 投稿された論文の質は保証されません。それにより、たとえ自分が質 の高い論文を投稿しても、ハゲタカジャーナルへの掲載であるという だけで正当に評価されない可能性があります。 ハゲタカジャーナルとは?
- 26. • 査読にかかる時間・コストの増大 - 査読の引き受け手が少ない、採否判断に関わる時間の増大 • 「質のフィルター」としての機能不全 - 有効性、信頼性、公正性に関わる一貫性が担保しづらい • 査読における不正行為 - ライバルの論文をわざと却下したり、アイディアを盗用する - 著者自身が査読者となるような不正 - 査読を行っていないのに行っているふりをする雑誌側の不正 既存の査読の問題点
- 27. 1. アイデンティティの公開(Open identities) 2. 査読レポートの公開(Open reports) 3. オープンな参加(Open participation) 4. オープンなやり取り(Open interaction) 5. 査読前原稿の公開(Open pre-review manuscripts) 6. 最終版へのコメント機能(Open final-version commenting) 7. オープンなプラットフォーム(非連結レビュー)(Open platforms (“decoupled review”)) ロス・ヘラーによるオープン査読の整理
- 28. 1. アイデンティティの公開(Open identities) 2. 査読レポートの公開(Open reports) 3. オープンな参加(Open participation) 4. オープンなやり取り(Open interaction) 5. 査読前原稿の公開(Open pre-review manuscripts) 6. 最終版へのコメント機能(Open final-version commenting) 7. オープンなプラットフォーム(非連結レビュー)(Open platforms (“decoupled review”)) ロス・ヘラーによるオープン査読の整理
- 31. • あらゆる人が自由に閲覧し、利用し、修正し、そして共有できること を知識/knowledge がオープンであるとする。その際に掛けられる制 限は、出自情報やオープンさの保持を考慮する程度に留められる。 - Open Knowledge Foundation. “オープンの定義” http://opendefinition.org/od/2.1/ja/ 最終アクセス日:2019年7月8日 オープンデータの定義
- 32. • オープンデータは字義通りに解釈すれば「データの公開」にすぎないが、 より詳細には「ウェブ上での再利用性の高いデータの公開」と定義できる。 再利用性には制度と技術の2つの観点がある。制度面での再利用性とは、 データの2次利用や再配布に制約が設けられていないことを指す。 • 英国Open Knowledge Foundation(OKFN)は、商用・非商用を問わず 誰もが利用・再利用・再配布できることがオープンの定義であり、その他 の制約としてはクレジットの明記と再配布に対して同様の利用条件を課す ことのみが可能であるとしている。技術面では、公開されたデータがコン ピュータで容易に取り扱えることが重要である。 • 大向一輝. オープンデータと図書館. カレントアウェアネス. 2014, (320), CA1825, p. 14-16. http://current.ndl.go.jp/ca1825 オープンデータにおけるオープンの定義
- 33. • 活用事例のリンク集 - https://sorabatake.jp/14930/ • データシティ鯖江ポータルサイト - https://data.city.sabae.lg.jp/ - 福井県鯖江市が公開しているサイト。LODに適応しているオープンデータが多 く公開され、ライセンスも明確である。ただしアプリの更新状況は古い。 • 東京都オープンデータカタログサイト - https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/ - 東京都が公開しているオープンデータが一覧できる。 - ただしPDFなどLinkしにくいものも含まれている。 オープンデータ公開の例
- 34. • 国立国会図書館による説明 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/lod.html • LODとは、ウェブ上でデータを公開し共有するための方法で、さまざまな データ同士を結び付けて(Linked Data)、誰でも自由に利用できるよう 公開されている(オープンライセンス)ものです。ウェブの創始者である ティム・バーナーズ=リーによると、Linked Dataには次のような4つの原 則があります。 - 事物の名前としてURIを用いること - これらの名前を参照できるように、HTTP URIを用いること - URIを参照したときに、RDFやSPARQLのような標準技術を用いて、有用な情報 を提供できるようにすること - さらに多くの事物を発見できるように、他のURIへのリンクを含むこと Linked Open Dataとは?
- 35. • Wikidataは「データ版のWikipedia」とも言われ、現在ではWikipediaの 管理を行っているWikimedia Foundationが管理している。アカウントを 作れば誰でも編集に参加できる。 • Wikidataは1)オープンなライセンスで提供され、2)インターネットを 通じて自由にアクセスでき、3)機械可読であり、4)オープンなフォー マットが使われている「オープンデータ」の一種である。オープンデータ を活用することで、公開された情報を再利用することが容易になるため、 行政の情報公開制度と重なって、様々な取り組みが各地で行われている。 • 特に、機械可読なだけで無く、他のデータにリンクするLOD(Linked Open Data)の性質を持っていることから、Wikidataは理想的なオープン データである。 Wikidataとは?
- 36. まとめ
- 38. • アクセス可能性の観点から - オープンになることで科学者以外のコミュニティから参照する事が可能に なった - クローズな時よりも自分の論文の参照可能性が上がる - 限られた時間で多くの文献に触れることができる • 質の担保の観点から - 多くの人の目に触れることで、偽の情報が淘汰されていく オープンになって良いこと
- 39. • アクセス可能性の観点から - オープンでなければ参照されない、存在しないと見なされる恐れ - 出版される論文数が増大し、重要な研究を見つけにくくなる恐れがある。 • 質の担保の観点から - 公開されている論文が玉石混淆になってしまう状態 - 偽の情報が多く出回り、繰り返し主張されてしまう恐れ - プレプリントなどは査読が完了していない状況である • 専門家をどう確保するか? - ある程度高度な分野は、素人では判断できず専門家の存在が必要であるが、専 門家はいつもボランタリーで助けてくれるわけではない。 オープンになったことで考えなければいけなくなったこと
- 40. • 様々な問題があるが、アクセス可能性の観点からはメリットが多い。 - 若手の研究者が求職する際には、メリットが多い(ただし、文系の研究者 ほどオープンにしない傾向がある。)。 - 誰も使わなかった資料を何十年後かに発掘して使うという物語にはロマン があるが、誰も使わない、使えない資料や文献は将来的には廃棄される危 険性がある。 • フェイクや不正を行おうとする人にとっては有効な手段になってしま う恐れがある。 - オープンにすることは決して特効薬ではない。 - 質の担保された情報資源は依然として必要である。 オープンにすることは「良い」ことなのか?
