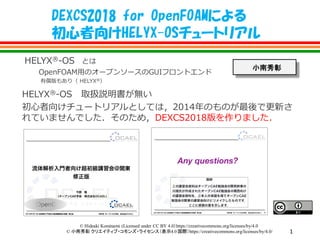More Related Content Similar to Helyx os dexcs2018
Similar to Helyx os dexcs2018 (8) 1. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DEXCS2018 for OpenFOAMによる
初心者向けHELYX-OSチュートリアル
1
HELYX®-OS 取扱説明書が無い
初心者向けチュートリアルとしては,2014年のものが最後で更新さ
れていませんでした.そのため,DEXCS2018版を作りました.
小南秀彰
HELYX®-OS とは
OpenFOAM用のオープンソースのGUIフロントエンド
有償版もあり( HELYX®)
2. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
目次
• DEXCS2018 for OpenFOAMとは?
• 例題:バックステップ流れとは?
• FreeCADによるモデルの作成
• HELYX®-OSによる
メッシュの作成・条件設定・計算実行
• ParaViewによるポスト処理
2
3. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DEXCS2018 for OpenFOAM 起動画面
3
VirtualBOX上にインストールした場合は
2つのアイコンが表示される
各種のツールが左側に並んでいる.
アイコンの左クリック→ツールが起動
隠れているものが表示される
4. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DEXCS2018 for OpenFOAM 起動画面
4
FireFox(ウェブブラウザー)
ファイル(ファイルブラウザー)
ヘルプ
端末(コマンド入力コンソール)
Emacs(テキストエディター)
Ubuntuソフトウェア
DEXCSランチャー
TreeFOAM
Paraview(可視化ソフト)
FreeCAD(3D-CADソフト)
HELYX-OS
OpenFOAMTerminal
5. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
CFDの一連の操作の流れにそって
各種のツールを起動して作業を簡単
に行うためのGUI画面を提供するツー
ルが3種類ある.それぞれから呼び出
すことのできるツールを示す
DEXCSのツールの関係
5
DEXCSランチャー TreeFoam
Paraview(可視化ソフト)
FreeCAD(3D-CADソフト)
HELYX®-
OS
OpenFOAM(ソルバー)
各種のメッシュ生成ソフト
入門者向け
標準設定:非圧縮性流体のみ
非圧縮性以外の設定ができる
圧縮性・熱流体・超音速・混僧流・反応流など
操作性/操作方法の違い
CADデータの
取り込み
以下の
資料での
操作の流れ
灰色の矢印は
各々のGUIツールが
想定している
作業フロー
6. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
FreeCADとは
6
・3D汎用CAD
・フィーチャーベース・パラメトリック・モデラー
・オープンソース(GPL&LGPL)
・マルチプラットフォーム
(Windows,Mac,Linux)
https://www.freecadweb.org
日本語を選ぶと
メニューやマニュアル類
の和約が表示される
7. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
目次
• DEXCS2018 for OpenFOAMとは?
• 例題:バックステップ流れとは?
• FreeCADによるモデルの作成
• HELYX®-OSによる
メッシュの作成・条件設定・計算実行
• ParaViewによるポスト処理
7
8. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
今回は形状が単純で,笠木らによる実測のデータがWEBで公開されている以下
のバックステップ流れを演習する
例題:バックステップ流れとは
8
[1] Nobuhide Kasagi, Akio Matsunaga: Three-dimensional particle-tracking velocimetry measurement of turbulence statistics and energy
budget in a backward-facing step flow, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol.16, No.6, pp.477-485, 1995
[2] 3-D PTV Database of Turbulent Flows http://www.thtlab.t.u-tokyo.ac.jp/PTV/ptv_database.html
流路中に段差(backward facing step)があり,再循環領域の渦を伴なう複雑な流
れであることから,乱流モデルのベンチマークとして多用される
OpenFOAMのチュートリアルにPitzとDailyによる実測(1981)のケースがある
出口:p=0 Pa
入口:Ux=10.0 m/s
x
y
9. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
目次
• DEXCS2018 for OpenFOAMとは?
• 例題:バックステップ流れとは?
• FreeCADによるモデルの作成
• HELYX®-OSによる
メッシュの作成・条件設定・計算実行
• ParaViewによるポスト処理
9
10. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
TreeFoam起動→FreeCADでの形状作成
10
① 左クリック
する
TreeFoam起動
TreeFoamはOpenFOAMのファイルを管理,モデル作成,
条件定義,計算実行およびポスト処理を統合的に扱える
GUIです.
11. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
新規作業フォルダーの作成
11
① 右クリック
する
作業フォルダーを
作成したい
ディレクトリー
(Desktop)を
左クリックで
選んで
② 左クリック
する
「新しいフォルダーを追加」を
③ 名前を入力する
作業フォルダーの
④ 「OK」を左クリック
ここでは「BackStep」とする
12. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
作業フォルダーの選択
12
①
作業フォルダーを
左クリックして選ぶ
② 左クリックする
作業フォルダーになる
とチェックマークが表示
される
作業フォルダーはTreeFoamから起動されるアプリ
ケーションの入出力先となるため,必ず設定する必
要がある
13. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
FreeCADの起動
13
① 左クリックする
(FreeCAD起動)
DEXCS版の場合はFreeCADが起動するようになっている.
(別のCADに割り当てることも可能です)
14. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
モジュールの選択
14
② 「Part」を選ぶ
① 左クリックする
モジュールの選択メニュー
起動直後は「Start」
15. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
モデルの新規作成
15
① メニューバーの「ファイル」を左クリック
新しい 空の図面 ができます
② 「新規」を左クリック
16. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ナビゲーションスタイルの設定
16
① ビュー画面で右クリック
② 「ナビゲーションスタイル」を左クリック
デフォルトの「OpenInventor」でよいでしょう
17. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ナビゲーションスタイル操作方法
17
① メニューバーの「編集」を左クリック
② 「設定」を左クリック
18. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ナビゲーションスタイル操作方法
18
① 「表示」を
左クリックする
② 「OpenInventor」
を確認する
③ 「マウス」
を左クリックする
⑤ 「OK」を左クリックする
④ マウスの操作方法を
確認したら「Close」を
左クリックする
19. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Boxの作成
19
① 左クリック
する
「立方体のソリッ
ドを作成」を
② 左クリック
して選ぶ
あたらしくできた
「立方体」を
③ 選択したオブジェクトが緑色に
なるのを確認する
④ 左クリック
する
「データ」タブを
「立方体」のプロパ
ティが表示される
20. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Boxの寸法変更
20
① 寸法を
変更する
Length 30 mm
Width 3 mm
Height 2 mm
② 寸法が変更されたのを確認する
21. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2つ目のBoxの作成
21
① 左クリック
する
② 左クリック
して選ぶ
あたらしくできた
「立方体001」を
③ 寸法を
変更する
Length 2 mm
Width 1 mm
Height 2 mm
22. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
切り欠き(立体の引き算)
22
① 左クリックする
「選択された二つの図形の
ブーリアン演算を実行」を
「立方体」から「立方体001」の部分を切り欠きたい
「立方体」から「立方体001」を引き算したい
つまり
23. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
切り欠き(立体の引き算)
23
④ 「Apply」を左クリックする
② 「立方体」を選択する
① 「差集合」を選択する
③ 「立方体001」を選択する
2番目の図形
1番目の図形
24. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
切り欠き(立体の引き算)
24
② 「Close」を左クリックする
① 形を確認する
成功していれば図
のような形になる
25. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
立体の引き算の結果
25
もとの「立方体」と「立方体001」は非
表示になっている
「Cut」が切り欠いたあとの立体です
26. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
面への分解
26
① 左クリック
して選ぶ
あたらしくできた
「Cut」を
② 左クリックする
「・・・分解,・・・減算」を
③ 左クリック
して選ぶ
あたらしくできた
「Solid」を
④ ふたたび を左クリックする
27. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
面への分解
27
8個の面に分解された
流入部 流出部
面を選択すると緑色になる
・流入部は「Face」
・流出部は「Face006」
28. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流入面の形状ファイルへの出力
28
① 流入部の
面を選ぶ
② メニューバー「ファイル」を
左クリック
③ 「エクスポート」
29. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流入面の形状ファイルへの出力
29
④ 「Save」
左クリック
② ファイル形式を
「STL_Mesh」
にする ③ ファイル名を
「inlet.ast」にする
FreeCADではASCII形式のSTL
ファイルの拡張子がastです.
① 保存先のフォルダーを
TreeFOAMの作業フォルダーにする
30. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流出面の形状ファイルへの出力
30
① 流出部の
面を選ぶ
② メニューバー「ファイル」を
左クリック
③ 「エクスポート」
31. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流出面の形状ファイルへの出力
31
④ 「Save」
左クリック
① 保存先のフォルダーを
TreeFOAMの作業フォルダーにする
③ ファイル名を
「outlet.ast」にする
FreeCADではASCII形式のSTL
ファイルの拡張子がastです.
② ファイル形式を
「STL_Mesh」
にする
32. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
壁面の形状ファイルへの出力
32
①
流入部と
流出部の
残りの面を
全て選ぶ
「Face001」を左クリックして,Shiftキーを
押しながら「Face005」を左クリックする.
Ctlキーを押しながら「Face007」を左ク
リックする
② メニューバー「ファイル」を
左クリック
③ 「エクスポート」
33. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
壁面の形状ファイルへの出力
33
④ 「Save」
左クリック
③ ファイル名を
「walls.ast」にする
FreeCADではASCII形式のSTL
ファイルの拡張子がastです.
② ファイル形式を
「STL_Mesh」
にする
① 保存先のフォルダーを
TreeFOAMの作業フォルダーにする
34. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
FreeCADファイルの保存と終了
34
② 「名前をつけて保存」
を選ぶ
① メニューバー「ファイル」を
左クリック
35. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
FreeCADファイルの保存と終了
35
④ 「Save」
左クリック
③ ファイル名を
「backstep」にする
ファイル名は任意で良い
拡張子の指定は不要です
② ファイル形式は
「FCStd」
になっている
① 保存先のフォルダーを
TreeFOAMの作業フォルダーにする
36. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
FreeCADファイルの保存と終了
36
② 「終了」
または
右上の×印を左クリックする
① メニューバー「ファイル」を
左クリック
37. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの拡張子変更
37
TreeFoamとOpenFOAMでは
ASCII形式のSTLファイルの拡張子はstlです.
② 「inlet.ast」を
右クリックする
③ ファイル名を
「inlet.stl」に変更する
④ 同様に「outlet.ast」を「outlet.stl」に
「walls.ast」を「walls.stl」に変更する
① 作業フォルダーを
左ダブルクリックする
38. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
目次
• DEXCS2018 for OpenFOAMとは?
• 例題:バックステップ流れとは?
• FreeCADによるモデルの作成
• HELYX®-OSによる
メッシュの作成・条件設定・計算実行
• ParaViewによるポスト処理
38
39. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSの起動
39
①
HelyxOSボタンを
押す
(TreeFoamの
HelyxOSボタンで
ない)
② 「New」を左クリック
③ 「newCase」を入力
(名前は任意で可)
④ Parent Folder を
作業フォルダーにする.
⑤ 「OK」を左クリック
場合によっては
こちら
並列計算用
の設定
④ Parallelの
チェックを外す
40. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
TreeFoam作業フォルダの変更
40
TreeFoamのフォルダーが
後ろに隠れている場合があります
② 作業フォルダーの下に先ほどのケース名の
フォルダーができている.
そのフォルダーを選択する
③ このボタンを
左クリックして
解析フォルダーに
設定する
TreeFoam
HelyxOS
マウスカーソルを
移動させると
アプリケーションソフトの名
前が
ポップアップ表示される
隠れているものを表示させる
① 更新ボタンを
左クリック
41. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSの画面操作
41
42. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの特徴辺の抽出
42
① TreeFoamの
HelyxOSのアイコンを
左クリック
② 「参照」を左クリック
43. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの特徴辺の抽出
43
① STLファイルを
保存したフォルダを選ぶ
② 「決定」を左クリック
44. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの特徴辺の抽出
44
① 「stlチェック」を左クリック
「stlファイルの編集」画面が表示されれば,stl
ファイルは正常です.
※ 異常なファイルが混じっていると
この画面が表示されません
② 「閉じる」を左クリック
45. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの特徴辺の抽出
45
① 「Dict編集」を
左クリック
③ 「OK」を左クリック
② stlファイルを選ぶ
④ 「OK」を左クリック
「特徴辺抽出用設定ファイル
surfaceFeatureExtractDictが生成され
たことを確認したら
46. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの特徴辺の抽出
46
×印のアイコンで
エディターを閉じる
geditエディタで
特徴辺抽出用設定ファイル
surfaceFeatureExtractDict
が開かれるが,変更は不要なので
47. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの特徴辺の抽出
47
① 「Dict実行」を
左クリック
③ 「OK」を左クリック
特徴辺(特徴線)の抽出を確認したら
② 「OK」を左クリック
特徴辺(特徴線)の抽出をするので
48. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの読み込み
48
① 「HelyxOS」を
操作対象に
選ぶ
② 「Geometry」を選ぶ
③ 「STL」を選ぶ
④ STLファイルを保存した
フォルダーにする
⑤ stlファイルを選ぶ
⑥ 「Open」を左クリック
49. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
形状ファイルの読み込み
49
① 「Lines」を選ぶ ② 「Open」を左クリック
③ STLファイルを保存した
フォルダーにする
④ eMeshファイルを選ぶ
⑤ 「Open」を左クリック
50. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ベースメッシュと分割数の設定
50
① 「Base Mesh」を選ぶ ② 「User Defined」を選ぶ
③ 入力する
ベースメッシュは形状ファイル(X:0-30, Y:0-3, Z:0-2)を包
含している必要がある.分割幅をX:0.6,Y,Z:0.2として,そ
の分,座標と分割数を調整する
51. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
内部点(Material Point)の設定
51
② 「Material Point」を選ぶ
表示モードを
「Boundary Edge」
にすると見やすい
内部点はベースメッシュの界面や辺上にあって
はいけないため,形状ファイルの領域の角の少
し内側を指定すると良い
電球ボタン を押すと位置を示すマー
クが表示される.このマークをドラッグし
ても位置を移動できる
アイコン を左クリックすると何となく
良い場所に移動する(たぶん領域の中
心に移動すると思われます)
① 「BoundaryBox」を非表
示にすると見やすい
③ 内部になるように座標を入力する
例) X=5.0 Y=2.0 Z=1.0
52. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
メッシュの作成
52
③ 「Create」を左クリック
表示モード
「Surface」
BaseMesh と解析領域の形状が表
示されている
② BaseMeshを確認する
① 「BoundaryBox」表示
53. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
メッシュの作成
53
表示モード
「Surface with Edge」
メッシュ生成ログが端末に表示される.
終了したら“End”と表示される
①
② メッシュを確認する
形状の輪郭への再現性が悪いが,
このまま進める
③
×印のアイコンで
端末画面を閉じる
54. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
参考:HelyxOS上でのメッシュ制御
54
メッシュ制御には
主に,これらを使う
① 「Options」を
左クリック ② 「Snapping」タブ
55. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
参考:HelyxOS上でのメッシュ制御
55
レイヤーメッシュの制御
パラメーター
③ 「Layers」タブ① 「General」タブ
レイヤーメッシュを生成するときに
チェックをする.
②
56. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
参考:HelyxOS上でのメッシュ制御
56
① チェックをやめる
しかし,今回のモデルでは効きませんでした.
“レイヤーメッシュを生成しない“ようにするのが効きました.
立方体を組み合わせたような矩形断面の形状・・・snappyHexMeshが苦手なものの一つ
(のちほど,別のメッシュ生成方法も行います)
② 左クリック
③ 「Create」を左クリックすると
メッシュを再生成する
再生のたびにあたらしいが画面が増えていくので,
不要なものは消してよい.
57. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSでの条件設定
57
①
「Open」を
左クリック
③ 「OK」を左クリック
② ケースフォルダーにする
58. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSでの条件設定
58
② 「Solution Modeling」を
左クリック
① 「Case Setup」タブを左クリック
③ Time: Steady
(定常=流れの時間変化無し)
④ Flow: Incompressible
(非圧縮=流体の密度変化が非常に小さい)
⑤ Model: Standard high-Re k-ε
(標準 高Re型k-εモデル)
今後設定を変更してからメニューを移動する場
合は以下のダイアログが出るので,問題が無
ければOKボタンを押して続ける
ドロップダウン式メニュー
調子が悪い時
◇ ↓でメニュー表示
◇ ↑と↓で項目選択
◇ Enterで決定
59. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流体物性の入力
59
③ 「water」を左クリック
① 「air」を左クリック
② 「Change Material」を
左クリック
④ 「OK」を左クリック
HelyxOSではデフォルトの物性ラ
イブラリがある.その中にある水
(液体)の物性値を使う
60. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
境界条件の設定(流入条件)
60
① 「water」に変わって物性値が変更されたことを確認する
② 「inlet」を左クリック ③ 「Wall」から「Patch」に変更
ドロップダウン式メニュー
調子が悪い時
◇ ↓でメニュー表示
◇ ↑と↓で項目選択
◇ Enterで決定
マウスの調子が悪い時
◇ Boundary Conditions
を左ダブルクリック
◇ ↑と↓で項目を移動
④ 「Momentum」タブ
の設定をする
Velocity Type Fixed Value
Velocity [m/s] 10.0 0.0 0.0
Pressure Type Zero Gradient
Wallは壁面用で,
Patchは,流入・流出面用です
⑤ 「Turburence」タブは
デフォルトのままでよい
61. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
境界条件の設定(流出条件)
61
① 「outlet」を左クリック ② 「Wall」から「Patch」に変更
ドロップダウン式メニュー
調子が悪い時
◇ ↓でメニュー表示
◇ ↑と↓で項目選択
◇ Enterで決定
マウスの調子が悪い時
◇ Boundary Conditions
を左ダブルクリック
◇ ↑と↓で項目を移動
③ 「Momentum」タブ
の設定をする
Velocity Type Zero Gradient
Pressure Type Fixed Value
Pressure [m2/s2] 0.0
Wallは壁面用で,
Patchは,流入・流出面用です
④ 「Turburence」タブは
デフォルトのままでよい
62. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
境界条件の設定(壁面条件)
62
① 「walls」を左クリック ② 「Wall」のまま
ドロップダウン式メニュー
調子が悪い時
◇ ↓でメニュー表示
◇ ↑と↓で項目選択
◇ Enterで決定
マウスの調子が悪い時
◇ Boundary Conditions
を左ダブルクリック
◇ ↑と↓で項目を移動
③ 「Momentum」タブ
の設定をする
Type Fixed wall
Wall Type No-slip
Wallは壁面用で,
Patchは,流入・流出面用です
63. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
計算条件の設定
63
① 「Runtime Controls」を
左クリック
計算条件を設定する画面
です.今回はデフォルト
設定値のままでよい Control
Write Control Time Step 1000
結果を保存する時間間隔が1000
※ 定常計算の場合は反復回数のことです
Control
Start From Start Time 0
時刻0から計算を開始
End Time 1000
終了時刻は 1000
※ 定常計算の場合は反復回数のことです
64. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
解析領域の状態の初期化
64
①
「Fields Initialisation」
を左クリック
計算開始時の解析領域
の状態を設定する画面
です.今回は定常計算
なので計算結果に影響
しません
② 「Initialise」を左クリック
③ 「Save As…」を左クリック
次の計算実行に進む前に,設定した内
容を保存するために
65. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
解析領域の状態の初期化
65
計算開始時の解析領域
の状態を設定する画面
です.今回は定常計算
なので計算結果に影響
しません
① 作業フォルダー
② ケースフォルダー
③ 「Saveを左クリック
66. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
解析実行
66
② 「Run Options」を
左クリック
① 「Solver」タブを左クリック
③ 「Run」を
左クリック
67. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
解析終了
67
Control
繰り返し計算中の
残差グラフが描画される
Control
繰り返し計算中の
計算ログが表示される
最後に1000ステップ目のログとEndが表示さ
れたら計算が終了しています
①
繰返計算が
終了したのを
確認する
② メニューバー:File→Exit マウスの調子が悪ければ
×印で終了する
③
68. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
目次
• DEXCS2018 for OpenFOAMとは?
• 例題:バックステップ流れとは?
• FreeCADによるモデルの作成
• HELYX®-OSによる
メッシュの作成・条件設定・計算実行
• ParaViewによるポスト処理
68
69. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
paraFoam(ParaView)の起動
69
① ここからはTreeFoamで操作する
「paraFoamの起動」を左クリック
③ 「OK」を左クリック
② 「paraFoam」を
左クリック
Control
paraFoam
paraFoam-builtin
並列計算結果の読込用
70. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
paraFoam(ParaView)の起動
70
① 「Apply」を
左クリック
71. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Z方向中心断面表示
71
② 「Z Normal」を左クリック
① 「slice」フィルターを左クリック
③ 「Show Plane」のチェックを外す
④ もしも「Apply」が緑色になったら
左クリック
⑤ 「Last Frame」を左クリックして
最終時刻(ステップ)に移動する
72. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流速ベクトル図
72
② Glypy Type を「2D Glyph」にする
④ 「Apply」が緑色になるので左クリック
⑤ 速度で矢印の色付けをするため
「〇U」 「Magunitude」を選ぶ
⑥ 「Show Center」を
トグルオフにする
③ Vectors を「〇U」にする
ベクトル表示をするため
① 「Glyph」フィルターを
左クリック
73. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ステップ後流の循環渦
73
① 下にスクロールする
② Scale Mode を「off」,
Scale Factorを「0.3」くらい
③ 「Apply」が緑色になるので左クリック
④ マウス操作でステップ後流部
を表示して,循環流を確認する
74. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流線
74
① 「Gryph1」フィルターの目のアイコンを
左クリックして,流速ベクトルを
非表示にする
④ 「Apply」が緑色になるので左クリック
③ 「Stream Tracer」フィルターを選ぶ
② 一番上のオブジェクトを左クリックして選ぶ
Control
流線を描くには,断面ではなく解析領域全体
の速度のデータが必要になるので,Sliceフィ
ルタの下流ではなく,上流のオブジェクトから
接続する
厳密には,Stream Tractorは流線を描く機
能ではありません.今回は定常計算のた
め流線と一致します.
75. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流線の調整
75
② Integrator Type を
「Runge Kutta 4」にする
① 「Toggle advencee properties」
という歯車アイコンを
トグルオンにする
③ Initial Step Length を「0.02」にする
76. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流線のシードの変更
76
① Seed Type を
「High Resolution Line Source」
にする
② 直線の両端の座標を設定する
Point1 3 -1 1
Point2 3 3 1
もしも,Slice1の面と重なって見難い時はZ座
標を1.1くらいにする
Control
シード(種)から速度ベクトルを積分して線
をつなげたのが流線です
77. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
流線のシードの変更
77
①
Resolution を
「50」くらいにする
② 「Show Line」の
チェックを外す
③ 緑色になった「Apply」を
左クリックすると,流線を再描画する
78. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ステップ後流での循環渦の流線表示
78
① 「Slice1」フィルターを
左クリックして選ぶ
② 速度で矢印の色付けをするため
「〇U」 「Magunitude」を選ぶ
③ カラーレジェンドが表示されていない時は,
左クリックしてトグルオンする
③ カラーレジェンドをマウスでドラッグして
位置や大きさを調整する
79. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
状態ファイルの保存とParaviewの終了
79
① 「File」 → 「Save State…」
を選ぶ
③ 「File」 → 「Exit」
を選ぶ
② ファイル名を入力
「OK」を左クリック
80. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
目次
• DEXCS2018 for OpenFOAMとは?
• 例題:バックステップ流れとは?
• FreeCADによるモデルの作成
• HELYX®-OSによる
メッシュの作成・条件設定・計算実行
• ParaViewによるポスト処理
• cfMeshによるメッシュ生成
80
おまけ
81. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
CFDの一連の操作の流れにそって
各種のツールを起動して
設定を簡単に行うためのGUI画面を
提供するツール
DEXCSのツールの関係
81
DEXCSランチャー TreeFoam
Paraview(可視化ソフト)
FreeCAD(3D-CADソフト)
HELYX®-
OS
OpenFOAM(ソルバー)
各種のメッシュ生成ソフト
入門者向け
標準設定:非圧縮性流体のみ
非圧縮性以外の設定ができる
圧縮性・熱流体・超音速・混僧流・反応流など
操作性/操作方法の違い
CADデータの
取り込み
以下の
資料での
操作の流れ
灰色の矢印は
各々のGUIツールが
想定している
作業フロー
82. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:FreeCADでの形状作成
82
FreeCAD :終了している
TreeFoam :起動している
HelyxOS :起動している
Paraview :終了している
TreeFoam ① 解析フォルダーを「BackStep」にする
② FreeCADを起動して,前に保存してある
CADファイル(backstep.fcstd)を開く
今の状態の確認
83. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:FreeCADでの形状作成
83
FreeCAD ① 流入部(Face)の名前を「inlet」にする
方法A
対象を選んでおいて右クリックメニュー→名前の変更
方法B
プロパティのLabel欄で修正する
② 流出部(Face006)の名前を「outlet」にする
84. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:FreeCADでの形状作成
84
FreeCAD
① 残りの面を選ぶ ② 「複数の形状の和集合」
を左クリック
③ 「Yes」を左クリック
85. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:FreeCADでの形状作成
85
FreeCAD
① 「Fusion」の名前を
「walls」にする
② 別の名前で保存する.
「ファイル」→「名前をつけて保存する」
保存場所:home/dexcs/Desktop/BackStep
名前 :bakcstep4mesh.fcstd(任意)
86. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:解析フォルダーの作成
86
TreeFoam
① 新しいフォルダーを作成する
② 新しいフォルダーを解析フォルダーにする
「BackStep」を選んでおいて右クリック→「新しいフォルダー追加」
フォルダー名はnewFolder_0(任意)
87. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:解析フォルダーの作成
87
TreeFoam ① 「HelyxOS」を
左クリックする
② 左クリック
③ 「OK」を左クリック
④ ×印を左クリック
して閉じる
88. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:メッシュ作成
88
FreeCAD ① 「cfMesh」を
左クリックす
る
② “ケースファイルの場所”=“解析フォルダー”を変更する
「Case」を左クリックすると選択できるようになる
「newFolder_0」を選んで「開く」を左クリックする
③ 変更後の状態を確認する
89. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:メッシュ作成
89
FreeCAD ① maxCellSize = 0.2
② wallsのみ変更
Typeをwallにして
Boundary Layerを
チェックする
③ 「Export」を左クリック
④ 「Yes」を
左クリック
HelyxOS(snappy)のとき
X方向:0.5,Y,Z方向:0.2
cfMeshは全体サイズを設定する
90. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:メッシュ作成
90
FreeCAD
① 「OK」を左クリック
② 「Exit」を
左クリック
③ 「Yes」を
左クリック
④ FreeCADを終了する
91. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:メッシュ作成
91
TreeFoam ① 「mesh編集」を
左クリックする
② 「cfMeshによる
Mesh作成…」を
左クリックする
92. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
cfMesh:メッシュ作成
92
① 「cfMesh実行」を
左クリックする
④ 「閉じる」を
左クリックする
② 端末画面が表示される,図のような状態
になったらメッシュ作成が終了している.
×印のアイコンを左クリックして端
末を閉じる
TreeFoam
③ 作成されたメッシュを確認したい時
は「paraFoam起動」を左クリックする
93. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSの起動
93
①
HelyxOS
(TreeFoamの
HelyxOSでは
ない)
② 「open」を左クリック
③ 画面の表示にしたがい
「home/dexcs/Desktop/backStep/newFolder_0」
を開く
94. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
内部点(Material Point)の設定
94
読み込まれたメッシュ
① 「Material Point」を選ぶ ② 内部になるように
座標を入力する
例) X=5.0 Y=2.0 Z=1.0
表示モードを
「Boundary Edge」
にすると見やすい
95. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSでの条件設定
95
① 「Open」を 左クリック
④ 「Open」を左クリック
②
作業フォルダーにする
③
ケースフォルダーを選ぶ
96. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
HelyxOSでの条件設定
96
「Case Set」タブ
Time: Steady
Flow: Incompressible
Model: Standard high-Re k-ε
以前と同様に解析条件の設定を行う
「Materials」
「Solution Modeling」
air → water に変える
「Boundary Conditions」
Momentum/U Momentum/p Tubulence
inlet Fixed Value /10 / 0 / 0 Zero Gradient
デフォルト設定outlet Zero Gradient Fixed Value / 0
walls Fixed Wall / No-slip
97. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
計算条件の設定
97
「Case Setup」タブ
「Runtime Controls」
前回と同様にデフォルト設定
「Fields Initialisation」
前回と同様に初期化を行う
前回と同様に,設定を保存する
メニューバー:Save As…
作業フォルダーにする
(/home/dexcs/Desktop/BackStep)
ケースフォルダーにする
(newFolder_0)
「Save」を左クリック
98. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
解析実行とポスト処理
98
「Slover」タブ
「Run Options」
前回と同様に「Run」を左クリック
前回と同様に,計算が終了したことを確認する.
前回と同様に,HelyxOSを終了する.
TreeFoam
前回と同様に,メニューバーのアイコンを左クリックして,paraviewを起動する.
前回に作った paraviewの状態ファイル(post1.pvsm)を
newCase から newFolder_0 にコピーする.
方法はいろいろあります. コマンド端末 / ファイル(GUI)
99. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ポスト処理
99
「newFolder_0.OpenFOAM」
という名前を憶えておく.
右クリック → DELETE(削除)
メニューバー「File」 → 「Load State…」を選んで,
状態ファイル(post1.pvsn)を開く
① 「Choose File Names」にする
② 「 newFolder_0.OpenFOAM 」
にする
③ 「OK」を左クリックする
100. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ポスト処理
100
前回のポスト処理の時と同様に可視化の設定ができている
ことを確認してください.
レイヤーメッシュ
表示設定(Slice面,Crinkle Sliceにチェック SolidColor/Surface with Edge)
101. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
まとめ
• バックステップ流れを例に,モデル作成,メッシュ分割,条件定義,計算
実行および解析結果の確認という解析フローの一連の流れを
DEXCS2018 for OpenFOAMを使って説明した.
もとは DEXCS2013 for OpenFOAMでの例題である.
• 本実習で使用したDEXCS,FreeCAD,OpenFOAM,ParaViewと
HELYX®-OSはオープンソースソフトであるためソフトのライセンス料を支
払う必要がない.商用利用も可能である.
• HELYX®-OSは境界条件の設定がドロップダウンメニューから選べるた
めに,Dictファイルをエディターで修正しなければならないDEXCSラン
チャーよりも作業が楽である.
今回は割愛したがTreeFoamで設定するよりも楽である.ただし,出力されるファイルの内容が対応してい
ないこともあるので注意が必要である.
• 今回使用したソフトはWeb上で.情報が集めやすく,自学自習がしやすい
のも特徴である.
101
102. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
まとめ
102
2)HELYX®-OSが作るcontrolDictファイルにはsolverの種類の記載がないためOpenFOAM
の標準的な端末では動作しない.今回の場合はcontrolDictファイルに下記の行を追記す
れば計算することができた.
application simpleFoam;
ただし
DEXCSのバージョン
DEXCS for OpenFOAM
2016
DEXCS for OpenFOAM
2017
DEXCS for OpenFOAM
2018
OpenFOAM v4.X v1706 v1804
HELYX®-OS v2.3.1 未調査 v2.4.0
このHELYX®-OSが対応して
いるOpenFOAMのバージョン v2.3 -----
v4.X
v1606+
1)下の表のように,無料版のHELYX®-OSは対応するOpenFOAMのバージョンに制約があ
る.今回の練習問題では,v4.Xとv1806とが共通する記載だったために問題が発生しな
かった.
3)調べた限りでは,壁面の熱的境界条件の記載がOpenFOAM-v2.3形式のままでエラーが
発生したためエディターでの修正が必要だった.
HELYX-OSの最新版はv2.4.0 です
103. © Hideaki Kominami (Licensed under CC BY 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
© 小南秀彰 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
謝辞
103
この資料の前半部(snappyでメッシュを生成してポスト処理を行うまでの部分)
は,もともとDEXCS2013 for OpenFOAMを使ってオープンCAE勉強会@関西幹
事(当時)の川畑氏が作成されたオープンCAE勉強会@関西向けの講習会資料
を,ご本人の承諾を得て今野氏がオープンCAE勉強会@関東の講習会向けに
リメイクしたものを,さらに自分がDEXCS2018 for OpenFOAM用にリメイクした
ものです.
お二人の御承諾をいただいた結果,公開できることになりました.
(川畑氏の資料が CC BYでしたので,この資料も同じライセンスで公開します.)
(貴重な活用ノウハウを最初に公開していただいたお二人に感謝いたします.)
後半部(cfMeshでメッシュを生成してポスト処理を行うまでの部分)は自分が
追加した部分ですが,cfMesh用マクロの開発を行った野村氏に感謝いたします.