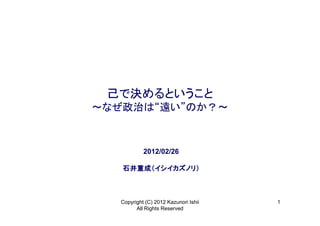More Related Content
More from 86akademeia (9)
86akademeia political culture in japan
- 5. Agenda
1 日本の政治文化の特徴
1.1 世論調査を見てみると・・・
1.2 日本人の政治的態度は「あなたまかせ」?
1.3 「政治的な主体性」ってなんだ?
1.4 日本の民主主義は「借り物」?
2 新しい世の中をつくるため
2.1 政治は科学ではない
2.2 国家はフィクション
2.3 政治と無関係に生きることはできない
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 5
All Rights Reserved
- 7. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
国民に意思は政府に伝わらない? 借り物民主主義
約8割の国民が政策に民意が反映されていないと感じている (2010年)
国の政策への民意の反映程度 (内閣府HPより作成)
1.2 17.3 2.8 58.1 20.5
平均
20-29歳
30-39歳
かなり反映されている
40-49歳
ある程度反映されている
50-59歳
わからない
60-69歳 あまり反映されていない
70歳以上 ほとんど反映されていない
0% 20% 40% 60% 80% 100%
参照:http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-shakai/zh/z27.html
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 7
All Rights Reserved
- 8. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
政府や政治家は国民の声を聞いてくれない? 借り物民主主義
4割以上の国民が、国や政治家はもっと国民の声を聞くべきだと感じている(2010年)
国の政策への民意の反映方法 (内閣府HPより作成)
27.5 14.1 20.2 15.3 15.3 5.1
平均 政治家が国民の声をよく聞く
政府が世論をよく聞く
20~29歳
国民が国の政策に関心を持つ
30~39歳
国民が選挙の時に自覚して投票する
40~49歳
国民が参加できる場をひろげる
50~59歳 マスコミが国民の意見をよく伝える
60~69歳 その他
70歳以上 わからない
0% 20% 40% 60% 80% 100%
参照:http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-shakai/zh/z29.html
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 8
All Rights Reserved
- 9. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
日本人の「お上依存」は世界トップクラス? 借り物民主主義
7割以上の日本人が社会に責任を持つのは個人ではなく国であると回答している
国民が安心して暮らせるように責任を持つのは個人ではなく国と答えた人の割合
国民が安心して暮らせるように責任を持つのは個人ではなく国と答えた人の割合
(「世界価値観調査(電通・2005)」より作成)
ロシア
日本 71.4%
ドイツ
フランス
アメリカ
イギリス
スウェーデン 33.1%
0 20 40 60 80
参照:『日経ビジネス(2008年5月12日号)』
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 9
All Rights Reserved
- 10. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
日本の高校生は社会に悲観的? 借り物民主主義
日本の高校生は自分の政治参加によって、国や社会を変えられるという感覚に乏しい
個人の力では政府の決定に影響を与えられないと思うか (ベネッセHPより作成)
0.9
韓国 13.4 41.8 33.6 10.3
0.6
中国 19.1 24.7 34.1 21.5
全くそう思う
4.2
アメリカ 14.6 28.3 26.6 26.3 まあそう思う
あまりそう思わない
1.9 全くそう思わない
日本 40.1 40.6 11.9 5.5
無回答
0% 20% 40% 60% 80% 100%
⇒ 次章では、このような日本人の政治的態度(=政治文化)の特徴を考えていく
参照:http://benesse.jp/berd/aboutus/katsudou/research_column/pt_02/23.html
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 10
All Rights Reserved
- 11. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
アーモンド・ヴァーバによる政治文化の3分類 借り物民主主義
政治文化には「偏狭型」、「臣民型」、「参加型」が存在する
アメリカの政治学者であるガブリエル・アーモンドとシドニー・ヴァーバは、5カ国の比較研究
により、政治文化を「政治的対象に対する心理的指向」
「政治的対象に対する心理的指向」と定義した。
「政治的対象に対する心理的指向」
①政治システム
②インプット(政治機構に対する利益の表明や投票による影響力の行使など)
③アウトプット(政府の決定した政策内容やその施行方法など)
④政治システムの中の自分
分類 ① ② ③ ④ 該当する国
該当する国
偏狭型 メキシコ
臣民型 ドイツ、イタリア
参加型 アメリカ、イギリス
参照:『現代日本の政治文化』、中村菊男著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 11
All Rights Reserved
- 12. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
政治的有効性感覚とは? 借り物民主主義
政治学者である中村菊男は、日本の政治文化を臣民型に近いと主張した
自分の一票で社会をどれだけ変えることができるかという政治意識
自分の一票で社会をどれだけ変えることができるかという政治意識を
一票で社会を
政治的有効性感覚という この政治的有効性感覚は2種類あり、市民
政治的有効性感覚という。
有効性感覚という 市
有効性感覚(citizen competence)と臣民的有効性感覚
的有効性感覚(
性感覚( ) 臣民的有効性感覚(subject
臣民的有効性感覚
competence)に分けられる。
政治的有効性感覚 市民的有効性感覚(citizen competence)
⇒政治体系の入力面に対する有効感であり、政治参加や影響力行
使といった能動的、積極的な有効感
臣民的有効性感覚(subject competence)
⇒政治体系の出力面に対する有効感であり、被治者(すなわち臣民)として
の役割の自覚や、統治者への評価・期待といった受動的な有効感
⇒世論調査を見ると納得?
参照:『現代日本の政治文化』、中村菊男著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 12
All Rights Reserved
- 13. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
尭舜の治 借り物民主主義
「国は国民が何の憂いもなく幸せに暮らせるように責任を持つべき」という発想がある
中国の伝説に尭と舜という天子が登場する。
尭の治世によって国は栄え、人々は幸せに暮らしていた。
ある日、尭は自分の政治によって天下が本当に治まっているか、
民が暮らしに満足しているか不安になり、変装して町に出る。
老百姓が愉快に歌っているのを見て、尭は世の中の安寧を悟った。
「舜帝の切手」
「老百姓の歌」
帝力何有於我哉
耕田而食
鑿井而飲
日入而息
日出而作
日の出と共に働きに出て、
日の入と共に休みに帰る。
水を飲みたければ井戸を掘って飲み、
飯を食いたければ田畑を耕して食う。
帝の力がどうして私に関わりがあるというのだろうか。
参照:『指導者の条件』、松下幸之助著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 13
All Rights Reserved
- 14. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
日本人の政治的態度は「あなたまかせ」? 借り物民主主義
政治不信の構造を研究した村山皓は、日本人の政治意識を「あなたまかせ」と称した
「日本人の政治不信は「あなたまかせ」
「あなたまかせ」の不信である。日本人の政治
「あなたまかせ」
への不満は、民主政治に原因と結果があるのなら、原因を無視し結
果の善し悪しで左右される。政治への国民の影響力が民主政治の原
因とすれば、その影響力がないことへの不満は比較的重要ではない。
結果としての国の政策や行為への不満の うが重要である」
結果としての国の政策や行為への不満
むしろ結果としての国の政策や行為への不満のほうが重要である
村山皓
Q.1:日本人の政治意識は「あなたまかせ」だと思いますか?(Yes/No)
Q.2:その理由を教えてください
⇒次章では、そもそも「政治を担う」とはどういうことなのかを考えていく
参照:『日本の民主政の文化的特徴』、村山皓著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 14
All Rights Reserved
- 15. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
近代における政治的主体の誕生 借り物民主主義
マキャベリは『君主論』の中で、君主が主体として国家をつくることを論じた
マキャベリは君主が備えるべき徳(ヴィルトゥ)とはなにかを『君主論』
で論じた。強大な国家をつくって維持することがすべてに優先する。
すべてが“宗教の侍女”であった昨日までの世界とは逆に、すべてが
政治的な目的の侍女になる。キリスト教でさえ君主が国家を維持する
ための道具でしかない。
国家は神とともに人間 君臨する存在としてではなく、人間
国家は神とともに人間に君臨する存在としてではなく、人間がつくるべ
する存在としてではなく、人
被造物として えられた。「人間が主体であり国家が客体である」と
物として捉
き被造物として捉えられた。
いうこれまでの神中心の世界観が逆転した。
ニッコロ・マキャベリ
「国家は自らの手でつくりあげるもの」と
マキャベリの思想において、 「国家は自らの手でつくりあげるもの」
いう近代的な意味における、政治的主体性が誕生した 。
・・・ちなみに、マキャベリの発想の根底には2つの前提があった
①国家をつくる基本は暴力の集中である
②民衆は阿呆である
参照:『現代における政治と人間』、高畠通敏著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 15
All Rights Reserved
- 16. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
「市民」の誕生 借り物民主主義
社会契約論と革命によって、近代国家的な市民が誕生した
ルソーは、人々が単に恐怖から君主の権力に従うのではなく、進んで
従うべき権力や政府というものを考えるとき、そこに契約という原初的
な合意があったと仮定する以外にないと考えた。
絶対君主を革命によって打倒して人々たちは、古代ギリシャのポリス
におけるデモクラシーよりもはるかに規模の大きい、多数主体が運営
多数主体が運営
多数主体が
する国家という課題に向き合う必要があった。
する国家
人々はまず法や制度を整え、立憲政治を創設する。市民国家の憲法
は、人権の宣言と政府の組織の二つの部分からなり、その枠を超えて
権力は行動できないとしている。 ジャン・ジャック・ルソー
近代国家の最大の問題は、人々の相互の対立をどのように調整
人 相互の対立
の対 のように調整
し、少数派 納得して う決定を生み出すことができるかというこ
少数派も して従
し、少数派も納得して従う決定を生み出すことができるか
とであり、それが議会政治の焦点となっていく。
「理性的」なコミュニケーションによって国益を討議する、議会民主
主義の担い手としての市民が誕生する。
市
フランスのシテ島
参照:『現代における政治と人間』、高畠通敏著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 16
All Rights Reserved
- 17. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
市民の崩壊と大衆の登場 借り物民主主義
マルクスは「市民」というイデオロギーを暴露し、選挙権拡大によって「大衆」が登場する
マルクスは市民国家はブルジョア支配にすぎないと批判する。「理性的」
市民国家はブルジョア支配にすぎない
支配にす
な討議デモクラシーを、市民(=ブルジョワ)による支配の正当化と捉え、
市民国家という概念そのものがイデオロギーであると主張する。
当時の「市民」とは財産と教養を持つ人々であり、無産階級の絶対多数の
人々は含まれなかった。かれらは財産と教養を独占することによって支配
階級に居座ることができ、それを「理性的」と称していたに過ぎないと。
カール・マルクス
「普通選挙実施年」
選挙実施年」
「市民」という概念が揺らいでいく一方で、普通選挙(選
男性 女性 挙の際に年齢・性別以外の制限をつけない形式)の実
フランス 1848年 1944年 施を求める運動が各国で拡がっていった。
アメリカ 1870年 1920年 ここにおいて政治的主体としての大衆
大衆が誕生する。マス
大衆
イギリス 1918年 1928年 メディアが非常に大きな影響を持つようになり、大衆は
大衆は
大衆
的には政治的主体であるのにもかかわらず、実際
概念的には政治的主体であるのにもかかわらず、
概念的には政治的主体であるのにもかかわらず、実際
日本 1925年 1945年
には「受動的な存在」になっていく。
受動的な存在」になっていく
には「受動的な存在」になっていく
参照:『現代における政治と人間』、高畠通敏著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 17
All Rights Reserved
- 18. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
近代政治の発展は政治的主体数の拡張 借り物民主主義
政治的主体数が増えれば増えるほど、国家に対する影響力は小さくなる
政治的主体 主体数
主体数 国家に対する影響力
君主 一人 とても大きい
市民 小数 大きい
大衆 多数 小さい
「自分が何かしても国は変わらない」と感じる大きな原因に政治的主体数の増加がある。
「自分が何かしても国は変わらない」
⇒現代人が「自分が何かしても国は変わらない」
しかし、国や地域によってその政治的態度に違いが見られるのは何故だろうか?
次章では、日本人の政治的態度の構造や起因を考えていく。
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 18
All Rights Reserved
- 19. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
明治維新と敗戦 借り物民主主義
日本の近代化(民主化)は外圧によって急ピッチで成し遂げられた
列強諸国からの外圧によって、明治維新を成し遂げ
た日本は、富国強兵を推進し、急激な近代化を成し
遂げた。憲法を策定し帝国議会を設立した日本は市
民革命を経験したかのようにも見える。
しかし、「和魂洋才」という言葉が示すように、システ
「和魂洋才」
ムを取り入れても、依然として“日本的”な思考・慣
習がそこにあることが分かる。明治維新が当時「御
一新」と呼ばれたことも示唆深い。
太平洋戦争に敗れた日本は、GHQの指導の下、様々な民主化政
策を受け入れる。新しい憲法には「国民主権」「平和主義」「基本的
人権」が謳われ、議院内閣制が明文化され、女性参政権も認めら
れた。
しかし、これらの成果は日本人自身が勝ち取ったものではない(と
言われる)。そこに戦後民主主義最大の特徴がある。
⇒日本は西欧のシステムを輸入することによって近代化や民主化を達成したが、
制度の土台となる文化や慣習には、きわめて“日本的”な要素が多く残っている。
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 19
All Rights Reserved
- 20. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
日本の根底にある「ムラ」カルチュア 借り物民主主義
「ムラ」カルチュアとは「全員一致の意思決定」や「対立自体が悪」などの習俗を指す
「全員
「全 の意思決定」 「対 自体が悪
「対立
政治学者の神島二郎は「ムラの文化は近代日本の社会あるいは
明治以降
集団内での根源的な政治原理として機能してきた。明治以降の日
明治以 西欧的な政治制度
本社会とは、旧来の伝統的なムラ文化の上に、欧米から輸
旧来の伝 欧米から
本社会とは、旧来の伝統的なムラ文化の上に、欧米から輸入さ
日本的な「ムラ」カルチュア
れたデモクラシー(近代的な法体系
近代的な法体 度など)が重なった二
れたデモクラシー(近代的な法体系・制度など)が重なった二重構
造から成っている」と述べる。 イメージ図
全員一致の意思決定 対立自体が悪という概念
自体が悪という概念
内部にしこりを残さないために「多数決による 対立自体を悪とし、「本来なら人々は分
意思決定」を退ける かり合える」という同質性の前提に立つ
⇒一見、みんなの意見を大切にする方法に見 ⇒100人いれば100通りの考え方がある
えるが、少数者や反対者が意見を述べること という「お互いに異なる立場からの主張」
自体が不可能となる が困難になる
e.f.) 稟議制における「逆さ印」の話
⇒「弁論の勝利(お互いの立場から議論を交わし、議論によって決着をつける)」という
カルチュアが成立しにくい
参照:『近代日本の精神構造』、神島二郎著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 20
All Rights Reserved
- 21. 世論調査
あなたまかせ
政治的主体
高度経済成長とPublic(公) 借り物民主主義
戦後日本は経済成長を第一に掲げて、PublicとPrivateの領域を区別してきた
英語圏でpublicとは「みんなのもの」であるのに対して、日本
語で公とは「お上」や「官」を指すことが多い。
公(おおやけ)という字はもともと「大家(天皇家)」からきてい
る。publicという語に「公」の字があてられたこと自体が日本
人の政治意識を表している。
戦後日本では、戦前の国家主義の反動で「お上」である「公」
よりも「私」のことがらが重要であるという風潮がつくられ、
」は政治家と官僚に任せておけばよく、「普通の人」は基
官僚に任せておけばよく、「
「公」は政治家と官僚に任せておけばよく、「普通の人」は基
本的に「私」の世界に生きていればよいことになった。
本的に「私」の世界に生きていればよいことになった
経済成長を至高命題とする日本の政治は、戦争の総括や天皇制の
あり方を国民を巻き込んで議論してこなかった。
物質的な豊かさを求めるには「頑張って働けばよい
働けばよい」ということにな
頑 って働けばよい
り、自分たちの政治参加によって社会をよくしようという気運が高ま
ることは少なかった。
自民党の一党独裁を存続させた大きな原動力がここにある。
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 21
All Rights Reserved
- 23. 政治は科学ではない
政治的決定はあらゆる関係者に対してトレードオフの関係にあり、「正解」はない
「
政治は「科学」ではない。政府がなんらかの政策決定を行うとき、そこに
政治は「科学」ではない
は倫理的な判断が必要とされる。どれだけ「よい」目標を掲げても、その
「よい」目標同士が衝突してしまうこともあるし、利用できる資源が限られ
ていることもある。
たとえば経済的平等を実現しようとすれば、経済的な刺激が損なわれて
しまう可能性がある。高齢者の税の負担を軽減しようとすれば、若年層
の負担を重くすることになりうる。それぞれの目標がトレードオフの関係
それぞ
それ れの目標がトレードオ
にある場合、政府の政策判 を「科学的」に下すことはできない。
にある場合、政府の政策判断を「科学的」に下すことはできない ロバート・ダール
定性的・感情的な判断が必要となる以上、政治的
政治的
決定に「正 )」はない。
決定に「正解(≒中立)」はない
人々の生き様や政治的決定の結集である歴史もま
た「正解」を持たない。政治には「終わり」もない
政治には「終
政治には「 わり」もない。
参照:『デモクラシーとは何か』、ロバート・ダール著
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 23
All Rights Reserved
- 24. 国家はフィクション
国家や政府とは人間がつくりだした創造物にすぎない
創造物
創造
国家や政府というのは最初からどこかにあるものではなく、人
が作ったものに過ぎない。よって、人間の作為的行為として捉
えるべきである。
そして人為的行為である以上、誰がやっても「間違える」
「間違える」とい
える」
うことを前提に政治にかかわる姿勢が必要である。
政治家とは特別ではない、「普通の人間
政治家とは特別ではない、「普通の人間」である。
満員電車に揺られて、長時間労働に疲弊する人がいる一
方で、職がない人たちがたくさんいる。
「こんな世の中に誰がした?」という不満を言う人は多い。
しかし、「こんな世の中にしているのは私たち自身」と答え
「こんな世の中にしているのは私
「こんな世の中にしているのは
ざるを得ないし、その意識こそがデモクラシーを本物にする。
嫌なら嫌と言えばいいし、変えたいのなら変えればいい。
なら嫌 いいし、変えたいのなら変えれば
それは自分たち
それは自分たちでつくったものなのだから。
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 24
All Rights Reserved
- 25. 政治と無関係に生きることはできない
政治とはより多く人々が納得できる意思決定
より多く人々 納得できる意思決定をする行為である
より できる意思決定
人は、自分に関る意思決定がされる時に、自分がそのプロセスにコミットしているかどうかで納
自分に関る意思決定がされる時に、自分がそのプロセスにコミットしているかどうかで納
自分に関る意思決定がされる コミットしているか
感が変わってくる。さらに、自分に不利な意思決定であればあるほど、その度合いは高まる。
得感が変わってくる。
日本の政治にとって、「納得性の問題」はこれからどんどん重要になってくる。人口減少・少子
「納得性の問題
性の問
高齢化、債務超過や経済規模縮小といった大きな課題に向き合わなければならないからであ
る。政府の役割が「富の分配」から「負担の分配」にシフトしている
政府の 割が「富の分配」から「負担の分配」にシフトしていることを理解する必要がある。
政府の役
しかし、ネガティブになることはない。
こそ「新しい世」をみんなでつくることができる時代
時代だと思うから。
今こそ「新しい世」をみんなでつくることができる時代
ソーシャルに繋がり、会社が全てという価値観を棄て、経
済大国の看板をどうでもよいと思えるから世代だからこそ
できることがある。
「政治」という言
「政治」という言葉を小さく捉えないで欲しい。霞ヶ関や永
さく捉えないで欲しい。霞ヶ関や永
霞ヶ関や
田町で きていることだけ
田町で起きていることだけが政治ではない。
自分の生き方を自分で決める。これこそが政治のゴ
自分の生き方を自分で決める。これこそが政治のゴール
であり、デモクラシーの根 理に違
であり、デモクラシーの根本原理に違いない。
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 25
All Rights Reserved
- 27. 「刺さる」文献
今日の講義で政治文化論に興味を持った方にオススメしたい本たち
「「現実」主義の陥穽」、丸山真男著
⇒何気なく使っている「現実主義」という言葉に潜む罠とは?
『「空気」の研究』、山本七平著
⇒太平洋戦争開戦はその場の空気によって決まった?
『人間を幸福にしない日本というシステム』、カレルヴァン・ヴォルフレン著
⇒「仕方がない」という発想が自分たちを不幸にする?
『現代における政治と人間』、高畠通敏著
⇒政治とは何か? そんな根源的な問いを考えるのにピッタリ
Copyright (C) 2012 Kazunori Ishii 27
All Rights Reserved