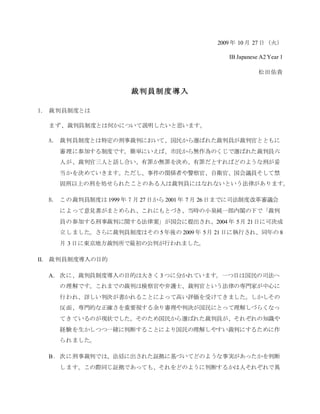More Related Content
More from Yuki Matsuda (7)
裁判員制度ー原稿
- 1. 2009 年 10 月 27 日(火)
IB Japanese A2 Year 1
松田佑貴
裁判員制度導入
I. 裁判員制度とは
まず、裁判員制度とは何かについて説明したいと思います。
A. 裁判員制度とは特定の刑事裁判において、国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに
審理に参加する制度です。簡単にいえば、市民から無作為のくじで選ばれた裁判員六
人が、裁判官三人と話し合い、有罪か無罪を決め、有罪だとすればどのような刑が妥
当かを決めていきます。ただし、事件の関係者や警察官、自衛官、国会議員そして禁
固刑以上の刑を処せられたことのある人は裁判員にはなれないという法律があります。
B. この裁判員制度は 1999 年 7 月 27 日から 2001 年 7 月 26 日までに司法制度改革審議会
によって意見書がまとめられ、これにもとづき、当時の小泉純一郎内閣の下で「裁判
員の参加する刑事裁判に関する法律案」が国会に提出され、2004 年 5月 21日に可決成
立しました。さらに裁判員制度はその 5 年後の 2009 年 5月 21 日に執行され、同年の 8
月 3 日に東京地方裁判所で最初の公判が行われました。
II. 裁判員制度導入の目的
A. 次に、裁判員制度導入の目的は大きく 3 つに分かれています。一つ目は国民の司法へ
の理解です。これまでの裁判は検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心に
行われ、詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきました。しかしその
反面、専門的な正確さを重要視する余り審理や判決が国民にとって理解しづらくなっ
てきているのが現状でした。そのため国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識や
経験を生かしつつ一緒に判断することにより国民の理解しやすい裁判にするために作
られました。
B. 次に刑事裁判では、法廷に出された証拠に基づいてどのような事実があったかを判断
します。この際同じ証拠であっても、それをどのように判断するかは人それぞれで異
- 2. なり、例えば、ある証人の証言について、ある人は「信用できる」、他の人はその経
験や知識を照らし合わせて「信用できない」と判断することもあります。さまざまな
生 活上の経験や知識を持った市民が刑事裁判に参加することによって、証拠
を いろんな角度から評価することが可能となり、刑事裁判の質が向上するこ
と が期待されます。
C. 最後に刑事裁判では「無罪の推定」が重要なポイントとされています。「無罪の推定」
とは、犯罪を行ったと疑われて捜査や、刑事裁判に受ける人について、刑事裁判で有
罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として扱わなければならないとする法律
です。さらに被告人が犯罪を行ったことにつき、検察官が「合理的な疑問を残さない
程度の証明」、つまり被告人を有罪にするためには、疑問の余地はないと確信
で きる程度の証明をしない限り、被告人を有罪とすることはできません。刑
事 裁判では、検察や警察がその組織と捜索・取調べなど強制力を用いて証拠
を 集めることができるのに対して、疑いを向けられた被告人は有利な証拠を
集 めるための組織も強制力もなく、大きな力の差があります。にもかかわら
ず 、被告人が自らの無実を証明できないからといって、有罪となってしまっ
た ら、多くの無実の市民が有罪とされてしまうおそれがあります。そして、
無 実の市民に対する有罪判決は、市民の自由や権利を勝手に奪い、その人生
を 狂わせ、家族にまで大きな打撃を与えるという深刻な問題が発生します。
市 民が常識に照らして疑問の余地がないかどうか確認するということがまず
無 実の市民が罰せられるという悲劇を防止します。
III. 裁 判員裁判
A. さ て、国民が裁判員として参加する裁判はどのような事件が挙げられると思
い ますか。刑事裁判すべてにあたるわけでもありません。実際のところ数あ
る 刑事裁判の中でも重要な事件に限られてきます。ではどんな事件が対象か
というと、死刑または無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件、およ
び短期 1 年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件のうち故意の犯罪行為に
より被害者を死亡させた罪に関する事件が対象です。具体的の事件としては殺人罪、
傷害致死罪、身代金目的誘拐罪、などがあります。レジュメに細かく載っているので
そちらを見てください。以下の通り世間を騒がせるような凶悪事件が対象となってい
ます。ちなみに去年の全国の地検・支部が裁判員制度対象事件で延べ1212人を起
- 3. 訴したと最高検察庁が発表しました。これは裁判員法施行の5月21日以降に起訴さ
れた被告が、裁判員裁判の対象です。
B. 次 に裁判員は有罪、無罪の判決や少年事件における保護処分が妥当と認める
場 合の家庭裁判所への移法決定にあたって事実の認定、刑の重さについて裁
判 官と共に協議して決める権限があります。評議では裁判員、裁判官の全員
一 致を目指して議論しますが、仮に全員の意見が一致しなかった場合には、
多 数決により結論を出します。
IV. 背 景事情
A. さ て、裁判員制度導入前の 2009 年 5 月の調査でまずこれまでの刑事裁判の判
決について尋ねたところ、「適切だと感じることが多い」は 34%にとどまり、
「 軽すぎる」が 50%、「重すぎる」は4%だったことからこれまでの判決に
つ いて割り切れない思いを抱いているようです。しかし裁判員として裁判に
参 加したいか尋ねたところ「参加したい」と思う人は 18%にとどまり、「参
加 したくない」は 79%でした。つまりほぼ 8 割の人が、自分が裁判員になる
こ とに不安を感じています。
B. 続いて、裁判員制度に賛成、そして反対の意見を比較してみたところ賛成する立場の
根拠として「国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に
反映する」という考えの上に成り立っているものが多く、制度導入によって市民の負
担は少ないと考えている人が多いようです。それに対して、反対の立場は「一般市民
には裁判の知識が乏しい」と見ていて素人の判断で正しい判決が出るかと心配してい
る声が多く上がっています。
V. 問 題点
A. 続 いて、裁判員制度導入の問題点ですが大きく分けて二つあります。一つ目
は 裁判員の出頭義務です。これは裁判員に選ばれた人が裁判当日に正当な理
由 なく出廷しないときは、10万円以下の罰金が科せられます。なお従業員
が 裁判に参加することで、かりに業務に支障をきたしたとしても、その従業
員 に処分を課すことや、解雇にすることは裁判員法で禁じられています。そ
- 4. の ため、トヨタ自動車や東京電力などの会社ではいちはやく裁判参加を理由
に 社員が休暇をとる場合に備えて、「裁判員休暇」を新設しています。
B. 次 に裁判員の不利益です。裁判員候補者は、正式な裁判員を選ぶときに宗教
や プライバシーに踏み込んだ質問を受ける可能性があります。さらに裁判員
は 法廷で出される全てを確認する必要があるので、その中に遺体の写真など
グ ロテスク資料があった場合は不愉快に感じ、精神的な後遺症をわずらうお
そ れがあります。その他、判決で合理的な理由により死刑判決に賛成した場
合 であっても、将来にわたり罪悪感に見舞われ一般生活に支障をきたすおそ
れ があります。
C. 裁 判員を経験された人判決を決める時、有罪、無罪を含めた量刑まで決めな
く てはいけないので、何を基準にして決めればいけないかというのが大きな
問 題です。
VI. 展 望
A. 裁 判員制度が始まって 2 年目の 2010 年、検察側の死刑求刑が予想される重大事件
や、被告が起訴事実を否認する事件などの審理が大幅に増えると予想されます。09 年
の初年度は被告側が犯行を認め、刑の重さが争われる事件が大半であったが、今後は
死刑求刑事件や無罪主張事件では、より慎重な審理が求められ、公判回数も増えると
可能性があります。
以 上で裁判員制度のプレゼンテーションを終わります。