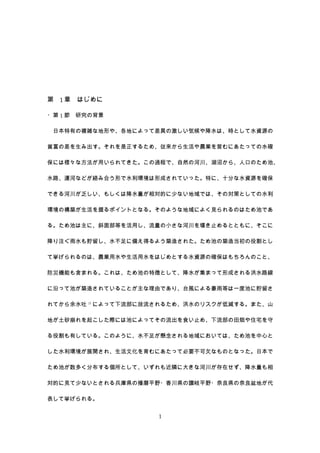
【卒論】ニュータウン建設がもたらす水利構造の変化
- 1. 第 1 章 はじめに ・第 1 節 研究の背景 日本特有の複雑な地形や、各地によって差異の激しい気候や降水は、時として水資源の 貧富の差を生み出す。それを是正するため、従来から生活や農業を営むにあたっての水確 保には様々な方法が用いられてきた。この過程で、自然の河川、湖沼から、人口のため池、 水路、運河などが絡み合う形で水利環境は形成されていった。特に、十分な水資源を確保 できる河川が乏しい、もしくは降水量が相対的に少ない地域では、その対策としての水利 環境の構築が生活を握るポイントとなる。そのような地域によく見られるのはため池であ る。ため池は主に、斜面部等を活用し、流量の小さな河川を堰き止めるとともに、そこに 降り注ぐ雨水も貯留し、水不足に備え得るよう築造された。ため池の築造当初の役割とし て挙げられるのは、農業用水や生活用水をはじめとする水資源の確保はもちろんのこと、 防災機能も含まれる。これは、ため池の特徴として、降水が集まって形成される洪水路線 に沿って池が築造されていることが主な理由であり、台風による豪雨等は一度池に貯留さ れてから余水吐 1) によって下流部に放流されるため、洪水のリスクが低減する。また、山 地が土砂崩れを起こした際には池によってその流出を食い止め、下流部の田畑や住宅を守 る役割も有している。このように、水不足が懸念される地域においては、ため池を中心と した水利環境が展開され、生活文化を育むにあたって必要不可欠なものとなった。日本で ため池が数多く分布する個所として、いずれも近隣に大きな河川が存在せず、降水量も相 対的に見て少ないとされる兵庫県の播磨平野・香川県の讃岐平野・奈良県の奈良盆地が代 表して挙げられる。 1
- 3. ・第 2 節 ため池の抱える課題 古代から築造され、日本の農業および生活を発展させるツールとして利用され続けたた め池、およびその基幹をなす水利環境は、ここ数十年の開発によりその姿が大きく変化し た。その過程で、ため池への利用目的や存在価値は変化した他、ため池自体が消滅するケ ースや、維持管理の放棄とともに荒廃するケースが見られる。とりわけ深刻なのは、最後 に記述したため池の荒廃である。その理由としては、堤体および付帯設備の老朽化により 決壊のリスクが高くなるという点にある。経年により堤体には貯留水が徐々に浸み込み、 その骨組みは時間の経過とともに貧弱なものとなり、洪水や地震などの自然災害時におけ る決壊が懸念される。実例として、香川県では 2003 年の台風により県内 834 か所のため 池が被災し、決壊が 114 か所、堤防の前面、裏面のズレが生じたものや洪水吐、取水施設 に被害が生じたものが 215 か所、その他の被災が 505 か所に及んだ 2) 。また、維持管理が 放棄された結果水質が悪化し、悪臭が近隣住民の生活をむしばむことも問題になっている。 ため池の維持管理がおろそかにされる背景には、主に行政が管理するケースの多い河川と は異なり、比較的小規模な水利組合や集落、個人の手によって管理されている実態を認識 する必要がある。そもそも維持管理されにくい条件に加え、高度経済成長期の宅地開発ラ ッシュにより急激に変化する土地利用からため池が取り残され、残置されたものの状態が 悪化する例がいくつか存在する。その前例として、泉北ニュータウン造成によるため池の 潰廃を挙げる 3) 。これは、ニュータウン造成において、計画的に設定された残置ため池の 管理権が水利団体から大阪府企業局へと委譲され、水利団体の有する権利はあくまで自動 3
- 5. どのような方向性を持っているのか、④これらを踏まえ、私たちの身近に存在するため池 の価値を今一度見直し、現在もなお進行する都市計画事業の水環境への考え方に対して、 ある程度の提言を加えることを主たる研究目的として設定する。 第 2 章 調査地の概要 ・第 1 節 千里丘陵の地形 千里丘陵は、現在の大阪市の北側に近接し、行政区域として西側は豊中市、東側は吹田 市にまたがるかたちで位置する。この地域は、六甲山脈が北東に伸びた形で誕生した北摂 山地から大阪平野に向けて突出隆起している洪積台地であり、地質学的には洪積層に分類 される。この千里丘陵を含め、大阪平野の周辺部にはいくつかの丘陵地帯が存在し、これ らはまとめて大阪層群と呼ばれている。大阪層群の起源は約 170 万年前にさかのぼり、氷 河期における海面の後退と陸化、および山地の隆起運動を経た後、さらに浸食、準平原化 が繰り返されて、現在の丘陵地帯を形成したと考えられている。 次に、地形の特徴を述べる。丘陵の標高は丘陵北西部に位置する島熊山 (133m) 付近を 最高地点とし、そこから地形は南東方向に向けてゆるく傾斜する形で広がる。丘陵南東部 の末端部からはやや急峻な標高差を表しながら、大阪平野へと臨んでいる。なお、丘陵全 体の平均標高は約50mから約70mで、平坦な尾根筋と谷部が波浪するかの如く入り組んだ 複雑な地形を見せており、豊中市と吹田市の境界線に沿って北から南へ伸びる尾根線が分 水線となっている。丘陵内の主要な河川は 5 つ挙げられ、丘陵西部から順に千里川・天竺 川・高川・正雀川・山田川である。千里川は箕面山を水源とし、途中丘陵西部を経由して 5
- 6. 猪名川に合流する。残る 4 つの河川は丘陵内部に水源とし、谷を形成しながら丘陵の南端 に向かって流れ、天竺川・高川は神崎川に合流した後に、正雀川・山田川は安威川へ合流 した後に、それぞれ淀川へと通じている。 ・第 2 節 宅地開発前の生活状況 千里丘陵において、山田地区・佐井寺地区・旧垂水村は湧水の豊富な地域であったこと から、宅地開発の進行前から既にある程度の集落が存在したと考えられている。この「垂 水」の地名は豊富な湧水が起源となっている。また、垂水神社・神殿神社の存在は、湧水 や泉の付近に集落が位置していたことを物語っている。しかしながら、上記以外の地域で の水利環境は非常に乏しく、丘陵内の主要な河川は千里川・天竺川・高川・正雀川・山田 川の 5 つにとどまり、いずれも流量、流域ともに小さなものであった。江戸時代からは農 業用の目的としてため池の築造が開始されたと考えられているが、水資源の確保は相変わ らず困難であり、当時の水不足への苦悩を表したものとして、「月夜に田んぼが焼ける」 という言葉が存在するほど深刻であった。また、当時の住民の話によれば、丘陵内の水田 は頻繁に干上がるため、年貢米を収めるのは他の地域と比較して非常に苦労したと記録さ れている 4) 。当時、タケノコは千里の名物とされていたが、それは深刻な水不足に影響さ れる米づくりから脱皮するための所産でもあり、土地の名物として知れ渡ることは一種の 皮肉だったと考えられる。また、丘陵内の神社では雨乞い行事が盛んに行われ、盛り上が りを見せた。ニュータウン開発前の土地利用を見ても、尾根と谷が複雑に入り組んでおり、 その大部分はマツなどの原生林で覆われ、残りの部分は果樹園・タケノコ畑が位置し、河 6
- 7. 川の位置する谷部には水田とため池が位置するのが土地利用の概要であったが、生活を営 むための水源を確保するのがやっとの状態であった。以上から、千里丘陵においての深刻 な水不足と複雑に入り組んだ地形は宅地化開発をより困難なものとする大きな要因であり、 その結果、大阪市内と比較して土地開発から大きく取り残され、農地利用以外にほぼ未開 拓のまま残っていた。 ・第 3 節 土地利用の変遷 第 2 節で述べたことを理由に、これまでほぼ手つかずの状態だった千里丘陵で最初に開 発の手が加わったのは佐井寺地区で、原生のタケ林を切り拓く形で宅地化が進行した。続 いて、吹田市南東部には府営住宅がまとまって開発された。しかしながら、これらの開発 が丘陵全体面積に占める割合はわずか数%にとどまっており、あくまで今までの未開拓地 に住宅が点在し始めた状態に過ぎなかった。千里丘陵全体の土地利用の変化を述べるにあ たって最大の特徴として挙げられるのは、 1958 年に着工が正式決定し、 1961 年に建設 開始された千里ニュータウンである。その開発面積は 1,160ha( 吹田市域は791ha、豊中 市域は 369ha) と当時としては大規模なものであり、これは千里丘陵北部の大部分を占め る計算となる。開発された背景として、 1950 年代から 1960 年代にかけての高度経済成 長期にかけて、急激に増加の一途をたどる大阪府内の人口に対してどう対処するかが課題 となり、市内に代わる新たな宅地を開発する必要性が高まったことが挙げられる。そのよ うな中で、大阪市内からほど近い立地でありながら、未開拓地まだ目立っていた千里丘陵 に白羽の矢が立ったのである。そして、大阪万博を間近に控えた 1962 年に、千里ニュー 7
- 8. タウンはまちびらきを迎えた。この開発によって、現在の吹田市と豊中市にまたがる広大 な範囲において土地利用が大きく改変され、従来の小集落で生活を営み、農業中心で生計 を立てる自給自足の傾向が強い土地の性格から、大阪市内へのベッドタウンとしての性格 の強い地域へと完全に変貌した。一方、ニュータウン建設当時には既に集落がある程度ま とまって存在していた現在の上新田地区 ( 地区内の全丁目 ) 、および古江台 6 丁目につい てはニュータウンの開発予定地からは除外された。これらの地域ではニュータウンの開発 とは別個で民間によるマンション誘致を中心に宅地開発が進行している。 ・第 4 節 千里ニュータウンにおける水利構造の特徴 千里丘陵のような広大な敷地を宅地開発すること、すなわち既存の土地利用を大きく変 化させるにあたって生じる課題は、既存の水利構造をいかにして変化させるかということ である。水不足が叫ばれ続けたこの地域に突如として建設された膨大な住宅群を満たすだ けの水資源を確保することは非常に困難であり、地下水も地下 180m ないし 250m でよう やく貧弱な水源に達する程度にとどまる。当然ながら、既存の河川やため池を生活用水と して利用するのは望ましいとは言えない上に、貯留量も住宅全体をまかなうにはとてもほ ど遠く、非現実的であった。しかしながら、広大なニュータウンを建設するにあたっては 水道設備をただちに整備し、住民の誰もが気兼ねなく利用できるような水環境の整備が必 要となる。その結果、上水道としてのニュータウンの水源は丘陵南部を流れる淀川から水 道パイプ管を用いて受水することとなった。丘陵北部については、大阪府交野市の村野浄 水場から淀川を渡る形で設けられた受水管を経由して直接受水した上で蓮間配水池および 8
- 9. 柿木配水池へ送水を行い、丘陵南部については淀川沿いの庭窪浄水場から送水し、山田ポ ンプ場を経て豊中配水池、津雲配水池へ送水を行っている。 また、下水道の整備、および雨水の排水計画の確立が必要となった。千里ニュータウン 造成は基本的に元来の地形を生かす方向性で進行したため、下水道計画および雨水排水計 画は「地形現況をできるだけ生かした自然流下」の原則のもと計画された。具体的には、 地形の起伏等を考慮したうえで、天竺川排水区、山田川排水区、正雀川排水区、高川排水 区の 4 つの排水区を設定するというものだった。下水道計画の概要は、豊中市に属する天 竺川排水区内の下水は原田処理場に送水し、吹田市に属する山田川排水区、正雀川排水区、 高川排水区内の下水は正雀処理場へと送水されるといったものである。一方、雨水排水計 画としては、排水幹線の中に現在の蓮間ケ池、菩提池、牛ヶ首池の 3 つのため池を組み込 み、丘陵内の河川を経由した上で神崎川および安威川へと放流されている。一般的に、宅 地開発でアスファルト化が進行すると降雨はそのまま既存の河川に流れ込み、自然排水系 統の統合による流量の増大が大きな課題となる。その傾向は、地形の傾斜が顕著に見られ る丘陵部においては顕著である。とりわけ、天竺川、高川では降雨時の洪水が問題だった ことも踏まえた上で丘陵内の河川では改修工事が実施され、変化する雨水流水経路に対応 するものとなった。それに加え、自然排水系統の拡大に備えてニュータウン造成中はため 池とは別に 15 か所の遊水池が整備されたが、これらは一時的なものであったため 、 1969 年までに埋め立てられて消滅している。 以上のとおり、既存の土地を大規模に切り拓き、千里丘陵の面積の大部分を占めること となった千里ニュータウンでは、生活用水としての上水道は需要を満たすだけの安定性を 9
- 10. 鑑みた結果、水源は全て丘陵外部からまかなうことになったため、ため池が今まで有して いた農業用水・生活用水としての機能の必要性は低くなった。しかしながら、降水を一時 的にとどめておく従来の防災目的としての役割は重要視されており、雨水排水幹線の中に ため池が組み込まれることとなった。 第 3 章 千里丘陵内におけるため池の概要 ・第 1 節 ため池の総数の変化と位置関係の特質 ここでは、地形図によって確認できるため池の総数を論ずる。今回は、国土地理院発行 の 2 万 5 千分の 1 地形図を用いて、 1970 年と 2007 年での総数の変化を調査することと した。まず、総数を計算するにあたっての範囲設定をより明確にした上で調査するため、 千里丘陵の位置する吹田市・豊中市のおけるそれぞれの総数を計算することとした。その 結果、 1970 年発行の地図によれば、吹田市では 66 か所、豊中市では 56 か所のため池 の存在が確認できた。その一方、 2007 年発行の地図における吹田市のため池の総数は 33 か所、豊中市では 24 か所にまで減少していた。続いて、ニュータウン開発予定地内 のため池の総数を計算した結果、 1970 年、 2007 年ともに 16 か所という結果になり、 その総数自体に変化は見られなかった。 ・第 2 節 千里ニュータウン内における残置ため池の特質 ニュータウン内におけるため池の総数は、造成直後と現在でほぼ変化なしだったが、そ の原因を探るべく、現在残置されているため池の位置関係を調べ、その周辺環境の変化を 10
- 11. 述べるにあたってキーポイントとなるのが、ニュータウン造成時より計画的に保全された タケ林などの原生林、および整備された公園緑地である。ニュータウン敷地内全体では 37 か所の公園が整備されており、その内訳は地区公園が 3 か所、近隣公園が 14 か所、 児童公園が 20 か所である。地区公園に分類される千里北公園、千里中央公園、千里南公 園では、現在でも 3 か所全てにおいて保全されたため池 ( 順に蓮間池と水遠池、安場池、 牛ヶ首池 ) が存在する。続いて、近隣公園においては、現存する 14 か所中、佐竹公園、 桃山公園、樫ノ木公園、東町公園の 4 か所において、その内部にため池 ( 順に菩提池、春 日大池、樫ノ木池、深谷池 ) が確認できた。よって、ニュータウン開発予定地内に位置す るため池の中で、公園内に組み込まれたものは合計 7 か所であった。開発の過程において、 「地形現況をできるだけ生かした設計」が重視されるのは前提条件であったが、それに加 えて、公園緑地は街路樹の整備やある程度の原生林の保全とともに、新たなまちづくりの 「骨格」をなすものとして位置づけられた。その「骨格」が整っていくと同時に「緑豊か で住みよいまち」が展開され、ヒートアイランドや大気汚染、騒音などの公害から地域住 民を守るものとしても機能する。上記を踏まえて、開発予定地に残置されていたため池も 新たなまちづくりの「骨格」を構成する一員として枠組みに組み込まれ、公園緑地ととも にニュータウン内の環境を構築していったのである。 11
- 12. 第 4 章 千里丘陵におけるため池の位置づけ ・第 1 節 親水機能を生かしたため池の活用 ため池には主として「利水機能・環境保全機能・親水機能」の 3 つの機能を有している とされる 5) 。これらの中で、最近全国のため池で共通して見直されつつあるのが親水機能 である。さらに、親水機能は①水辺景観の形成、②レクリエーション空間の形成、③地域 コミュニティの形成、④文化継承、⑤学習・教育の 5 つに分類できるとされる。これら 5 つの条件すべてに共通することは、「人々と水との親睦を深める機能」である。ここから は、親水機能という視点に着目して、現在千里丘陵内に残置されているため池の有してい る存在意義について論じていきたい。親水機能を有していると考えられる千里丘陵内のた め池に共通する事項として、従来から存在する地域特有のタケ林、雑木林と隣接し、緑と 調和した良好な水辺景観を形成している点が挙げられる。また、公園の豊かな緑の中で、 地域住民が気軽に水とふれあえるよう、フェンスを低めに設定して展望性が確保されてい る他、池の周囲を公園内の散歩道として整備されているのが大きな特徴である。親水機能 が重視されて従来の環境から変化した実例として、吹田市佐竹台の佐竹公園に位置する菩 提池を挙げる。ここでは、今まで覆っていたフェンスが 1988 年に全て取り払われ、比較 的低い柵に取り換えられた。また、親水目的を果たすべく①遊歩道の整備、②水辺への植 物帯の設置、③休憩コーナーとしてのベンチの設置、④子どもが水遊びを楽しめるような 設計に変更された。この事業の背景として考えられるのは、ため池の親水化を求める当時 の地域住民のニーズの変化である。菩提池は従来、高いフェンスで覆われていたため池は それに隠れるかたちとなっており、特に小さな子どもの場合池を眺めることすら困難であ 12
- 14. なっている。山田西公園内に位置する高町池では、上記の外来魚の放流により、元来生息 していたモロコなどの魚類が全滅した他、同じく放流されたソウギョにより水草が食べつ くされた結果、水質悪化が問題となった。これを受け、平成 14 年には池の水をすべて抜 き取るかいぼりが行われ、外来魚は一斉に駆除された他、失われた水草は植え直された。 外来魚が問題となっているのは高町池に限らず、多くのため池で生態系の保護や外来魚の 放流、池内の釣りの禁止などが看板で呼びかけられている。ただ、釣りに関しては全ての ため池で禁止されている訳ではなく、南千里駅に近接する千里南公園に位置する牛ヶ首池 では、その面積の約半分が釣りスペースとして設定されている。以上の例から、ため池が 有するビオトープとしての役割を重視すべく釣りを禁止する箇所がある一方、公園でのレ ジャーの一環としてため池を釣り目的で活用している箇所も存在し、親水機能を有するた め池においてもその活用方針には差異が見られることが明らかとなった。 ・第 3 節 「残置」にとどまるため池の現状 千里ニュータウン内ではため池が公園内に組み込まれている例が多いが、その全ての箇 所で親水性が確保されているとはいえない。残置ため池の役割として新たに親水目的が見 出され、併設される公園とともに地域住民が水と親しみあい、地域の憩いの場としての新 たな存在意義が加わったため池が存在するその一方で、あくまで「残置」されるだけにと どまり、親水目的を果たしているとはとても言えないため池も存在するのが現状である。 その実例として、豊中市新千里東町に位置し、千里中央公園内部に存在する安場池を挙げ る。 2015 年 11 月に筆者が訪問したところ、周囲は公園としての付帯設備が整備されて 14
- 15. いるのに関わらず池の周囲は高いフェンスや雑木林で覆われ、池の姿を見ることすら困難 な状態であった。親水機能を有するため池では、池併設のベンチ、野鳥が止まるスペース、 子ども向けに水遊びができるスペースなどがよく確認できるが、そのようなものは未整備 であった。千里中央公園そのものは千里中央駅から徒歩圏内の公園であり、展望台や桜並 木を備えた公園そのものはレジャー施設として十分機能している。しかしその一方で、た め池はまさに「残置」された状態となり、本来有している機能を発揮出来ないままとなっ ている。その他、樫ノ木池、水遠池においても、公園内に位置していながら約140cmの高 いバリケードと柵が確認でき、池を眺めるのは背の低い子どもにとっては困難な状態であ ったため、親水機能を果たしているとは言い難かった。公園内に位置するにも関わらず、 ため池が残置でとどまってしまう要因として一つ考えられるのは、 1973 年に起こった桃 山公園内の春日大池で幼児が誤って池に転落した事故である。この事故では、家族から管 理責任を問われた市が民事訴訟で敗訴しており、その反省からため池に付加するべき最た る条件は安全性だとして、事故から 5 年の 1978 年までに、ニュータウン内の 11 か所の 池にフェンスを設けたのである 6) 。前述の菩提池の前例のように、親水目的をもつ池とし て生まれ変わる前例はあるが、フェンスを外して周囲を遊び場として整備することは、同 時に子どもが水に立ち入って遊ぶことによっての事故の危険性を高めることも意味してい る 7) 。現在では後述する計画により親水機能の価値を重要視する方針としているが、この 二律背反する条件を踏まえ、安全性と親水性を両立することが必須ではないかと考えられ る。公園緑地の整備とともにため池は新たなまちづくりの「骨格」を構成する一員として 枠組みに組み込まれ、地域住民の生活をより豊かなものとして位置づけられたのは事実で 15
- 16. あるが、親水機能を果たすことを目標に、付帯設備等を整備して人々が水と直接ふれ合え るようにため池に新たな役割や利用価値を付加するのと、公園の中に組み込まれたため池 を単に「残置」するのにとどまるのでは大きな差異が生じる。ニュータウン内の公園内に 位置するため池の中でも、親水目的が付加されるか否かの格差が生じているのが現状であ る。 ・第 4 節 吹田市におけるこれからの都市計画と水環境 最近では、ため池が有する機能を改めて見直し、地域の生活をより良いものにすべく活 用する動きが全国各地でみられる。例として、兵庫県の東播磨地域では、「いなみのため 池ミュージアム」が開設されている 8) 。具体的な活動内容として、ため池に対する地域住 民の理解を深め、水質と環境を保全するきっかけづくりを目的としたイベントの開催が挙 げられる。また、同地域には 2010 年 10 月時点で、 56 地区のため池協議会が設立され ている。協議会の大きな特徴として、構成員は高齢化傾向の強い農家にとどまらず、地域 の自治体や学校、企業、 NPO などを巻き込んだ形だということである。これにより、少 子高齢化が原因で引き起こされるため池の維持管理の放棄に歯止めをかけ、ため池周辺部 の清掃や草刈りなどで維持管理が持続されている。また、協議会の活動を通じて、水辺環 境の保全、および後世に向けてため池の重要性を伝達することにつながっている。 一方、千里丘陵のため池の大部分を抱える吹田市においては、まちづくりを進めるにあ たっての景観に対する理念が重要視され、生活の機能性・安全性と並列して、その美しさ や居住の快適さを追求した取り組みが続けられている。 1993 年には、地域の特色ある景 16
- 17. 観づくりを総合的・計画的に推進するため、「吹田市都市景観形成基本計画」が設定され、 これを 1 つの指標として景観整備を進めていくことになる。その後、景観形成に対する地 域住民の関心のさらなる高まりを受け、 2006 年には上記の計画を見直したうえで「景観 まちづくり計画」が策定された 9) 。この計画は、市民が主体となって住んでいるまちの課 題や将来像について考え、話し合い、合意形成を図っていくための指標を示す他、既存の 「吹田市都市景観形成基本計画」の将来像の実現に向けての方向性を示す役割を持ってい る。 ニュータウン建設前から存在するため池も例にもれず、都市計画を進行させるにあたっ てその処遇を決めることになる。「景観まちづくり計画」では、河川・ため池の今後の処 遇方針として、まちの生い立ちを伝え、心地よさが感じられる水辺空間をはぐくむことを 目標として定めた。具体的には 8 項目におよぶ方針10) が示されているが、要約すると①水 質の保全や改善・維持管理の促進、②親水性のある水辺空間の創造促進の 2 つに分類でき る。 現在の取り組みとして、目標①を達成すべく、「吹田市第 2 次環境基本計画」に基 づいて、吹田市内の 17 か所のため池の水質が年度ごとに測定されているが、これは 2007 年現在において吹田市内に現存するため池の約半分が水質調査を受けている計算に なる。 2014 年の測定では、すべてのため池において国の定める環境基準をクリアしてお り、引き続きの水質管理が望まれる。水質測定の対象地の特徴として、周囲を公園として 整備されているため池が目立つことが挙げられ、蓮間池、水遠池、ピアノ池、牛ヶ首池、 菩提池、高町池、春日大池、王子池、釈迦ヶ池の 9 つがこれに該当する11) 。一方、周囲を 公園として整備されていないため池は水質測定の対象から除外されている場合が目立つ。 17
- 19. れて親水性を生かせていないため池も存在する。この背景には安全性の確保が横たわって おり、それを疎かにすることは出来ない。今後は、吹田市の「景観まちづくり計画」によ って積極的なため池の親水性確保が期待できるが、それと同時に安全性も両立出来るかと いうことが、日本各地に広がる水辺環境を改善するにあたっての可能性を左右する一つの 指標になるのではと考える。また、外来魚の放流によるため池のビオトープの破壊や公園 利用者のマナー悪化によるため池へのごみ投棄も課題であり、これは水環境に対しての 人々の軽視が原因だと考えられる。この現状を阻止するとともに、親水性をより効果のあ るものとし、水利環境の保全へとつなげるには、現在の市の方針のもと親水性を創出する のはもちろん、その結果として、水環境に対しての人々の理解とその環境保全への関心や 自覚を促すことが必要である。 参考文献・資料 ・「千里ニュータウンの建設」、大阪府、 1970-3 ・内田和子『ため池―その多面的役割と活用―』、農林統計協会、 2008 ・内田和子『日本のため池―防災と環境保全―』、海青社、 2003 ・川内 三『大阪平野の溜池環境 変貌の歴史と復元』、和泉書院、 2009-12-25 ・北畠 潤一「大阪平野の北部丘陵地における住宅化 -1945~1979 年 - 」、地理学評論 57 、 1984 、 703-719 頁 ・篠沢 健太、宮城 俊作、根本 哲夫著「千里ニュータウンにおける集水域の構造変容と公 19
- 20. 園緑地系統の関連」、ランドスケープ研究 70(5) 、 2007 、 647-652 頁 ・宮城 俊作「千里丘陵の開発における地形の取扱いと自然環境の構造」 2006-5-1 ・南埜 猛「溜池の存続とその維持管理をめぐる取り組み ―兵庫県東播磨地域を事例と して―」、経済地理学年報 第 57 巻、 2011 、 75-89 頁 ・毎日新聞「千里ニュータウン物語」、 1988-10-18 ・「郷土の歩み 人々の生活 12 号」、 1974-11 ・吹田市「吹田市景観まちづくり計画(新・吹田市都市景観形成基本計画)」、吹田市都 市整備部都市整備室、 2007-3 ・http://www.city.suita.osaka.jp/ 最終閲覧日 2015-12-10 ・ http://www.pref.kagawa.jp/ 最終閲覧日 2015-10-20 20