ボトムアップで進める地域振興
•
0 likes•684 views
2016年12月17日(水)|藤原直哉理事長(第18回 NSP時局ならびに日本再生戦略講演会 午後の部 ・後半) 音声・動画は、NSPサイト内アーカイブにて公開中です。https://nipponsaisei.jp/archives/91 ◆認定NPO法人日本再生プログラム推進フォーラム(NSP)は、NSP会員の皆さまからいただきました年会費・ご寄附を原資にアーカイブづくりをしています。ありがとうございます。
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
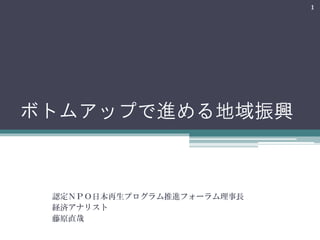
More Related Content
Similar to ボトムアップで進める地域振興
Similar to ボトムアップで進める地域振興 (7)
【講演】なぜ今、田舎暮らしに注目があるのか。 全国事例をふまえて@大ナゴヤ大学(2015年3月8日)

【講演】なぜ今、田舎暮らしに注目があるのか。 全国事例をふまえて@大ナゴヤ大学(2015年3月8日)
More from 日本再生プログラム推進フォーラム
More from 日本再生プログラム推進フォーラム (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
My Inspire High Award 2024「スーパーマーケットで回収されたキャベツ外葉は廃棄されているの?」

My Inspire High Award 2024「スーパーマーケットで回収されたキャベツ外葉は廃棄されているの?」
My Inspire High Award 2024「なぜ人は他人と違うところがあってもそれをなかなか誇れないのか?」

My Inspire High Award 2024「なぜ人は他人と違うところがあってもそれをなかなか誇れないのか?」
My Inspire High Award 2024「Yakushima Islandってなんか変じゃない?」.pdf

My Inspire High Award 2024「Yakushima Islandってなんか変じゃない?」.pdf
Establishment and operation of medical corporations.pdf

Establishment and operation of medical corporations.pdf
ボトムアップで進める地域振興
- 11. 今後の日本と世界の方向性 グローバル主義から地域・民族自立へ : 世界最適生産・最適調達 → 地域・民族ごとの個性化 経済の先祖がえり : 金融と市場原理主義 → 雇用が第一 経済の物差し : 生産と消費 → 所得と雇用 少子高齢化時代の本格化 : 量・即戦力 → 質・熟練 資源・食料・エネルギー制約の本格化 : 安価で大量の世界調達 → 地域自給と戦略的低エネルギー 政府機能の衰退、財政の行き詰まり : 官と民の対峙 → 新しい公共 11
- 15. 仕事の原点 15
- 16. 日本の村々に 人たちが 小さい小さい よろこびを 追っかけて 生きている ああ 美しい 夕方の 家々の 窓の あかりのようだ 昭和62年12月26日 椋鳩十 政治の原点 16
- 17. 地方振興に欠くことのできない力 • ボランティア精神にあふれたリーダーたち • 地域の継続と発展に向けた強い意志 • 人々が集える共同体 • チームワークを生かした実践活動 • 外部との広範な交流とコミュニケーション • イノベーションを起こしていく勇気と行動力 17
